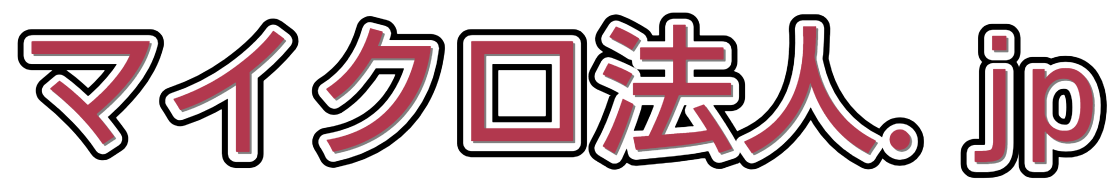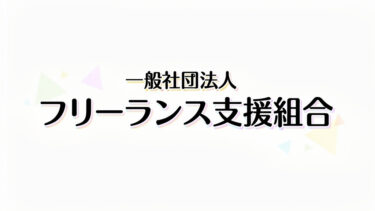マイクロ法人と合同会社の違いでお悩みですか?
結論から言うと、マイクロ法人は法人形態の名称ではなく、合同会社などを活用した運営手法のことです。
本記事では、なぜマイクロ法人に設立コストの安い合同会社が選ばれるのかを徹底解説。
社会保険料削減などの節税メリットから、設立・運営コスト、手続きまで比較し、あなたが最適な選択をするための知識を提供します。
マイクロ法人と合同会社 そもそも何が違うのか
「マイクロ法人と合同会社の違い」というテーマで情報を探している方の多くは、個人事業主からの法人成りや、副業の規模拡大に伴う節税対策を検討されているのではないでしょうか。
しかし、この二つの言葉は、実は比較の土俵が異なります。
まずはその根本的な違いを理解することが、最適な選択への第一歩です。
結論から言うと、マイクロ法人は法律上の法人形態ではなく、事業規模や運営スタイルを表す「呼称」です。
一方で、合同会社は会社法で定められた「法人形態の一つ」です。
つまり、「乗り物」という大きな括りの中に「軽自動車」という種類があるように、「マイクロ法人」という概念の中に「合同会社」という選択肢が含まれる、という関係性になります。
マイクロ法人の正体は合同会社や株式会社
「マイクロ法人」という言葉に、法律上の明確な定義はありません。
一般的に、社長一人、あるいは家族などごく少人数で運営される小規模な法人を指す言葉として使われています。
特に、個人事業主やフリーランスが、主に社会保険料の負担を軽減する目的で設立する法人を指すケースが多いです。プライベートカンパニーとも呼ばれます。
マイクロ法人はあくまで「状態」や「目的」を表す言葉であるため、その法人格(法的な器)としては、既存の会社形態を選ぶ必要があります。
その主な選択肢が「合同会社」と「株式会社」です。
つまり、「マイクロ法人を設立する」とは、具体的には「節税などの目的を達成するために、合同会社や株式会社といった形態で小さな会社を設立する」ことを意味します。
このため、「マイクロ法人と合同会社、どちらが良いか?」という問いは、「マイクロ法人を設立するにあたり、法人形態は合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきか?」という問いに置き換えて考えるのが適切です。
合同会社の特徴とメリットを解説
それでは、マイクロ法人の設立形態として選ばれることが多い「合同会社」とは、どのような特徴を持つ会社なのでしょうか。
合同会社は、2006年の会社法施行によって導入された比較的新しい会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルにしています。
株式会社と比較することで、その特徴がより明確になります。
合同会社と株式会社の主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(最低額) | 約6万円~(登録免許税6万円~) | 約20万円~(登録免許税15万円~、定款認証手数料など) |
| 出資者と経営者 | 原則として一致(出資者=社員=経営者) | 分離可能(出資者=株主、経営者=取締役) |
| 意思決定機関 | 社員総会(定款で自由に設計可能) | 株主総会・取締役会 |
| 利益の配分 | 定款で自由に決定可能(出資比率と無関係に配分できる) | 原則として出資比率(株式の保有数)に応じて配分 |
| 役員の任期 | 任期なし(更新手続き不要) | 原則2年(最長10年まで伸長可能、任期ごとに登記が必要) |
| 決算公告の義務 | 義務なし | 義務あり(官報掲載などで毎年費用が発生) |
| 社会的信用度 | 株式会社に比べるとやや低い傾向 | 一般的に高い |
この表からわかるように、合同会社の最大の特徴は、設立・運営コストの低さと経営の自由度の高さにあります。
具体的には、株式会社の設立に必要な定款の認証が不要で、登録免許税も最低6万円からと安価です。
また、役員の任期がないため更新登記の手間や費用がかからず、決算公告の義務もないため、ランニングコストを抑えることができます。
これらの特徴から、一人社長や家族経営など、迅速な意思決定と柔軟な運営が求められる小規模ビジネスとの相性が非常に良く、多くのマイクロ法人が設立形態として合同会社を選択しています。
【節税メリットで比較】マイクロ法人と合同会社の違い

「マイクロ法人」と「合同会社」を比較する際、節税メリットは最も重要な論点の一つです。
しかし、前述の通りマイクロ法人は法人形態の名称ではなく、その実体は合同会社や株式会社です。
したがって、ここでの比較は「マイクロ法人(実体は合同会社)を設立した場合」と「個人事業主のまま事業を継続した場合」の税制・社会保険上の違いと捉えるのが正確です。
この章では、マイクロ法人として合同会社を設立することで得られる、具体的な節税メリットを深掘りしていきます。
最大のメリットは社会保険料の削減
マイクロ法人を設立する最大の目的と言っても過言ではないのが、社会保険料(健康保険・厚生年金)の負担を最適化できる点です。
個人事業主が加入する国民健康保険料は前年の所得に応じて算出され、所得が増えるほど保険料も高くなります。
一方、法人の役員が加入する社会保険料は、法人から受け取る「役員報酬」の金額(標準報酬月額)に基づいて決まります。
この仕組みを利用し、個人事業主としての事業所得はそのままに、マイクロ法人を設立して役員に就任し、その法人からの役員報酬を低く設定します。
すると、社会保険料の算定基準となるのはその低い役員報酬額だけになるため、社会保険料の総額を大幅に削減できるのです。
例えば、個人事業で年間800万円の所得がある場合、国民健康保険料は高額になります。
しかし、事業の大部分(例:750万円)は個人事業の所得とし、マイクロ法人を設立して一部の事業(例:50万円の売上)を移管し、法人から月額4.5万円(年間54万円)の役員報酬を受け取る形にすれば、社会保険料は月額4.5万円を基準に計算されるため、劇的に安くなります。
役員報酬の設定が節税のポイント
社会保険料を最適化するための役員報酬は、いくらに設定すれば良いのでしょうか。
ポイントは、社会保険の加入義務が発生し、かつ保険料が最も低くなる金額帯を狙うことです。
一般的には、健康保険・厚生年金の保険料が最も低い等級となる月額6万円前後に設定するケースが多く見られます。
これにより、厚生年金に加入できるというメリットを享受しつつ、保険料負担を最小限に抑えることが可能です。
ただし、注意点もあります。
役員報酬は、事業年度の開始から3ヶ月以内に決定し、その年度中は原則として変更できない「定期同額給与」というルールがあります。事業の状況を考慮せずに安易に金額を決めると、後から変更できずに困る可能性もあるため、慎重な計画が必要です。
また、役員報酬を低く抑えるということは、その分法人の利益が増えることを意味します。
その利益には法人税が課税されるため、税金全体のバランスを見ながら最適な報酬額を決定することが重要です。
法人税と所得税の税率の違い
マイクロ法人を設立すると、所得を「個人事業の事業所得」と「法人の役員報酬(給与所得)」に分散できます。
これにより、税率の違いを活かした節税が可能になります。
個人事業主の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されており、最大で45%に達します。
一方、法人税は所得金額にかかわらず税率がほぼ一定です(中小法人の場合、所得800万円までは軽減税率が適用)。
以下の表は、所得税と法人税の税率構造を比較したものです。
| 税金の種類 | 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得税(個人) | 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | |
| 4,000万円超 | 45% | |
| 法人税(中小法人) | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 年800万円超の部分 | 23.2% |
※上記は2024年4月時点の税率です。復興特別所得税・住民税・事業税などは考慮していません。
個人事業主として高い所得を得て高い累進課税率が適用されるよりも、法人を設立して所得を分散させた方が、トータルの税負担を抑えられるのです。
一般的に、個人事業の課税所得が800万円~900万円を超えるあたりから、法人化による節税効果が大きくなると言われています。
さらに、役員報酬は「給与所得」となるため、給与所得控除が適用されます。
これにより、個人事業の事業所得と給与所得の両方で控除が受けられるため、課税対象となる所得を効率的に圧縮することが可能です。
【コストで比較】マイクロ法人と合同会社の違い

マイクロ法人を設立する上で、多くの方が気になるのが「コスト」ではないでしょうか。
コストは、設立時に一度だけかかる「初期費用(設立費用)」と、法人を維持するために継続的にかかる「ランニングコスト」の2つに大別できます。
マイクロ法人の実体は合同会社や株式会社であるため、ここでは主に合同会社と株式会社のコストを比較しながら解説します。
設立費用を比較 合同会社は登録免許税が安い
法人を設立する際には、定款の作成や法人登記など、さまざまな手続きに費用がかかります。
結論から言うと、設立費用を安く抑えたいなら合同会社が圧倒的に有利です。株式会社と比較して、最低でも14万円以上の差が生まれます。
具体的な費用の内訳を下の表で比較してみましょう。
ここでは、近年主流となっている電子定款を利用した場合の費用を記載しています。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款に貼る収入印紙代 | 0円 | 0円 | 電子定款の場合。紙の定款では4万円が必要。 |
| 定款の認証手数料 | 不要 | 3万円~5万円 | 資本金の額によって変動。合同会社は認証が不要なため0円。 |
| 登録免許税 | 6万円~ | 15万円~ | 資本金の額×0.7%で計算。最低額が合同会社6万円、株式会社15万円。 |
| 合計(最低額) | 6万円 | 18万円~20万円 | 合同会社の方が12万円以上安い。 |
表からわかる通り、最も大きな違いは「定款の認証手数料」と「登録免許税」です。
合同会社は公証人による定款認証が不要なため、その手数料がかかりません。
さらに、法務局へ支払う登録免許税も、株式会社の最低15万円に対して合同会社は最低6万円と、半分以下に設定されています。
これらの理由から、マイクロ法人のようにスモールスタートを目指す場合、初期費用を大幅に削減できる合同会社が最適な選択肢となりやすいのです。
ランニングコストを比較 税理士費用や法人住民税
法人を設立すると、個人事業主の時にはなかった種類のコストが毎年発生します。
特に注意すべきなのが、赤字でも支払い義務が生じる「法人住民税均等割」です。
マイクロ法人(合同会社)を運営していく上で、主にかかるランニングコストは以下の通りです。
| 項目 | 費用の目安(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 法人住民税(均等割) | 約7万円~ | 会社の利益が赤字でも必ず発生する税金。自治体や資本金の額によって変動。 |
| 税理士費用 | 20万円~40万円程度 | 顧問契約や決算申告のみなど、依頼内容による。自分で申告すれば0円も可能だが、専門知識が必要。 |
| 会計ソフト利用料 | 2万円~6万円程度 | クラウド会計ソフトが主流。プランによって料金が異なる。 |
| 社会保険料 | 役員報酬の約30% | 会社と個人で折半して負担。マイクロ法人の節税スキームの要となる部分。 |
ランニングコストにおいて、合同会社と株式会社で大きな差はありません。
しかし、個人事業主と比較すると、法人住民税の均等割という固定費が加わる点は大きな違いです。
法人住民税の均等割は、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の法人であれば、多くの自治体で年間約7万円に設定されています。
これは法人として存在する以上、利益が出ていなくても納税義務があるため、マイクロ法人を設立する際には必ず念頭に置いておくべきコストです。
また、法人の税務申告は個人事業主の確定申告よりも複雑なため、税理士に依頼するのが一般的です。
節税対策や手続きの手間を考えると、税理士費用は必要経費と捉えるのが良いでしょう。
最近では、マイクロ法人のような小規模な会社に特化した安価なプランを提供している税理士事務所も増えています。
【手続きと運営で比較】マイクロ法人と合同会社の違い
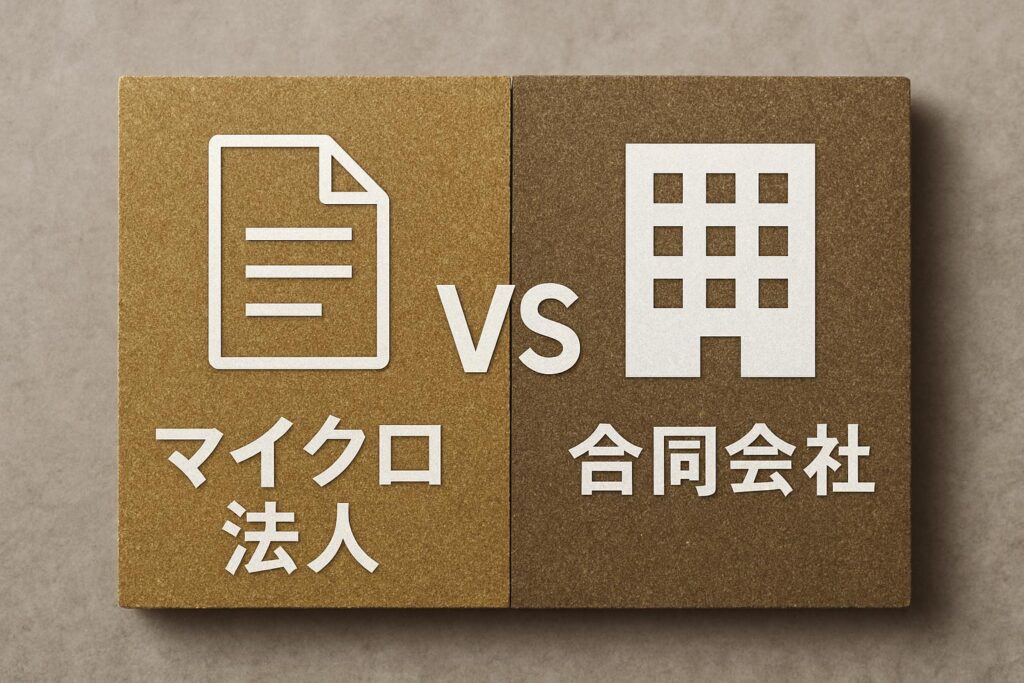
マイクロ法人を設立する際、節税メリットやコストだけでなく、設立手続きの手間や設立後の運営のしやすさも重要な比較ポイントです。
マイクロ法人の実体は合同会社や株式会社であるため、ここでは「合同会社」と「株式会社」を比較対象として、手続きと運営面の違いを具体的に解説します。
設立手続きの流れと必要書類
法人の設立は、定款の作成から始まり、登記申請を経て完了します。
この一連の流れにおいて、合同会社と株式会社では手続きの煩雑さに大きな違いがあります。
特に大きな違いは、株式会社で必須となる「定款の認証」が合同会社では不要である点です。
これにより、合同会社は時間と費用を抑えてスピーディーに設立できます。
具体的な手続きの流れと必要書類を比較してみましょう。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 定款の作成 | 必要(電子定款も可能) | 必要(電子定款も可能) |
| 定款の認証 | 不要 | 必要(公証人役場での認証) 認証手数料として3万円~5万円がかかる。 |
| 資本金の払込 | 出資者(社員)個人の銀行口座に払い込み、その通帳のコピー等で証明する。 | 発起人個人の銀行口座に払い込み、その通帳のコピー等で証明する。 |
| 登記申請(法務局) | 必要書類を揃えて法務局へ申請する。 | 必要書類を揃えて法務局へ申請する。 |
| 主な必要書類 | ・登記申請書 ・定款 ・代表社員の印鑑証明書 ・資本金の払込証明書 ・印鑑届書 など | ・登記申請書 ・認証済みの定款 ・発起人の決定書 ・役員の就任承諾書 ・役員の印鑑証明書 ・資本金の払込証明書 ・印鑑届書 など |
| 設立までの期間(目安) | 約1週間~2週間 | 約2週間~3週間 |
このように、合同会社は公証人役場での手続きが不要な分、シンプルかつ迅速に設立が可能です。
一人社長のマイクロ法人として、とにかく早く事業を開始したい場合には、合同会社の手軽さが大きなメリットとなります。
経営の自由度と意思決定プロセス
会社の運営において、誰がどのように物事を決めるのかという意思決定プロセスは非常に重要です。
この点において、合同会社と株式会社は組織の根本的な構造が異なります。
株式会社は「所有と経営の分離」が原則で、会社の所有者である「株主」と、経営を行う「取締役」が分かれています。
一方、合同会社は「所有と経営の一致」が原則で、出資者である「社員」が自ら経営(業務執行)を行います。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 最高意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
| 意思決定の方法 | 原則として、総社員の同意。 (定款で過半数など別段の定めも可能) | 株主総会での多数決(議決権は保有株式数に比例)。 業務執行は取締役会(設置している場合)で決定。 |
| 役員の任期 | 任期なし(定款で定めることは可能) | 原則2年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可能)。任期満了ごとに登記(役員変更登記)が必要。 |
| 利益の配分 | 定款で自由に定められる。 出資額に関係なく、貢献度に応じて配分することも可能。 | 原則として、出資比率(保有株式数)に応じて配当される。 |
マイクロ法人のように一人社長で運営する場合、合同会社の迅速な意思決定プロセスは非常に効率的です。
また、役員の任期がなく、任期ごとの変更登記が不要な点も、管理コストを抑えたいマイクロ法人にとって魅力的なポイントと言えるでしょう。
資金調達方法と社会的信用度
将来的な事業拡大を見据える場合、資金調達の選択肢と社会的な信用度は無視できない要素です。
この点では、株式会社に分があると言えます。
株式会社は「株式」を発行することで、広く一般から出資を募ることが可能です。
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を受け入れるなど、多様な資金調達手段があります。
一方、合同会社は株式を発行できないため、資金調達は社員からの追加出資や金融機関からの融資が基本となります。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 主な資金調達方法 | ・社員からの追加出資 ・金融機関からの融資 ・社債発行 | ・株主からの追加出資(増資) ・金融機関からの融資 ・社債発行 ・第三者割当増資など新株発行による調達 |
| 社会的信用度 | 一般的に株式会社よりは低いと見なされることがある。ただし、近年は知名度も向上しており、取引に支障が出るケースは少ない。 | 歴史が長く、知名度も高いため、一般的に社会的信用度は高い。上場を目指すことも可能。 |
| 役員(経営者)の名称 | 代表社員、業務執行社員 | 代表取締役、取締役 |
社会的信用度については、一般的に「株式会社」の方が高いと認識されています。
特に、歴史の長い企業との取引や、特定の許認可が必要な事業では、株式会社であることが有利に働く場合があります。
しかし、マイクロ法人として個人向けのサービスや小規模なBtoB取引を行う上では、合同会社であることが不利になる場面はほとんどありません。
近年では、Apple Japan合同会社やグーグル合同会社のように、世界的な大企業が日本法人として合同会社の形態を選択している例もあり、その認知度と信頼性は向上しています。
マイクロ法人に合同会社が選ばれる理由

マイクロ法人を設立する目的は、多くの場合、事業規模の拡大よりも社会保険料の最適化といった節税メリットにあります。
この目的を達成するためには、できるだけ設立・運営コストを抑え、シンプルな形態で法人を維持することが重要です。
その点で、合同会社はマイクロ法人と非常に相性が良く、多くの個人事業主やフリーランスに選ばれています。
ここでは、なぜマイクロ法人として株式会社ではなく合同会社が最適解となりうるのか、その具体的な理由を2つの側面から深掘りしていきます。
低コストで法人格を取得できる手軽さ
マイクロ法人を設立する上で、最初のハードルとなるのが設立費用です。
特に、個人事業主から法人化(法人成り)する場合、できるだけ初期投資を抑えたいと考えるのが自然でしょう。
合同会社は、株式会社と比較して設立時の法定費用(実費)を大幅に抑えられるという大きなメリットがあります。
具体的に、株式会社と合同会社の設立にかかる法定費用を比較してみましょう。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 定款認証 | 不要 | 3万円~5万円(公証人手数料) |
| 登録免許税 | 最低6万円(資本金の0.7%) | 最低15万円(資本金の0.7%) |
| 定款に貼る収入印紙代 | 電子定款の場合は0円(紙定款の場合は4万円) | |
| 合計(電子定款の場合) | 6万円~ | 約20万円~ |
上記のように、合同会社は株式会社の3分の1以下の費用で設立が可能です。
特に、マイクロ法人の場合、公証人による定款認証が不要である点は、手続きの手間と費用の両面で大きな魅力です。
約14万円以上の差額は、事業の運転資金に回せる貴重な資金となります。
さらに、ランニングコストの面でもメリットがあります。
株式会社の役員(取締役)には任期があり、最長でも10年ごとに役員変更の登記が必要です(費用:1万円~)。
一方、合同会社の社員には任期がないため、役員変更登記の手間とコストが原則として発生しません。
これも、長く法人を維持していく上で見逃せないポイントです。
一人社長でも運営しやすいシンプルな組織形態
マイクロ法人は、社長一人、あるいは家族だけで運営するケースがほとんどです。
そのため、組織の構造や運営ルールはできるだけシンプルであることが望まれます。
合同会社は、その点でもマイクロ法人に最適な会社形態です。
主な理由は以下の通りです。
- 迅速な意思決定が可能
合同会社は「所有と経営が一致」しており、出資者である「社員」が会社の経営を行います。株式会社のように、意思決定のために株主総会を開催する必要がありません。事業の方針転換や重要な契約など、あらゆる意思決定をスピーディーに行えるため、変化の速いビジネス環境にも柔軟に対応できます。 - 機関設計の自由度が高い
株式会社では取締役会や監査役といった機関の設置が求められる場合がありますが、合同会社にはそのような義務がありません。組織構造が非常にシンプルで、一人社長(代表社員)だけで完結できるため、管理コストや手間を最小限に抑えられます。 - 利益分配を自由に決められる
株式会社では、利益の配当は出資額(株式の保有割合)に応じて行われます。しかし、合同会社では、定款で定めることにより、出資額に関わらず、事業への貢献度などに応じて利益の分配割合を自由に決めることができます。一人社長の場合はあまり関係ありませんが、将来的に技術やノウハウを持つパートナーと組む際に、柔軟な報酬設計が可能になるというメリットがあります。
これらの特徴から、合同会社は法人運営の経験がない方でも管理しやすく、まさに「一人社長」のためにあるような会社形態だと言えるでしょう。
合同会社でマイクロ法人を設立する際の注意点
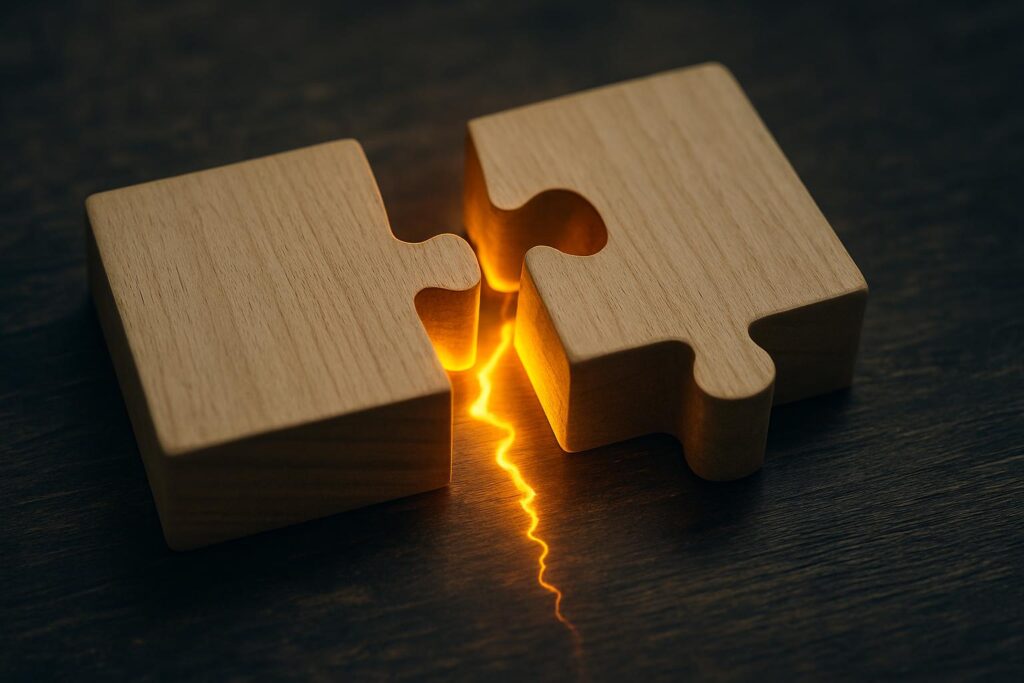
合同会社を利用してマイクロ法人を設立することは、節税や社会保険料の最適化において非常に有効な手段です。
しかし、メリットばかりに目を向けていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
ここでは、マイクロ法人を設立・運営する上で必ず押さえておきたい3つの重要な注意点を詳しく解説します。
個人事業との事業内容の明確な分離が必要
個人事業主がマイクロ法人を設立し、いわゆる「二刀流」で事業を行う場合、最も注意すべき点が個人事業と法人事業の明確な分離です。
この分離が曖昧だと、税務調査で「租税回避行為」とみなされ、法人の存在を否認されるリスクがあります。
税務署から法人が実態のないペーパーカンパニーだと判断された場合、法人の売上や経費はすべて個人事業主のものとして合算され、修正申告と追徴課税(過少申告加算税や延滞税など)が課せられる可能性があります。
このような事態を避けるため、以下の点を徹底しましょう。
- 事業内容の区別: 個人事業で行う事業と、マイクロ法人で行う事業を明確に分けます。例えば、個人事業でWebライティング、法人でWebサイト制作やコンサルティングを行うなど、客観的に見て異なる事業であることが重要です。
- 取引の分離: 法人としての契約書、請求書、領収書を必ず用意し、個人事業の取引と混同しないようにします。特に、個人事業の売上の一部を法人に付け替えるといった行為は絶対に避けるべきです。
- 資産・口座の分離: 法人名義の銀行口座を開設し、事業資金の管理を徹底的に分けます。個人の生活費や個人事業の経費を法人口座から支払うことは厳禁です。
- 経費の按分: 自宅を事務所として利用する場合など、個人と法人で共用する経費がある場合は、事業での使用実態(使用面積や時間など)に応じて合理的な基準で家事按分を行う必要があります。
形式的に法人を設立するだけでなく、事業の実態として独立した存在であることを証明できる状態を常に維持することが、税務上のリスクを回避する鍵となります。
扶養から外れる場合の判断基準
マイクロ法人の役員報酬を低く設定することで、社会保険料を抑えるのが大きなメリットですが、配偶者の扶養に入っている方がマイクロ法人を設立する際には注意が必要です。
一般的に、健康保険の被扶養者でいられる収入の基準として「年収130万円の壁」が知られています。
しかし、法人を設立した場合、この基準だけで判断するのは危険です。
最も重要なポイントは、法人はたとえ社長一人であっても、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となるという点です。
つまり、法人を設立した時点で、役員報酬の額にかかわらず、その法人は社会保険に加入する義務が生じます。
そして、法人の代表者(社長)自身も被保険者となるため、原則として配偶者の扶養から外れることになります。
ただし、役員報酬が極端に低いなど、事業の実態によっては日本年金機構の判断で加入が認められないケースも稀にありますが、基本的には「法人設立=社会保険加入義務発生=扶養から外れる」と理解しておくのが安全です。
扶養内でいられることを前提にマイクロ法人を設立すると、後から想定外の社会保険料負担が発生する可能性があるため、設立前に必ず年金事務所や専門家へ確認することをおすすめします。
赤字の場合の法人住民税均等割
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税はかかりません。
しかし、法人はたとえ事業が赤字であっても、支払わなければならない税金があります。
それが「法人住民税の均等割」です。
法人住民税は、法人の所得に応じて課税される「法人税割」と、所得にかかわらず資本金や従業員数に応じて定額で課税される「均等割」の2つで構成されています。
このうち「均等割」は、法人がその地域に存在することで受ける行政サービス(道路の整備、消防・救急など)に対する会費のようなもので、利益がゼロや赤字であっても支払い義務が生じます。
均等割の金額は、法人の資本金の額と従業員数、そして事業所の所在地(都道府県・市町村)によって異なりますが、マイクロ法人で最も一般的なケース(資本金1,000万円以下、従業員50人以下)の場合、最低でも年間約7万円(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)がかかります。
これは法人を維持するための最低限のランニングコストとして、必ず念頭に置いておく必要があります。
| 資本金等の額 | 従業員数 | 法人都民税(年額) | 法人事業税・特別法人事業税(年額) | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 70,000円 | – | 70,000円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 180,000円 | – | 180,000円 |
※上記は東京都の例です。税額は自治体によって異なる場合がありますので、詳細は各自治体のウェブサイトでご確認ください。
マイクロ法人を設立するということは、こうした赤字でも発生するコストを毎年負担し続ける覚悟が必要であることを理解しておきましょう。
まとめ
マイクロ法人は社会保険料の最適化を目指す手法で、その設立形態には合同会社が適しています。
株式会社に比べ設立費用が安く、運営の自由度も高いため、コストを抑えたい一人社長に最適です。
役員報酬の工夫で節税効果は高まりますが、個人事業との明確な事業分離や、赤字でも課される法人住民税均等割などの注意点も理解しておく必要があります。
メリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に合った法人形態を選択しましょう。