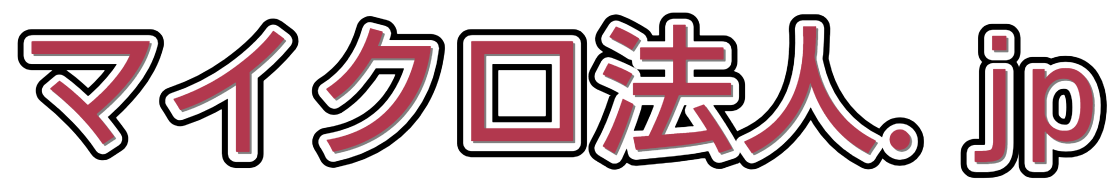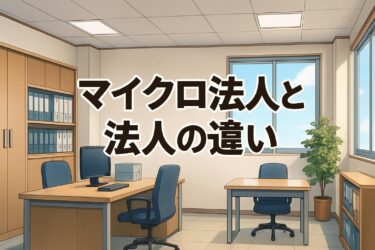法人成りを検討する際、「今の個人事業も一部残した方が得策か?」と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、法人成り後も個人事業を残すことは可能です。
この記事では、所得分散による節税などのメリット、経理が煩雑になるデメリットを比較し、具体的な手続きの流れを解説します。
さらに、税務調査で否認されないために最も重要な5つの注意点を詳しくお伝えし、失敗しないための判断基準を明確にします。
結論 法人成り後も個人事業を残すことは可能
多くの方が疑問に思われる「法人成りした後、個人事業主としての活動を続けても良いのか?」という点について、結論から申し上げます。
法人成り後も、個人事業をそのまま残して事業を継続することは法的に全く問題ありません。
会社法やその他の法律において、株式会社の代表取締役が個人事業主を兼業することを禁止する規定は存在しません。
そのため、例えば複数の事業を運営している方が、そのうちの一つの事業だけを法人化し、残りの事業は個人事業として続ける、といった柔軟な選択が可能です。
具体的には、以下のようなケースで個人事業を残す選択が検討されます。
- 将来性が高く、大きく成長させたい主力事業のみを法人化し、他の小規模な事業は個人事業として継続するケース
- 許認可の種類が異なり、法人と個人で事業を分けた方が管理しやすいケース(例:建設業と飲食業など)
- 法人としての信用が必要なBtoB事業と、個人名で活動したいBtoC事業を分けて運営するケース
このように、事業戦略上の理由から、法人と個人事業を併存させることには多くのメリットが存在します。
しかし、その一方で、手続きや税務上の注意点を正しく理解しておかなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性も否定できません。
ただし税務上のリスク管理が重要
法人成り後も個人事業を残すことが可能である一方、最も注意しなければならないのが「税務上のリスク」です。
安易に法人と個人事業を併存させると、税務調査の際に「租税回避行為(不当に税金を安くしようとする行為)」と見なされ、厳しい指摘を受ける可能性があります。
税務署が特に問題視するのは、法人と個人事業を併用することで、意図的に所得を分散させたり、経費を付け替えたりして、納税額を不当に操作していると疑われるケースです。
具体的に指摘されやすいポイントは以下の通りです。
| 指摘されやすいポイント | 具体的なNG例 | 税務署から見なされる可能性 |
|---|---|---|
| 事業実態の曖昧さ | 法人と個人で実質的に同じ事業を運営し、利益が少なくなるように意図的に売上を振り分けている。 | 所得分散を目的とした租税回避 |
| 個人と法人の取引価格 | 法人が個人事業主である自分に対して、市場価格から著しく乖離した高額な業務委託費や家賃を支払っている。 | 同族会社等の行為計算の否認(法人税法第132条) |
| 経費区分の不明確さ | 本来は法人が負担すべき交際費や消耗品費を、個人事業の経費として計上し、法人の利益を不当に多く見せている。 | 費用の付け替えによる所得操作 |
これらのリスクを回避するためには、なぜ法人と個人事業を併存させる必要があるのか、その客観的で合理的な理由を明確に説明できる状態にしておくことが極めて重要です。
「節税のため」という理由だけでは、税務署を納得させることは困難です。
事業内容や取引形態に応じて、法人と個人それぞれの役割を明確に区分し、すべての取引を第三者が見ても正当だと判断できる形で記録・管理する必要があります。
法人成りで個人事業を残す3つのメリット

法人成り後もあえて個人事業を残すという選択には、単に手続きを簡略化する以上の戦略的なメリットが存在します。
適切に活用すれば、税負担の軽減や経営の安定化に大きく貢献する可能性があります。
ここでは、その代表的な3つのメリットについて、具体的な仕組みとともに詳しく解説します。
メリット1 所得分散による節税効果
法人と個人事業の両方で事業を行う最大のメリットは、所得を分散させることによる節税効果です。
これは、個人に適用される「所得税」と法人に適用される「法人税」の税率構造の違いを利用した手法です。
個人の所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。
一方、法人税は基本的に一定の税率(資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円以下の部分は軽減税率)が適用されます。
そのため、個人事業主として得た高い所得をすべて個人の所得として計上するのではなく、一部を法人に移すことで、トータルでの税負担を軽減できるのです。
所得税と法人税の税率構造の違い
以下の表は、個人の所得税率と中小企業の法人税率を比較したものです。
個人の所得が一定額を超えると、法人税率よりも高くなることがわかります。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 法人税率(中小法人) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 年800万円以下の部分:15% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | |
| 695万円超 800万円以下 | 23% | |
| 800万円超 900万円以下 | 23% | 年800万円超の部分:23.2% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | |
| 4,000万円超 | 45% |
例えば、個人事業で1,500万円の所得がある場合、高い所得税率が適用されます。
しかし、事業を法人と個人に分け、法人から役員報酬として800万円、個人事業で700万円の所得を得るように調整すれば、それぞれに低い税率が適用され、合計の税額を抑えることが可能になります。
さらに、法人から受け取る役員報酬には「給与所得控除」が適用されるため、この点でも節税につながります。
法人と個人で利益を最適なバランスで分配することが、手残りを最大化する鍵となります。
メリット2 消費税の免税事業者メリットの活用
消費税の納税義務に関しても、法人と個人事業を併用することでメリットを享受できる場合があります。
特に、消費税の免税事業者としての期間を最大限に活用できる点は大きな魅力です。
原則として、資本金1,000万円未満で新たに設立された法人は、設立から最大2年間、消費税の納税が免除されます。
法人成りによって、これまで課税事業者だった個人事業主も、新設法人としてこの免税メリットを受けられるのです。
さらに、法人成り後も個人事業を残し、その個人事業の課税売上高が1,000万円以下であれば、個人事業のほうも引き続き免税事業者でいられます。
つまり、法人と個人事業の両方で、一定期間または一定条件下で消費税の納税義務が免除される可能性があるのです。
これにより、消費税分の資金繰りが改善し、事業への再投資などに資金を回しやすくなります。
ただし、2023年10月から開始されたインボイス制度には注意が必要です。免税事業者のままだと、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引の継続に影響が出る可能性があります。
そのため、取引先の状況や事業内容を考慮し、あえて課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択する戦略も重要になります。
免税メリットと取引上のデメリットを天秤にかけ、慎重に判断しましょう。
メリット3 事業リスクの分散と柔軟な経営
法人と個人事業という2つの事業形態を持つことは、事業リスクを分散し、経営の選択肢を広げることにも繋がります。
これは、将来の不確実性に備えるための有効な経営戦略となり得ます。
事業ポートフォリオによるリスクヘッジ
性質の異なる複数の事業を手掛けている場合、それぞれを法人と個人に分けて運営することで、リスクを分散できます。
例えば、以下のような分け方が考えられます。
- 安定収益事業と新規事業:収益が安定している主要事業を法人で運営し、先行投資が必要な新規事業や、将来性の見極めが必要な事業を個人で展開する。万が一、新規事業が失敗しても、法人本体への直接的なダメージを抑えることができます。
- 許認可事業とその他事業:建設業や不動産業など、特定の許認可が必要な事業を法人格で運営し、許認可が不要なコンサルティングやWeb制作などを個人事業として残す。これにより、許認可の管理がしやすくなります。
将来の事業承継やM&Aへの備え
事業を法人と個人に分けておくことで、将来的な事業承継やM&A(事業売却)がスムーズに進めやすくなります。
例えば、法人化した事業のみを後継者に引き継いだり、売却したりすることが可能です。
個人事業として残した事業は、引き続き自身で運営を続ける、あるいは別の形で整理するなど、柔軟な対応ができます。
事業の出口戦略を複数持てることは、長期的な経営において大きな強みとなります。
また、金融機関からの融資においても、法人と個人でそれぞれ融資枠を確保できる可能性があるなど、資金調達の面でも選択肢が広がる場合があります。
法人成りで個人事業を残す3つのデメリット
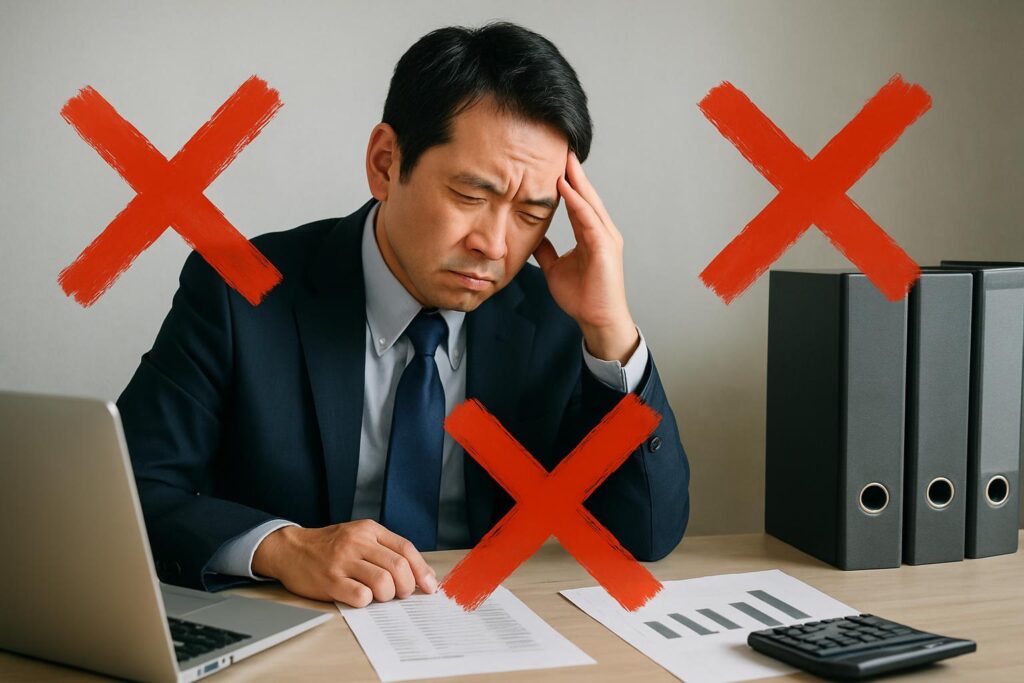
法人成り後も個人事業を残すという選択肢は、節税などのメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットも存在します。
メリットだけに目を向けて安易に決断すると、後々「こんなはずではなかった」と後悔する可能性も否定できません。
ここでは、事前に把握しておくべき3つの大きなデメリットを具体的に解説します。
デメリット1 経理処理が煩雑になる
最も実感しやすいデメリットが、経理・会計処理の複雑化です。
法人と個人事業主という2つの異なる事業体を同時に運営するため、管理の手間とコストが単純に2倍以上になる可能性があります。
具体的には、以下のような業務がそれぞれに発生します。
| 項目 | 法人 | 個人事業 |
|---|---|---|
| 会計帳簿 | 複式簿記による記帳が義務 | 青色申告であれば原則複式簿記 |
| 決算・申告 | 事業年度終了後2ヶ月以内に法人税等の申告 | 毎年2月16日~3月15日に所得税の確定申告 |
| 税金の種類 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など | 所得税、住民税、個人事業税、消費税など |
| 資金管理 | 法人口座での厳格な管理が必要 | 個人事業用口座での管理が望ましい |
このように、法人と個人の両方で会計帳簿を作成し、それぞれで決算と確定申告を行う必要があります。
また、プライベートの支出と事業の経費を分けるのはもちろんのこと、「法人の経費」と「個人事業の経費」も明確に区分しなければなりません。
事務所の家賃や光熱費、通信費などを両事業で共通して使用している場合は、事業内容や使用実態に応じた合理的な基準で按分する必要があり、この計算も煩雑です。
さらに、法人と個人の間で資金を安易に移動させることはできません。
法人の資金を個人事業のために使う場合は「役員貸付金」として処理するなど、適切な会計処理が求められます。
こうした複雑な経理処理を自分一人で行うのは非常に困難なため、税理士に依頼することになりますが、その分、税理士への報酬も高くなる傾向にあります。
デメリット2 社会保険料の負担が増える可能性がある
法人を設立し、その役員になると、事業規模や売上にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金と比較して、社会保険は保障が手厚い反面、保険料の負担が大きくなるケースが一般的です。
社会保険料は、役員報酬の金額(標準報酬月額)に基づいて計算され、会社と個人が半分ずつ負担します。
しかし、会社の負担分も元をたどれば会社の利益から支払われるため、実質的には全額を自分で負担しているのと同じと考えることができます。
例えば、役員報酬を月額30万円に設定した場合、東京都の令和6年度の保険料率で計算すると、健康保険料と厚生年金保険料の合計は月額約9万円となり、そのうち約4.5万円を会社が、約4.5万円を個人が負担することになります。
個人事業主時代に国民健康保険料の軽減措置を受けていた方や、売上がそれほど多くなかった方にとっては、この社会保険料の負担が経営を圧迫する要因になり得ます。
また、個人事業が残っていても、法人の役員として社会保険に加入するため、個人事業の方で国民健康保険に加入し続けることは原則としてできません。
デメリット3 税務調査で指摘されやすいポイントがある
法人と個人事業を併用するスキームは、意図的な利益調整や所得分散による租税回避行為を疑われやすく、税務調査において特に厳しくチェックされる傾向があります。
税務署から見て不自然な点や不明瞭な点があると、厳しい指摘を受け、最悪の場合、追徴課税や重加算税といった重いペナルティが課されるリスクがあります。
特に注意すべき、税務調査で指摘されやすいポイントは以下の通りです。
事業実態の有無
残した個人事業に、明確な事業実態があるかどうかは最も重要なポイントです。
単に法人の利益を個人に移すためだけの受け皿(ペーパー事業)と判断されると、個人事業の存在そのものが否認される可能性があります。
誰が、どこで、どのような事業活動を行っているのかを、契約書や請求書、業務の記録などで客観的に証明できる’mark>ようにしておく必要があります。
法人と個人間の取引価格の妥当性
法人が個人事業に対して業務を外注したり、個人が所有する不動産を法人が借りたりする場合、その取引価格が適正かどうかが問われます。
例えば、市場価格とかけ離れた高額なコンサルティング料を支払ったり、不当に安い賃料で事務所を貸したりすると、実質的な利益供与(寄附金)や所得移転とみなされ、法人側では経費(損金)として認められず、個人側では所得として課税される「寄附金認定課税」のリスクが生じます。
取引価格は、必ず第三者と取引する場合と同等の客観的な価格(時価)に設定しなければなりません。
経費区分の明確性
デメリット1でも触れましたが、経費の区分は税務調査における主要な論点です。
本来は法人が負担すべき経費を個人事業の経費として計上したり、その逆を行ったりすることは、所得の操作とみなされます。
特に、交際費や消耗品費、旅費交通費など、どちらの事業に関連するものか曖昧になりがちな経費は、領収書やレシートの裏に具体的な目的や相手先をメモするなど、どちらの事業活動に必要な経費であったかを明確に記録・管理することが不可欠です。
個人事業を残す場合の法人成りの具体的な手続き
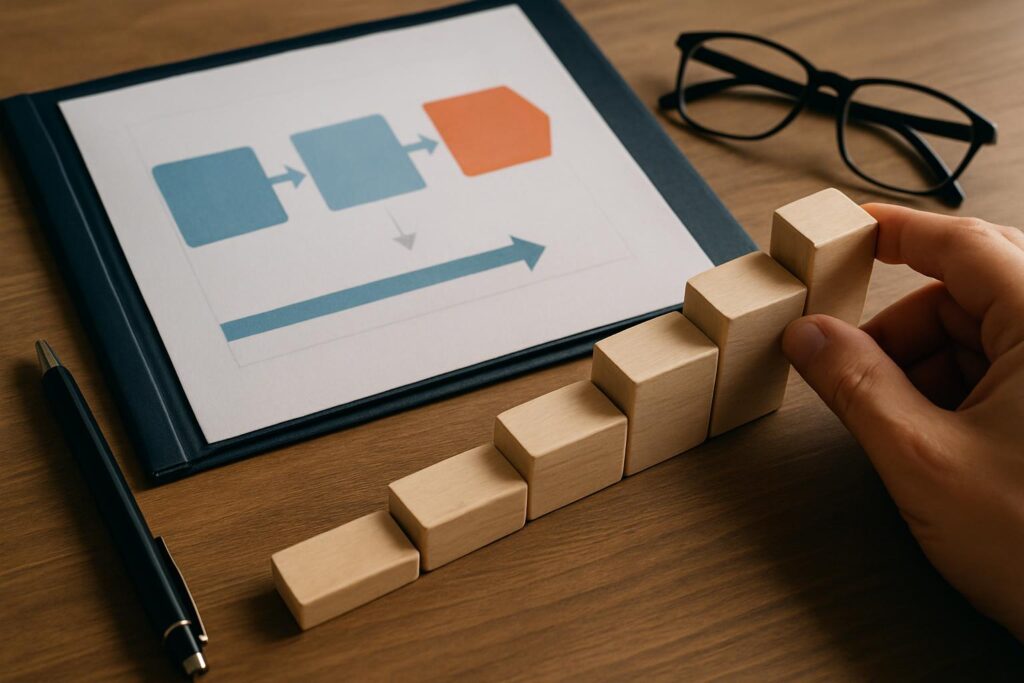
法人成り後も個人事業を残す場合、通常の法人成りとは異なる特有の手続きや注意点が存在します。
単に会社を設立するだけでなく、どの事業を法人に移し、どの資産を引き継ぐのかを明確に区分けするプロセスが不可欠です。
ここでは、その具体的な手続きを4つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1 会社設立の手続き(登記)
最初に行うのは、法人格を取得するための会社設立手続きです。
これは個人事業を残す場合でも、通常の法人成りと同様のプロセスを踏みます。
主な流れは以下の通りです。
まず、設立する会社形態を決定します。
一般的には、社会的信用度の高い「株式会社」か、設立コストが安く経営の自由度が高い「合同会社」のいずれかを選択することが多いです。
それぞれの特徴を比較検討し、ご自身の事業規模や将来の展望に合った形態を選びましょう。
会社形態を決めたら、以下の手順で設立手続きを進めます。
- 基本事項の決定:商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、役員構成などを決定します。
- 定款の作成・認証:会社のルールブックである定款を作成します。株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
- 資本金の払込み:発起人(設立者)個人の銀行口座に、定められた資本金を払い込みます。
- 登記申請書類の作成:登記申請書、就任承諾書、印鑑証明書など、法務局へ提出する必要書類を準備します。
- 登記申請:本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。この登記申請日が、会社の設立日となります。
登記が完了すれば、法人格が正式に誕生します。
その後、税務署や都道府県税事務所、市町村役場への法人設立届の提出、社会保険や労働保険の加入手続きなども忘れずに行いましょう。
ステップ2 法人化する事業の範囲を明確にする
個人事業を残す法人成りにおいて、最も重要なステップが「法人化する事業範囲の明確化」です。
なぜなら、法人と個人の事業区分が曖昧だと、税務調査で所得の意図的な操作(租税回避)を疑われるリスクが高まるからです。
税務署から指摘を受けないためには、誰が見ても納得できる客観的かつ合理的な基準で事業を区分けする必要があります。
以下に具体的な区分けの例を挙げます。
| 区分けの基準 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 事業内容で分ける | Web制作事業は法人、ライティング事業は個人事業として残す。 | 事業の種類が明確に異なる場合に有効です。関連性が低い事業同士だと、より説明しやすくなります。 |
| 取引先で分ける | 大手企業A社との取引は法人、中小企業B社や個人顧客との取引は個人事業で行う。 | 契約形態や取引規模などで明確な線引きができる場合に適しています。 |
| 地域で分ける | 東京エリアの店舗運営は法人、大阪エリアの店舗運営は個人事業として継続する。 | 物理的な拠点や管轄エリアが異なる場合に合理的な区分けと見なされやすいです。 |
ここで定めた法人の事業内容は、会社設立時に作成する定款の「事業目的」に具体的に記載します。
この事業範囲の定義が、後の経費按分や取引の正当性を主張する上での重要な根拠となります。
ステップ3 資産や契約の引き継ぎ(事業譲渡契約など)
法人化する事業範囲が決まったら、次はその事業に関連する資産、負債、契約などを個人から法人へ引き継ぐ手続きを行います。
引き継ぎ方法は主に以下の3つがあり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
事業譲渡
個人事業主が法人に対して事業を売却する方法で、最も一般的で明確な手続きです。
「事業譲渡契約書」を作成し、どの資産・負債をいくらで譲渡するのかを明記します。
これにより、財産の移転範囲が明確になり、後々の税務上のトラブルを防ぎやすくなります。
ただし、譲渡する資産の内容によっては、個人側に譲渡所得税、法人側に消費税や不動産取得税などが課税される可能性がある点に注意が必要です。
現物出資
事業用の資産(PC、車両、不動産など)を金銭の代わりに資本金として出資する方法です。
手元に現金がなくても会社を設立できるメリットがありますが、手続きが複雑になります。
特に、出資する財産の価額が500万円を超える場合は、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要となり、時間とコストがかかります。
賃貸借・売買
資産を法人へ移転せず、個人が所有したまま法人に貸し出す(賃貸借契約)か、個別に売却する(売買契約)方法です。
例えば、個人所有の事務所を法人に貸して賃料を受け取るケースがこれにあたります。
この場合、取引価格(賃料や売買価格)が相場から著しく逸脱していないかどうかが税務上の重要なポイントとなります。
どの方法を選択するかは、引き継ぐ資産の種類や価額、税務上の影響などを総合的に考慮して決定する必要があります。
専門家である税理士に相談しながら進めるのが賢明です。
ステップ4 各種許認可の再取得や変更手続き
特定の事業を行うために必要な許認可は、個人事業主として取得したものを法人が自動的に引き継ぐことはできません。
許認可は事業主(個人)に対して与えられているため、事業主体が法人に変わる場合は、原則として法人として新たに許認可を取得し直す必要があります。
この手続きを失念すると、許認可がないまま事業を運営している「無許可営業」の状態になり、営業停止や罰則の対象となる可能性があるため、絶対に軽視してはいけません。
以下に、再取得が必要となる主な許認可の例を挙げます。
| 許認可の種類 | 主な該当事業 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 建設業、工事業 | 個人で取得した許可は引き継げません。法人として新規申請が必要です。 |
| 宅地建物取引業免許 | 不動産業 | 個人免許は法人では使えません。法人として免許を再取得する必要があります。 |
| 飲食店営業許可 | 飲食店、カフェ | 保健所への申請者が個人から法人に変わるため、新規での取得が必要です。 |
| 古物商許可 | リサイクルショップ、中古品販売 | 管轄の警察署にて、法人名義での許可を新たに申請・取得します。 |
許認可の再取得には数ヶ月単位の時間がかかることも少なくありません。
法人設立後、事業がストップしてしまう事態を避けるためにも、会社設立の準備と並行して、管轄の行政庁に手続きや必要書類、所要期間などを事前に確認し、計画的に進めることが極めて重要です。
失敗しないために 法人成りで個人事業を残す際の5つの注意点

法人成り後も個人事業を残すという選択は、多くのメリットがある一方で、税務上のリスクを伴う複雑なスキームです。
安易な運用は、税務調査で思わぬ指摘を受け、追徴課税などのペナルティにつながる可能性があります。
ここでは、失敗を避け、メリットを最大限に享受するために必ず押さえておくべき5つの重要な注意点を詳しく解説します。
注意点1 法人と個人の取引価格の妥当性
法人と個人事業は、たとえ代表者が同一人物であっても法律上は別人格として扱われます。
そのため、両者間で行われる取引は「関連者間取引」とみなされ、税務署が特に厳しくチェックするポイントになります。
例えば、個人事業から法人へ商品を卸したり、法人が個人事業へ業務を委託したりする場合、その取引価格が市場価格(第三者と取引する場合の通常の価格)から著しく乖離していると、意図的に利益をどちらかに移すための「利益操作」と判断される恐れがあります。
このような取引は、法人税法上の「同族会社の行為計算の否認」という規定に抵触する可能性があります。
税務調査で取引価格が不相当であると指摘された場合、適正な市場価格で取引が行われたものとして所得が再計算され、不足分の税金に加えて加算税や延滞税といった重いペナルティが課されることになります。
こうしたリスクを避けるためには、以下の対策が不可欠です。
- 取引価格を客観的な時価(市場価格)に設定する
- なぜその価格設定なのかを証明できる根拠資料(相見積書、市場価格の調査データ、価格算定書など)を準備・保管する
- 取引内容を明確にした業務委託契約書や売買契約書を必ず作成する
常に「第三者と同じ条件で取引しているか」という視点を持ち、取引の妥当性を客観的に証明できるようにしておくことが極めて重要です。
注意点2 経費の明確な区分
法人と個人事業で、事務所や店舗、車両、設備などを共有する場合、家賃や水道光熱費、通信費といった経費を両者で分ける「経費按分」が必要になります。
この按分ルールが曖昧だと、税務調査で大きな問題となります。
税務署が懸念するのは、本来は個人事業が負担すべき経費を、利益が出ている法人の経費として計上する「経費の付け替え」です。
これは不当に法人の利益を圧縮し、法人税を逃れる行為と見なされます。
経費の按分を行う際は、誰が見ても納得できる合理的かつ客観的な基準を設定し、その基準に基づいて計算する必要があります。
恣意的な判断で割合を決めることは絶対に避けなければなりません。
以下に、経費ごとの合理的な按分基準の例を挙げます。
| 経費項目 | 合理的な按分基準の例 | 根拠資料の例 |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 事業ごとの使用面積の割合 | 事務所の図面、賃貸借契約書 |
| 水道光熱費 | 使用時間、コンセントの数、従業員数の割合 | 業務日報、設備の仕様書 |
| 通信費 | 使用頻度、回線数、従業員数の割合 | 通話記録、利用明細 |
| 車両関連費 | 走行距離、使用日数の割合 | 運転日報、走行記録 |
設定した按分基準とその計算根拠となる資料は、いつでも提示できるように整理・保管しておくことが、税務調査への最良の備えとなります。
注意点3 役員報酬の適切な設定
法人から自分自身へ支払う「役員報酬」は、法人にとっては損金(経費)となり、法人税の節税に繋がります。
しかし、受け取った個人にとっては給与所得となり、所得税・住民税、そして社会保険料の課税対象となります。
法人と個人事業を併用する場合、「役員報酬」と「個人事業の所得」の合計額に対して個人の税金や社会保険料が計算されるため、両者のバランスを慎重に検討しなければなりません。
役員報酬を高く設定すれば法人税は下がりますが、個人の税・社会保険料負担が急増する可能性があります。
逆に低く設定しすぎると、法人の利益が残りすぎて高い法人税が課せられます。
また、役員報酬は「定期同額給与」の原則により、事業年度の途中で自由に金額を変更できないという制約もあります。
したがって、法人成りを行う際には、所得税の超過累進税率と法人税率、社会保険料負担を総合的に比較し、法人と個人のトータル手残りが最も多くなる最適な役員報酬額をシミュレーションすることが不可欠です。
このシミュレーションには専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家と相談しながら決定することをお勧めします。
注意点4 利益相反取引への注意
「利益相反取引」とは、会社の取締役が、その立場を利用して自己または第三者の利益を図り、結果として会社の利益を害する恐れのある取引を指します。
法人と個人事業を同一人物が運営する場合、この利益相反取引に該当するケースが頻繁に発生します。
例えば、以下のような取引が典型例です。
- 取締役(個人事業主)が所有する不動産を、自身の法人に賃貸する
- 取締役(個人事業主)が自身の法人からお金を借りる
- 取締役(個人事業主)の借金に対して、自身の法人が連帯保証人になる
これらの取引を行うこと自体が禁止されているわけではありませんが、会社法では、利益相反取引を行う際には、事前に株主総会(または取締役会設置会社の場合は取締役会)でその取引に関する重要な事実を開示し、承認を得なければならないと定められています。
この承認手続きを怠った場合、その取引が無効と判断されたり、会社に損害が生じた際には取締役が損害賠償責任を問われたりする可能性があります。
税務上の問題だけでなく、法務上のリスクも潜んでいることを認識し、該当する取引を行う際は必ず適切な手続きを踏み、その証拠として株主総会議事録や取締役会議事録を作成・保管しておきましょう。
注意点5 税理士への早期相談
これまで解説してきた通り、法人成り後も個人事業を残すスキームは、税務・法務の両面で専門的な知識が要求され、判断を誤ると大きなリスクを伴います。
取引価格の妥当性、経費の按分基準、最適な役員報酬額など、自己判断で進めるのは非常に危険です。
そこでお勧めするのが、税理士への早期相談です。
法人成りや事業承継に詳しい税理士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 客観的な視点でのリスク分析と対策:税務調査で指摘されやすいポイントを熟知しており、事前に適切な対策を講じることができます。
- 最適な節税スキームの構築:個々の事業内容や収益状況に合わせて、法人と個人の所得バランスや役員報酬額など、トータルで最も有利な形をシミュレーションし、提案してくれます。
- 煩雑な手続きのサポート:会社設立手続きから、事業譲渡契約書の作成、税務署への各種届出、その後の経理処理や確定申告まで、複雑な手続きを安心して任せることができます。
重要なのは、相談するタイミングです。「法人成りをしようかな」と考え始めた段階で相談することが最も効果的です。
すでに法人を設立してしまった後では、修正が困難なケースも少なくありません。
将来の事業展開を見据え、安心して事業に集中するためにも、信頼できる専門家をパートナーとして見つけることが成功への近道と言えるでしょう。
まとめ
法人成り後も個人事業を残すことは可能です。
この手法は、所得分散による節税や消費税の免税事業者メリットの活用など多くの利点がある一方、経理処理の煩雑化や税務調査で指摘されやすいといったデメリットも伴います。
成功の鍵は、法人と個人の事業範囲や経費を明確に区分し、取引価格の妥当性を保つなど、税務上のリスクを適切に管理することです。
失敗を避けるためにも、計画段階から税理士などの専門家に相談し、慎重に手続きを進めましょう。