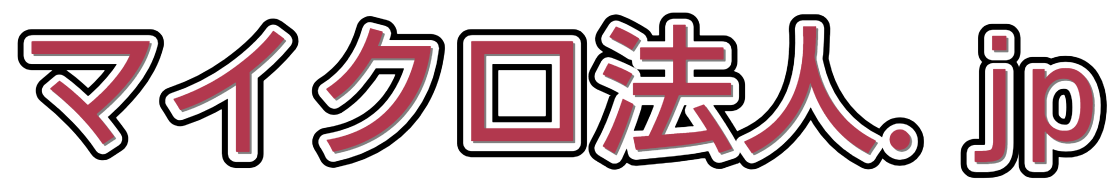本記事では、フリーランスが加入すべき社会保険制度の仕組みから加入要件や手続き、メリット・デメリット、保険料計算と節税法までを網羅解説します。
国民健康保険や国民年金、任意継続被保険者制度、中小企業退職金共済・小規模企業共済といった選択肢ごとの特徴も具体的に示し、加入のコツと最適なプランがわかります。
未経験の方もこれ一つで全体像が把握でき、安心して保険選びができます。
フリーランスと会社員の社会保険の違い
フリーランスと会社員では、社会保険の加入方法や保険料負担、給付内容などに大きな違いがあります。
本章では、社会保険の仕組みを解説し、両者の相違点を明確にします。
社会保険の基本的な仕組み
社会保険とは、労働者やその家族の生活を保障するための制度で、以下の5つが中心となります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
これらはリスクの共有を目的に、加入者が保険料を出し合い、病気や老後などの生活リスクに備えます。
会社員の場合は給与から自動的に保険料が天引きされ、事業主が一部を負担しますが、フリーランスは自ら全額を負担し、市区町村や年金事務所で手続きを行います。
会社員が加入する社会保険の種類
会社員は勤務先を通じて、以下の社会保険に自動加入します。
| 保険の種類 | 概要 | 保険料の負担割合 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 医療費の自己負担軽減や出産手当金など | 事業主50%/被保険者50% |
| 厚生年金保険 | 老後の年金給付や障害年金など | 事業主50%/被保険者50% |
| 介護保険(一号被保険者除く) | 40歳以上が対象、要介護状態への備え | 事業主50%/被保険者50% |
| 雇用保険 | 失業給付や育児休業給付など | 事業主75%/被保険者25% |
| 労災保険 | 業務災害や通勤災害への補償 | 事業主100% |
加入手続きは会社が行い、従業員は手続き不要です。
フリーランスに関係する社会保険の種類
フリーランスは会社員と異なり、勤務先がないため、原則として以下の社会保険に個別に加入します。
| 保険の種類 | 加入先 | 概要 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村 | 医療費の自己負担軽減、傷病手当金は原則なし |
| 国民年金 | 日本年金機構 | 基礎年金として給付、保険料は定額 |
| 介護保険(一号被保険者) | 市区町村 | 40歳以上の加入、要介護状態への備え |
| 任意継続被保険者制度 | 健康保険組合または協会けんぽ | 退職後2年間、会社員時の健康保険を継続可能 |
フリーランスは手続きを自ら行う必要があるため、加入漏れや手続き遅延に注意が必要です。
フリーランスが加入できる社会保険の種類

国民健康保険とは
国民健康保険は、会社員などが加入する健康保険から脱退した場合や、初めて医療保険に加入するフリーランス向けの公的保険制度です。
病院での診療や薬剤費の自己負担額が原則として3割となり、扶養家族も同一世帯であれば加入可能です。
保険料は所得額や世帯構成をもとに市区町村ごとに算出されますが、所得が低い場合は〈高額療養費制度〉や〈減免制度〉を活用し、医療費の自己負担軽減を図ることができます。
国民年金制度について
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎年金制度で、フリーランスは第1号被保険者として毎月定額の保険料を納付します。
老後に受給する〈老齢基礎年金〉をはじめ、障害年金や遺族年金の対象にもなります。
保険料は年度ごとに定められ、納付期間が25年以上あれば満額受給資格を得られます。
基礎年金を受給するためには、免除・猶予制度を併用しつつ納付期間を確保することが重要です。
任意継続被保険者制度について
任意継続被保険者制度は、退職前に会社員として健康保険に加入していた人が、退職後20日以内に申し込むことで最長2年間まで継続加入できる制度です。
保険料は退職時の標準報酬月額をもとに計算され、会社負担分がなくなるため全額自己負担となりますが、最長2年間にわたり同等の保障が維持できます。
扶養家族の社会保険活用法
フリーランス自身が加入するだけでなく、配偶者や子どもを被扶養者として加入させることで世帯全体の保険料負担を軽減できます。
たとえば、配偶者の年間所得が一定以下(多くの自治体で年間130万円未満)であれば、国民健康保険や国民年金の第3号被保険者として登録が可能です。
扶養家族の要件や手続きは市区町村窓口で確認し、早めに届け出ることをおすすめします。
中小企業退職金共済や小規模企業共済の活用
フリーランスや個人事業主が将来の資金を準備しつつ節税できる仕組みとして、以下の制度があります。
| 制度名 | 対象者 | 掛金(月額) | 税制優遇 | 受取方法 |
|---|---|---|---|---|
| 中小企業退職金共済(中退共) | 個人事業主・中小企業 | 5,000円~30,000円 | 全額損金算入 | 退職金・一時金 |
| 小規模企業共済 | 常時従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下) | 1,000円~70,000円 | 掛金は全額所得控除 | 共済金・年金 |
フリーランスの社会保険 加入義務と例外

社会保険の加入義務
フリーランスとして個人事業を営む場合、法律により国民健康保険への加入と国民年金への加入が義務付けられています。
事業開始後14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行い、保険証の発行を受ける必要があります。
国民健康保険料は前年の所得によって算出され、国民年金保険料は定額制です。
いずれも未加入や滞納は法的制裁の対象となるため、開業時点で必ず加入手続きを完了させましょう。
法人化した場合の社会保険加入
フリーランスが合同会社や株式会社を設立すると、代表者であっても健康保険(協会けんぽまたは組合健保)と厚生年金保険への加入が義務となります。
役員や従業員を雇用する場合は、すべて加入対象です。
| 事業形態 | 加入保険 | 加入対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 国民健康保険 国民年金 | 事業主本人 | 市区町村窓口で手続き |
| 合同会社・株式会社 | 健康保険(協会けんぽ等) 厚生年金 | 役員・従業員全員 | 被保険者報酬に応じて算定 |
法人化により保険料は給与額に連動しますが、半額を法人が負担するため、個人負担額を抑えながら保障を手厚くできます。
副業・兼業フリーランスの場合
本業で会社員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合、副業で得た報酬は追加の社会保険加入義務を生じさせません。
しかし条件によっては所得の合計額が一定基準を超えた際に扶養扱いが外れるケースがあります。
以下の条件を満たす場合、扶養から除外される可能性があるため注意が必要です。
- 副業の収入が年間130万円を超える
- 勤務時間が週20時間以上である
- 副業先で労使折半の社会保険に加入要件を満たす
扶養から外れた場合、副業先での健康保険・厚生年金加入が必要になるほか、国民年金第3号被保険者資格を失い、自身で国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
フリーランスが社会保険に加入するための手続き

国民健康保険の手続き方法と必要書類
退職や廃業などで会社の健康保険を離れた場合、市区町村役場で国民健康保険(以下、国保)の加入手続きを行います。
退職日の翌日から14日以内に手続きを済ませることで、保険の空白期間を防止できます。
| 書類名 | 用意するもの | 備考 |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど | 住所変更がある場合は現住所が確認できるもの |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 原本 | 国保料計算用に必要 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 退職先から発行された書類 | 健康保険被保険者証でも可 |
| 印鑑 | 認印 | 役場届出用 |
加入後は毎年度の所得に応じて保険料が決定し、原則として年4回に分けて納付します。
国民年金の加入手続きと注意点
20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金は、市区町村役場で手続きをします。
会社員からフリーランスに移行した場合、厚生年金喪失後に14日以内の手続きが推奨されます。
| 書類名 | 用意するもの | 備考 |
|---|---|---|
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 原本 | 未交付の場合は申請書を併用 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など | 国保と合わせて手続き可能 |
| 印鑑 | 認印 | 提出書類への押印用 |
注意点として、未納期間があると将来の年金受給額が減少します。
学生納付特例制度や免除制度も利用できるため、市区町村役場で相談してください。
任意継続被保険者の申請方法
退職前に加入していた健康保険を最長2年間延長できる任意継続制度は、退職日の翌日から20日以内に前勤務先の健康保険組合または協会けんぽへ申請します。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 任意継続被保険者資格取得申請書 | 健康保険組合または協会けんぽの所定様式 | 健康保険組合/協会けんぽ支部 |
| 健康保険被保険者証 | 退職前の被保険者証 | 同上 |
| 退職日の証明 | 離職票または退職証明書 | 同上 |
| 振込先口座情報 | 預金通帳の写しなど | 保険料口座振替用 |
保険料は本人と事業主折半分を全額自己負担しますが、毎月または2ヶ月分まとめて納付できます。
加入期間中は医療機関窓口で自己負担割合(原則3割)が適用されます。
手続きのタイミングと失業保険との関係
フリーランスに転身する際、前職で雇用保険に加入していた場合は「求職者給付」(失業保険)の受給手続きも並行して行えます。
ハローワークで離職票を提出し、求職申請を済ませたうえで国保・年金の手続きを行うとスムーズです。
- 退職日から14日以内:国保・国年の手続き
- 退職日の翌日から20日以内:任意継続申請
- 離職票受領後速やかにハローワークへ求職申請
失業保険受給中は求職活動実績の報告が必要ですが、フリーランス準備の状況も認められる場合があります。
具体的な要件や日程は最寄りのハローワークで確認してください。
フリーランスが社会保険に加入するメリットとデメリット

メリットについて
医療費補助と年金受給
フリーランスが国民健康保険に加入すると、病院窓口での自己負担が原則3割となり、万が一の高額医療費にも対応できます。
さらに、一定以上の医療費が発生した場合、高額療養費制度により自己負担額がさらに軽減されます。
国民年金に加入することで、老齢基礎年金を受給できるほか、月額400円を上乗せして将来の年金額を増やす付加年金制度も利用可能です。
疾病や障害時の保障
国民健康保険では傷病手当金が無い一方、国民年金の障害基礎年金(障害等級1級・2級)が受給でき、要件を満たせば生計維持者に対する額も支給されます。
また、病気やケガで長期入院した場合の生活資金を確保しやすくなります。
小規模企業共済などの税制優遇
フリーランス向け共済制度として小規模企業共済や中小企業退職金共済があり、掛金全額が所得控除の対象となります。
これにより課税所得を圧縮しながら、将来の退職金代わりの資産形成が可能です。
デメリットについて
保険料の金額と負担
国民健康保険料は前年の所得に応じて算出され、自治体によっては高額になる場合があります。
また、国民年金保険料(令和○年度は月額16,610円)は定額のため、収入が安定しない時期も同額を支払わなければなりません。
会社員との保障内容の差
会社員が受けられる傷病手当金や出産手当金、雇用保険の失業給付などの一部給付が利用できません。
また、労災保険の適用範囲が限定的になり、業務上災害の保障を別途加入で補う必要があります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・医療費補助や年金受給による生活安定 ・疾病・障害時の保障 ・中小企業共済・小規模企業共済で節税 | ・保険料自己負担の増加 ・傷病手当金や出産手当金の不在 ・加入手続き・保険料算定の煩雑さ |
社会保険料の計算方法と節税対策

国民健康保険料の算出方法
国民健康保険料は、所得割・均等割・平等割などを基に算出されます。
これらの合計額により、年度ごとの保険料が決まります。
住民票のある市区町村ごとに料率が異なるため、具体的な金額は自治体の公式サイトで確認が必要です。
所得割・均等割・平等割の内訳
| 項目 | 算出式 | 概要 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の課税所得額 × 料率(%) | 前年所得に応じた変動分 |
| 均等割 | 定額 × 世帯人数 | 世帯の人数に応じた固定分 |
| 平等割 | 定額 | 世帯ごとの固定分 |
例として、課税所得300万円、料率8%の自治体に5人世帯で住む場合の試算は以下の通りです。
| 内訳 | 試算額 |
|---|---|
| 所得割 | 300万円 × 8% = 24万円 |
| 均等割 (5人 × 4万円) | 20万円 |
| 平等割 | 3万円 |
| 合計 | 47万円 |
国民年金保険料の金額
国民年金は、全額定額の保険料を毎月納付します。令和6年度の月額保険料は16,590円です。
年度の途中で納付額が改定される場合がありますので、最新情報は日本年金機構のサイトでご確認ください。
所得が一定基準以下の場合は、保険料免除や納付猶予の申請が可能です。
申請により全額免除・一部免除を受けられることがあり、将来の年金受給額に影響します。
節税につながる共済や控除の活用
フリーランスが利用できる主な節税制度には、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。
いずれも掛金が全額所得控除の対象となり、課税所得を減らす効果が期待できます。
| 制度 | 概要 | 控除対象 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 経営者やフリーランスが退職時の資金を積み立てる制度 | 掛金全額 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 個人が自主的に年金を積み立てる制度 | 掛金全額 |
| 国民年金保険料控除 | 国民年金の支払い額に応じて所得控除 | 支払額全額 |
これらの制度を組み合わせることで、実質的な税負担を軽減できます。
ただし掛金の上限や条件が異なるため、加入前に制度の概要を十分に確認しましょう。
フリーランス向けの社会保険に関するよくある質問

支払いが難しい場合の対処法
フリーランスは収入の増減が大きいため、社会保険料の支払いに窮することがあります。
以下の制度を活用して、支払い計画の見直しを行いましょう。
| 制度名 | 対象保険 | 主な内容 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 分割納付制度 | 国民年金・国民健康保険 | 保険料を数回に分けて納付できる | 市区町村役場・年金事務所 |
| 納付猶予・免除制度 | 国民年金 | 所得状況に応じて全額または一部を猶予・免除 | 年金事務所 |
| 保険料減免 | 国民健康保険 | 災害・事業不振などで減免を申請 | 市区町村役場 |
各制度には申請期限や証明書類が必要です。早めの相談を心がけましょう。
家族の扶養に入れる条件
扶養家族を活用すると、世帯全体の保険料負担を軽減できます。
制度ごとの要件を以下にまとめました。
| 制度 | 加入対象 | 要件 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 配偶者・子ども | 同一世帯で前年所得が130万円未満 |
| 国民年金(第3号被保険者) | 配偶者 | 第1号または第2号被保険者の被扶養者であること |
扶養に入れる条件は制度ごとに異なります。事前の確認を怠らないようにしましょう。
将来の年金の受給額について
年金受給額は加入期間や保険料納付実績に応じて決まります。
以下のポイントでシミュレーションし、将来の受給見込額を把握しましょう。
- ねんきん定期便で加入記録を確認
- 年金ネットで受給額を試算
- 任意加入期間を延長した場合の増額効果
- 繰り上げ受給・繰り下げ受給のメリットと注意点
ライフプランに合わせて、受給開始時期を検討しましょう。
まとめ
フリーランスは国民健康保険と国民年金が原則ですが、任意継続被保険者制度や小規模企業共済を活用することで、保障と税制優遇を得られます。
加入義務や手続きを期限内に行い、保険料負担や保障内容の差を理解することが安定した生活設計には不可欠です。
保険料算出方法を理解し、法人化や扶養家族の利用、節税共済を組み合わせることで、支出を抑えつつ将来の年金受給額を安定させましょう。