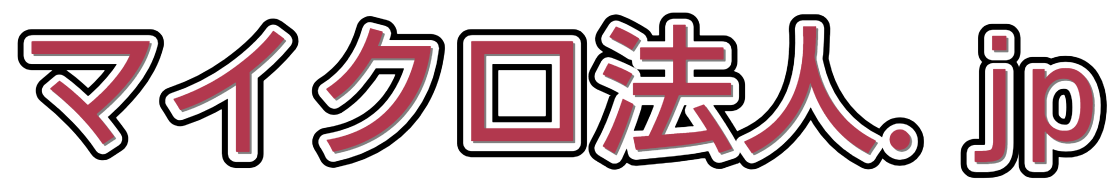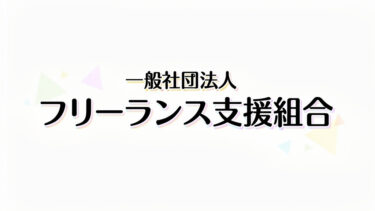マイクロ法人を設立して社会保険料を最適化したいけれど、何から始めればいいか分からない方へ。
本記事は、マイクロ法人設立の全手順を9ステップで解説する完全ガイドです。
株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか、費用や必要書類、最短スケジュールまで網羅的に解説。
結論として、一人社長なら合同会社がおすすめです。
この記事を読めば、設立から運営までの全体像を掴み、迷わず手続きを進められます。
マイクロ法人とは?設立前に知っておきたい基礎知識
「マイクロ法人」という言葉を耳にする機会が増えましたが、実はこの言葉に法律上の明確な定義はありません。
一般的には、社長一人、もしくは配偶者や親族などごく少人数で運営される、従業員のいない小規模な会社を指す言葉として使われています。
プライベートカンパニーと呼ばれることもあります。
近年、多くの個人事業主やフリーランスがマイクロ法人に注目している背景には、主に「社会保険料の最適化」と「節税」という大きなメリットがあります。
しかし、法人化にはメリットだけでなく、コストや手間といったデメリットも存在します。
まずはマイクロ法人の基礎知識を正しく理解し、ご自身にとって本当に設立すべきかを見極めることが重要です。
この章では、その判断に必要な知識を詳しく解説していきます。
マイクロ法人の定義と設立するメリット・デメリット
マイクロ法人を設立するかどうかを判断する上で、最も重要なのがメリットとデメリットの比較検討です。
特に金銭的なメリットは大きいですが、その分、新たな負担も生じます。両方を天秤にかけ、総合的に判断しましょう。
メリット 社会保険料の最適化と節税効果
マイクロ法人を設立する最大のメリットは、社会保険料と税金の負担を軽減できる可能性が高い点にあります。
社会保険料の最適化
個人事業主が加入する「国民健康保険」は所得に応じて保険料が上がりますが、法人が加入する「健康保険・厚生年金(協会けんぽなど)」は、役員報酬の金額(標準報酬月額)を基準に保険料が決定されます。
この仕組みを利用し、マイクロ法人からの役員報酬を低額(例:月額45,000円など)に設定することで、社会保険料を大幅に抑えることが可能です。
個人事業主としての事業は継続し、そちらで主な収入を得る「二刀流」という手法を取ることで、全体の所得を維持しながら社会保険料負担だけを最小限にできるのが大きな魅力です。
多様な節税効果
法人化することで、個人事業主よりも幅広い節税策を活用できます。
- 所得の分散:個人事業の所得と法人の役員報酬に所得を分けることで、所得税の超過累進税率を緩和できます。
- 給与所得控除の適用:役員報酬は給与所得となるため、経費とは別に給与所得控除が適用され、課税所得を圧縮できます。
- 経費計上範囲の拡大:自宅を社宅扱いにして家賃の一部を経費にしたり、出張手当(日当)を非課税で支給したりと、個人事業主では認められない経費計上が可能になります。
- 生命保険料の経費化:法人契約の生命保険であれば、保険の種類によって支払保険料の全部または一部を損金として算入できます。
- 欠損金の繰越期間:事業で生じた赤字(欠損金)を翌年以降の黒字と相殺できる期間が、個人事業主の3年間に対し、法人は10年間と長くなります。
デメリット 設立・維持コストと事務負担の増加
メリットがある一方で、法人を設立・維持していくためには相応のコストと手間がかかります。
設立・維持コストの発生
まず、法人を設立する際には、定款認証手数料や登録免許税などの法定費用がかかります。
これは最も安い合同会社でも約6万円〜、株式会社であれば約20万円〜が必要です。
さらに、設立後も利益が出ていなくても毎年支払わなければならない「法人住民税の均等割」が最低でも年間約7万円かかります。
その他、税理士に決算を依頼する場合は別途報酬も必要となり、これらの維持コストを上回るメリットがなければ、かえって損をしてしまう可能性があります。
事務負担の増加
個人事業主の確定申告に比べ、法人の経理・税務申告は格段に複雑になります。
会計処理は複式簿記が必須となり、日々の記帳に加え、年末調整や源泉徴収、社会保険の手続きなど、行うべき事務作業が大幅に増えます。
法人の決算申告は専門知識が必要なため、多くの場合は税理士などの専門家に依頼することになり、そのコストも考慮しなければなりません。
個人事業主やフリーランスとの違いを比較
マイクロ法人と個人事業主(フリーランス)には、税金、社会保険、社会的信用度など様々な面で違いがあります。
どちらの形態が自分に適しているか、以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主(フリーランス) |
|---|---|---|
| 設立手続き | 定款作成・法人登記などが必要で、時間と費用がかかる | 税務署に開業届を提出するだけで、費用はかからない |
| 税金 | 法人税、法人住民税、法人事業税など | 所得税、住民税、個人事業税など |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金(役員報酬に基づき算定) | 国民健康保険・国民年金(所得に基づき算定) |
| 経費の範囲 | 役員社宅、出張手当、生命保険料など範囲が広い | 事業に関連するものに限定され、範囲が狭い |
| 社会的信用度 | 法人格があるため高く、融資や取引で有利な傾向 | 法人に比べて低いと見なされる場合がある |
| 責任の範囲 | 有限責任(出資額の範囲内で責任を負う) | 無限責任(事業上の負債すべてに個人資産で責任を負う) |
| 事務負担 | 決算申告、社会保険手続きなど複雑で負担が大きい | 確定申告のみで、法人に比べると負担は少ない |
マイクロ法人設立がおすすめな人・おすすめでない人
これまでのメリット・デメリット、個人事業主との違いを踏まえ、マイクロ法人の設立が向いている人とそうでない人の特徴をまとめました。
【おすすめな人】
- 個人事業主としての課税所得が800万円を超え、所得税や社会保険料の負担を重く感じている人
- 事業収入が安定しており、今後も継続して利益が見込める人
- 個人事業と法人事業を明確に分け、両方のメリットを享受したい「二刀流」を目指す人
- 社会的信用度を高めて、金融機関からの融資や大手企業との取引を有利に進めたい人
- 法人設立・維持のコストや事務手続きの手間を許容できる、または専門家に依頼する資金的余裕がある人
【おすすめでない人】
- 事業の所得がまだ少ない、または不安定な人(法人維持コストが経営を圧迫する可能性があります)
- 経理や事務作業が極端に苦手で、専門家に依頼する費用も避けたい人
- とりあえず法人化したい、といった明確な目的や事業計画がない人
- 副業収入が年間20万円程度など、そもそも節税メリットが小さい会社員
マイクロ法人設立は、あくまで個人の資産形成や事業運営を最適化するための「手段」です。
ご自身の事業規模や所得、将来の展望などを総合的に考慮し、慎重に設立を検討しましょう。
マイクロ法人の会社形態は株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか
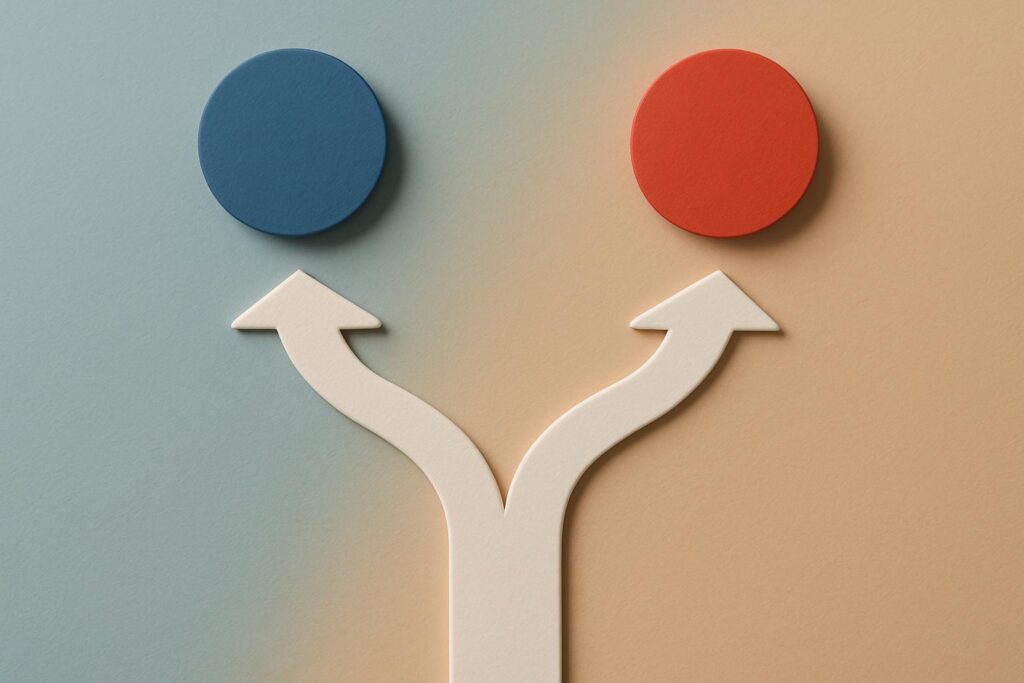
マイクロ法人を設立する際、最初に決めなければならない重要な選択肢が「会社形態」です。
主な選択肢として「株式会社」と「合同会社」の2つがありますが、それぞれに特徴があり、設立費用や運営方法も異なります。
ご自身の事業計画や将来のビジョンに合わせて、最適な形態を選ぶことが成功への第一歩となります。
この章では、株式会社と合同会社それぞれの特徴、メリット・デメリット、設立費用を詳しく比較し、特に一人社長のマイクロ法人にとってどちらが適しているのかを徹底的に解説します。
株式会社で設立する場合の特徴と費用
株式会社は、日本で最も認知度が高く、社会的な信用力に優れた会社形態です。
株式を発行して資金を調達し、株主から委任された経営者(取締役)が事業運営を行います。
一人社長の場合は、自身が株主であり取締役となります。
株式会社の主な特徴は以下の通りです。
- 社会的信用度が高い: 知名度が高く、金融機関からの融資や大手企業との取引、優秀な人材の採用において有利に働く傾向があります。将来的に事業を拡大し、外部との取引を重視する場合には大きなメリットとなります。
- 資金調達の方法が豊富: 株式を発行することで、投資家やベンチャーキャピタルから出資を募ることができます。将来的に大きな資金調達を視野に入れている場合は、株式会社が必須の選択肢です。
- 上場(IPO)を目指せる: 証券取引所への上場が可能なのは株式会社だけです。事業の最終目標として上場を考えているなら、株式会社一択となります。
- 役員に任期がある: 取締役の任期は原則2年(非公開会社の場合は定款で最長10年まで伸長可能)です。任期が満了するたびに役員変更の登記手続きが必要となり、その際に登録免許税(1万円または3万円)がかかります。
- 決算公告の義務がある: 毎年、官報や日刊新聞紙、または自社のウェブサイトで決算内容を公告する義務があります。これには数万円の費用と手間がかかります。
設立費用は合同会社に比べて高額になる点がデメリットです。
具体的には、定款認証手数料や登録免許税の最低額が高く設定されています。
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 設立登記の際に法務局へ納付する税金です。 |
| 定款認証手数料 | 3万円~5万円 | 公証役場で定款の認証を受けるための手数料です。資本金の額によって変動します。 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 認証された定款の写しを発行してもらうための費用です。 |
| 定款印紙代 | 4万円 | 紙の定款で作成する場合に必要です。電子定款にすれば0円になります。 |
| 合計 | 約22.2万円~ | 電子定款を利用しない場合は約26.2万円~となります。 |
合同会社で設立する場合の特徴と費用
合同会社は、2006年の会社法施行によって導入された比較的新しい会社形態です。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとしており、設立費用の安さと運営の自由度の高さが最大の特徴です。
合同会社の主な特徴は以下の通りです。
- 設立費用が安い: 株式会社と比べて、定款認証が不要で、登録免許税も最低6万円からと大幅に安く抑えられます。スモールスタートしたいマイクロ法人にとって最大のメリットと言えるでしょう。
- 運営の自由度が高い: 会社のルールを定款で柔軟に定めることができます。例えば、利益の配分を出資額の比率によらず、業務への貢献度などに応じて自由に決めることが可能です。
- 迅速な意思決定: 所有と経営が一体化しており、重要な事項の決定も社員(株式会社でいう株主に相当)の同意だけで行えるため、スピーディーな経営判断が可能です。
- 役員の任期がない: 株式会社のような役員の任期がないため、役員が変わらない限り、定期的な変更登記の手間と費用がかかりません。
- 決算公告の義務がない: 毎年の決算公告が不要なため、運営コストと事務負担を軽減できます。
デメリットとしては、株式会社に比べて一般的な知名度が低く、社会的信用度がやや劣ると見なされる場合がある点です。
ただし、近年はApple JapanやGoogle、Amazon Japanなど多くの有名企業が合同会社の形態をとっており、その認知度は向上しています。
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低6万円) | 株式会社より最低額が9万円安くなっています。 |
| 定款認証手数料 | 0円 | 合同会社は定款の認証が不要です。 |
| 定款の謄本手数料 | 0円 | 定款認証が不要なため、この費用もかかりません。 |
| 定款印紙代 | 4万円 | 紙の定款で作成する場合に必要です。電子定款にすれば0円になります。 |
| 合計 | 6万円~ | 電子定款を利用しない場合は10万円~となります。 |
一人社長のマイクロ法人設立におすすめなのは合同会社
ここまで株式会社と合同会社の特徴を比較してきましたが、結論として、社会保険料の最適化や節税を主目的とする一人社長のマイクロ法人には、合同会社での設立を強くおすすめします。
その理由は以下の3点です。
- 圧倒的なコストメリット: マイクロ法人は、大きな利益を追求するよりもコストを最小限に抑えることが重要です。設立費用が株式会社の3分の1以下で済む合同会社は、初期投資を大幅に削減できます。また、役員変更登記や決算公告が不要なため、設立後のランニングコストも低く抑えられます。
- 運営のシンプルさと手間削減: 一人社長の場合、経営に関する意思決定はすべて自分で行います。株主総会の開催義務がなく、運営ルールを定款で自由に決められる合同会社は、事務的な手続きが少なく、本業に集中しやすい環境を作れます。
- 信用力の影響が少ない: マイクロ法人の主な取引相手は、個人事業主としての自分自身や、限られたクライアントであることがほとんどです。そのため、株式会社のような高い社会的信用度が求められる場面は少なく、合同会社でも事業運営に支障が出るケースは稀です。
もちろん、将来的に外部から多額の資金調達を目指す、上場を視野に入れている、あるいは許認可の要件で株式会社であることが必須といった明確な理由がある場合は、最初から株式会社を選択すべきです。
しかし、そうした特別な事情がなければ、まずは合同会社でスモールスタートするのが最も合理的です。
事業が順調に拡大し、将来的に株式会社の信用力や機能が必要になった際には、合同会社から株式会社へ組織変更することも可能です。
この「後から変更できる」という選択肢があることも、最初に合同会社を選ぶハードルを下げてくれるでしょう。
マイクロ法人の設立方法 9つのステップを徹底解説

マイクロ法人の設立は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を一つひとつ理解すれば誰でも行うことができます。
ここでは、会社の基本事項の決定から設立後の各種届出まで、マイクロ法人設立の全プロセスを9つのステップに分けて具体的に解説します。
ステップ1 会社の基本事項を決定する
法人設立の第一歩は、会社の骨格となる基本事項を決めることです。
これらは定款に記載する重要な項目であり、後から変更するには費用と手間がかかるため、慎重に検討しましょう。
商号(会社名)
商号は会社の顔となる名前です。
自由に決められますが、いくつかのルールがあります。
まず、同一の住所に同じ商号の会社は登記できません。
また、使える文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、一部の記号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)に限られます。
事業内容がイメージしやすい、覚えやすい商号を考えましょう。
法務局の「オンライン登記情報検索サービス」や「国税庁法人番号公表サイト」で、類似の商号がないか事前に調査することをおすすめします。
事業目的
事業目的は、その会社がどのような事業を行うのかを明記するものです。
定款に記載されていない事業は原則として行えないため、現在行う事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある事業も幅広く記載しておきましょう。
目的の数は10個程度が一般的です。
また、事業内容によっては許認可が必要な場合がありますので、事前に確認が必要です。
本店所在地
本店所在地は、会社の住所となる場所です。
自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなどが選択肢となります。
自宅を本店所在地にすることも可能ですが、賃貸物件の場合は規約で法人の登記が禁止されていないか確認が必要です。
また、自宅住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィスの利用も有効な選択肢です。
資本金
会社法上、資本金は1円から設立可能ですが、資本金の額は会社の信用度や体力を示す指標にもなります。
設立当初の運転資金(少なくとも3ヶ月分程度)を目安に設定するのが一般的です。
許認可が必要な事業では、最低資本金額が定められている場合もあります。
また、資本金が1,000万円未満の場合、設立1期目と2期目の消費税が原則免除されるというメリットもあります。
役員構成
マイクロ法人の場合、役員は自分一人(取締役1名)というケースがほとんどです。
株式会社の場合は最低1名の取締役が、合同会社の場合は最低1名の業務執行社員が必要です。
一人社長であれば、複雑な機関設計(取締役会や監査役の設置など)は不要で、最もシンプルな構成で問題ありません。
事業年度
事業年度は、会社の会計期間(決算期)をいつにするかということです。
日本の多くの企業は4月1日から翌年3月31日としていますが、自由に決めることができます。
繁忙期を避けたり、消費税の免税期間を最大限活用できる時期(設立日から最も遠い月を決算月にするなど)を考慮して設定するのが賢明です。
ステップ2 法人用の印鑑を作成する
会社の基本事項が固まったら、法人運営に必要となる印鑑を作成します。
一般的には、以下の3本セットを準備しておくと便利です。
| 印鑑の種類 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| 会社実印(代表者印) | 法務局への登記申請、重要な契約書 | 法務局に登録する、会社にとって最も重要な印鑑。通常は丸印。 |
| 銀行印 | 法人口座の開設、手形・小切手の発行 | 金融機関との取引で使用。実印との兼用はリスク管理上避けるべき。 |
| 角印(社印) | 請求書、見積書、領収書など日常的な書類 | 認印として使用。会社の権威を示す役割も持つ。 |
印鑑は即日作成できるサービスもありますが、余裕をもって2〜3日、長くても1週間程度で手元に届くように注文しておきましょう。
ステップ3 定款を作成し認証を受ける(株式会社の場合)
定款(ていかん)とは、会社の組織や運営に関する基本ルールを定めた「会社の憲法」ともいえる重要な書類です。
ステップ1で決めた基本事項を基に作成します。
株式会社の場合は、作成した定款を公証役場に持参し、公証人による「認証」を受ける必要があります。
この認証手続きには約5万円の手数料がかかります。
一方、合同会社の場合は定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。
なお、紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款で作成すればこの印紙代は不要になります。
費用を抑えたい場合は電子定款の活用を検討しましょう。
ステップ4 資本金を払い込む
定款の作成(株式会社の場合は認証)が終わったら、発起人(会社設立者)個人の銀行口座に、定めた資本金を振り込みます。
この時点ではまだ法人口座は開設できないため、必ず個人の口座を使用します。
振り込みが完了したら、その口座の通帳のコピー(表紙、裏表紙、振り込みが記帳されたページ)を取り、それらをまとめて「払込証明書」という書類を作成します。
この払込証明書は、後の登記申請で必要になります。
ステップ5 登記申請書類を作成する
次に、法務局へ提出する設立登記の申請書類一式を準備します。
会社形態(株式会社か合同会社か)によって必要書類が異なりますが、主に以下のような書類が必要です。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付)
- 定款
- 発起人の決定書
- 取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書(発起人・取締役のもの)
- 払込証明書
- 印鑑届書
これらの書類のひな形は、法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
記入漏れやミスがないよう、慎重に作成しましょう。
ステップ6 法務局へ設立登記を申請する
すべての書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。
申請方法は、法務局の窓口へ持参する、郵送する、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で行う、の3つがあります。
法務局が申請書類を受理した日が、会社の設立日(創立記念日)となります。
特定の日を設立日にしたい場合は、その日に合わせて申請を行いましょう。
ただし、法務局は土日祝日は閉庁しているため、平日に申請する必要があります。
ステップ7 登記完了後に各種証明書を取得する
登記申請後、通常1週間から2週間程度で登記が完了します。
登記が完了したら、今後の手続きに必要となる以下の証明書を取得します。
- 登記事項証明書(登記簿謄本):法人口座の開設や税務署への届出などで必要です。複数枚取得しておくと良いでしょう。
- 印鑑証明書:法人実印の印鑑証明書です。こちらも契約や手続きで必要になります。
これらの証明書を取得するためには、まず法務局で「印鑑カード」の交付申請を行う必要があります。
忘れずに手続きしましょう。
ステップ8 税務署や自治体へ法人設立の届出を行う
会社の登記が完了したら、税務や社会保険に関する各種届出を、それぞれの管轄の役所へ提出します。
提出期限が短いものもあるため、速やかに行いましょう。
主な届出は以下の通りです。
| 提出書類名 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署、都道府県税事務所、市町村役場 | 設立後2ヶ月以内(自治体により異なる) |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立後3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設後1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 適用を受けたい月の前月末まで |
特に「青色申告の承認申請書」は、提出しないと税制上の様々な優遇措置が受けられないため、必ず期限内に提出してください。
ステップ9 年金事務所などで社会保険の加入手続きを行う
最後のステップは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きです。
マイクロ法人は、たとえ社長一人であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。
社会保険の手続きは管轄の年金事務所で行います。
「新規適用届」や「被保険者資格取得届」などの書類を提出します。
従業員を雇用しない一人社長の場合、労働保険の加入は任意ですが、従業員を一人でも雇用する場合は加入が必須となりますので、管轄の労働基準監督署やハローワークで手続きを行いましょう。
マイクロ法人設立の必要書類と費用一覧
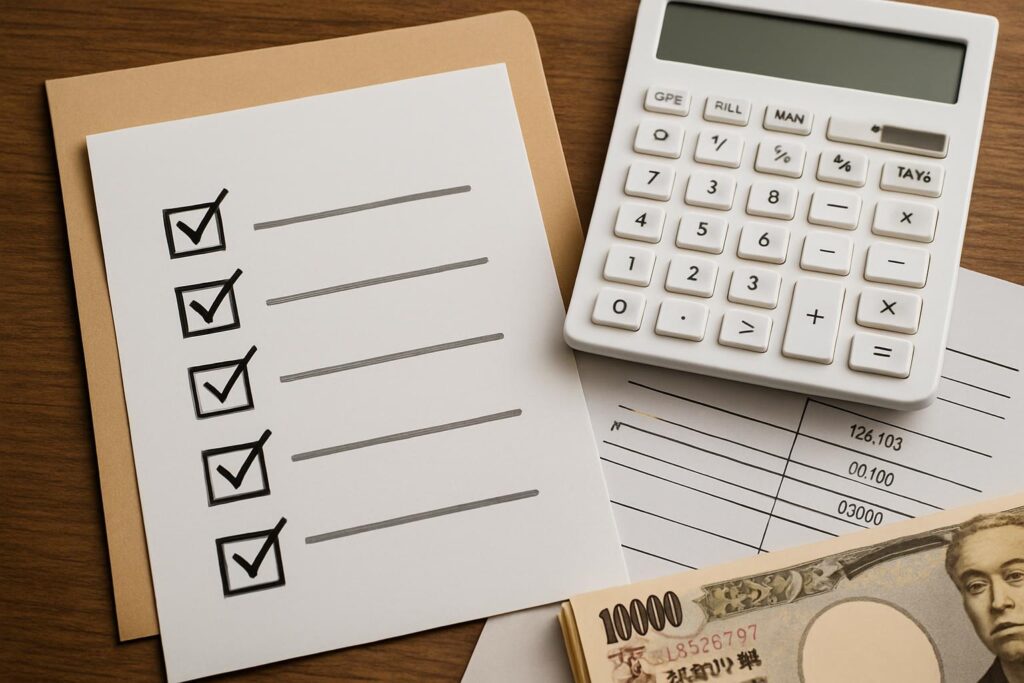
マイクロ法人の設立手続きを進めるにあたり、どのような書類が必要で、どれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことは非常に重要です。
特に、会社形態として株式会社を選ぶか、合同会社を選ぶかで必要書類や法定費用が大きく異なります。
この章では、設立に必要な書類を網羅したチェックリストと、費用の内訳を分かりやすく比較解説します。
設立手続きに必要な書類チェックリスト
法務局へ設立登記を申請する際に必要となる主な書類は以下の通りです。
会社形態によって必要なものが異なるため、ご自身のケースに合わせて準備を進めましょう。
| 書類名 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 設立登記申請書 | 必須 | 必須 | 法務局のウェブサイトからテンプレートをダウンロードできます。 |
| 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙 | 必須 | 必須 | 登録免許税額分の収入印紙を郵便局などで購入し、A4用紙に貼り付けます。 |
| 定款 | 必須 | 必須 | 株式会社は公証役場での認証が必要。合同会社は認証不要です。 |
| 発起人の決定書(または発起人会議事録) | 必須 | 該当なし | 本店所在地や役員などを決定したことを証明する書類です。 |
| 設立時取締役の就任承諾書 | 必須 | 該当なし | 取締役全員分が必要です。印鑑証明書と同じ印鑑で押印します。 |
| 設立時代表取締役の就任承諾書 | (※) | 該当なし | 取締役会を設置しない場合は不要です。 |
| 設立時監査役の就任承諾書 | (※) | 該当なし | 監査役を設置する場合に必要です。 |
| 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面 | 該当なし | 必須 | 定款で定めていない場合に必要となります。 |
| 代表社員の就任承諾書 | 該当なし | 必須 | 代表社員になる人の就任承諾書です。 |
| 印鑑証明書 | 必須 | 必須 | 取締役(合同会社では業務執行社員)全員分が必要な場合があります。 |
| 資本金の払込証明書 | 必須 | 必須 | 発起人(社員)個人の銀行口座のコピーなどで作成します。 |
| 印鑑届書 | 必須 | 必須 | 会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。 |
| OCR用申請用紙(登記すべき事項) | 必須 | 必須 | CD-Rなどの電磁的記録媒体で提出することも可能です。 |
※は、会社の機関設計によって必要性が変わる書類です。
設立にかかる費用の内訳【株式会社と合同会社を比較】
マイクロ法人の設立費用は、大きく「法定費用」と「その他の費用」の2つに分けられます。
法定費用は、法律で定められた必ず支払わなければならない費用であり、自分自身で手続きを行っても専門家に依頼しても同額が発生します。
法定費用(登録免許税・定款印紙代など)
法定費用は、株式会社と合同会社で金額が大きく異なります。
特に登録免許税の差が大きく、合同会社の方が9万円以上安く設立できます。
| 費用項目 | 株式会社の費用 | 合同会社の費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 紙の定款で作成する場合に必要。電子定款の場合は0円になります。 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 | 公証役場で定款の認証を受ける際に支払う手数料。合同会社は認証が不要です。 |
| 定款謄本手数料 | 約2,000円 | 0円 | 認証された定款の謄本(写し)を発行してもらうための費用です。 |
| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 | 法務局へ設立登記を申請する際に納める税金です。(資本金額 × 0.7%)が最低額に満たない場合は最低額を納付します。 |
| 合計(紙定款の場合) | 約222,000円~ | 約100,000円~ | – |
| 合計(電子定款の場合) | 約182,000円~ | 約60,000円~ | – |
その他の費用(印鑑作成費・専門家への報酬など)
法定費用以外にも、会社の運営準備に必要な実費や、手続きを代行してもらう場合の専門家への報酬が発生します。
- 法人印鑑の作成費用:
会社実印(代表者印)、銀行印、角印の3本セットで5,000円~30,000円程度が相場です。素材や品質によって価格は大きく変動します。 - 各種証明書の取得費用:
設立手続きに必要な発起人や役員の印鑑証明書(1通300円程度)や、設立後に取得する会社の登記事項証明書(登記簿謄本、1通600円)、印鑑証明書(1通450円)などの取得費用です。 - 専門家への依頼報酬:
司法書士や行政書士に設立手続きの代行を依頼する場合の報酬です。50,000円~150,000円程度が目安ですが、依頼する業務範囲によって異なります。 - 会社設立サービスの利用料:
「会社設立freee」などのオンラインサービスを利用する場合の費用です。無料で利用できるサービスから、専門家のサポートが付いた有料プランまで様々です。
設立費用を安く抑える方法 電子定款の活用
マイクロ法人の設立費用を最も効果的に抑える方法は、「電子定款」を活用することです。
電子定款とは、紙ではなくPDFなどの電子データで作成された定款のことを指します。
最大のメリットは、紙の定款で必須となる収入印紙代40,000円が不要になる点です。
これは、印紙税法において電子データは「課税文書」に該当しないと定められているためです。
株式会社・合同会社のどちらの形態でも、この節約効果は同じです。
ただし、個人で電子定款を作成するには、以下の準備が必要となり、手間と初期投資がかかります。
- マイナンバーカード
- ICカードリーダーライタ(3,000円程度)
- Adobe AcrobatなどのPDF作成ソフト
- 法務省の申請用総合ソフトのインストール
これらの準備が煩雑だと感じる場合は、オンラインの会社設立サービスや専門家への依頼を検討するのがおすすめです。
多くの司法書士事務所などのサービスは電子定款に対応しており、自分でICカードリーダーなどを購入するよりも安価かつ手軽に、印紙代4万円を節約することが可能です。
マイクロ法人設立の最短スケジュールと期間の目安

マイクロ法人の設立準備を始めるとき、「一体どれくらいの期間がかかるのだろう?」と気になる方は多いでしょう。
設立にかかる期間は、選択する方法によって大きく変動します。
一般的に、自分で全ての手続きを行う場合は2週間~1ヶ月、専門家に依頼すれば最短1週間程度が目安です。
ここでは、「自分で設立する場合」「専門家に依頼する場合」「オンラインサービスを利用する場合」の3つのパターンに分け、それぞれのスケジュール感と期間の目安を具体的に解説します。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶための参考にしてください。
自分で設立する場合のスケジュール感
すべての手続きを自分自身で行う場合、一般的に2週間から1ヶ月程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。
特に、書類の準備や各役所での手続きに慣れていない場合は、想定以上に時間がかかる可能性があります。
平日に役所へ行く時間を確保できるかどうかも、全体のスケジュールに影響します。
以下は、自分で合同会社を設立する場合のステップごとの所要期間の目安です。
| ステップ | 手続き内容 | 所要期間の目安 | 備考・注意点 |
|---|---|---|---|
| 1. 準備段階 | 基本事項の決定、法人印鑑の作成・発注 | 2日~5日 | 印鑑は即日作成可能なサービスもありますが、余裕を持つことが大切です。 |
| 2. 定款作成 | 事業目的などを盛り込んだ定款を作成する | 1日~3日 | 株式会社の場合は、この後に公証役場での「定款認証」が必要となり、さらに3日~1週間程度かかります。 |
| 3. 資本金の払込 | 発起人個人の銀行口座に資本金を振り込む | 1日 | 通帳のコピー(表紙、1ページ目、振込履歴のページ)が必要です。 |
| 4. 登記書類の作成 | 設立登記申請書、就任承諾書などを作成・押印する | 2日~4日 | 法務局のウェブサイトにあるテンプレートを活用できますが、記載ミスがないよう慎重に作成する必要があります。 |
| 5. 法務局へ申請 | 管轄の法務局へ登記申請書類を提出する | 半日~1日 | 窓口での提出のほか、郵送やオンライン申請も可能です。 |
| 6. 登記完了 | 法務局での審査、登記完了 | 7日~10日 | 法務局の審査期間が最も時間を要する部分です。繁忙期や書類に不備があった場合はさらに日数がかかります。 |
| 7. 完了後の手続き | 印鑑証明書等の取得、税務署・年金事務所への届出 | 2日~5日 | 登記完了後、速やかに行う必要があります。 |
このように、一つ一つの手続きは数日で終わるものが多いですが、積み重なると相応の期間が必要となります。
特に書類の不備による差し戻しが発生すると、スケジュールが大幅に遅れる原因となるため注意が必要です。
専門家に依頼する場合の最短スケジュール
司法書士などの専門家に設立手続きを依頼する場合、最短で1週間~10日程度での法人設立が可能です。
専門家は手続きに精通しており、電子定款やオンライン申請システムを最大限に活用するため、圧倒的なスピード感が魅力です。
専門家に依頼した場合の一般的な流れは以下の通りです。
- 無料相談・ヒアリング(1日目)
司法書士と面談し、会社の基本事項(商号、目的、資本金など)を伝えます。 - 依頼者による準備(1~2日目)
印鑑証明書の取得や法人印鑑の発注、資本金の払込など、依頼者側で必要な準備を進めます。 - 専門家による書類作成・手続き代行(2~5日目)
司法書士が定款や登記申請書類一式を迅速に作成します。電子定款を利用するため、公証役場へ出向く必要もありません。 - 法務局へのオンライン申請(5日目)
書類が整い次第、司法書士がオンラインで登記申請を行います。 - 登記完了・書類の受け取り(7~10日目)
登記が完了したら、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書などの必要書類一式を受け取ります。
費用はかかりますが、「時間を節約したい」「手続きのミスを防ぎたい」「本業に集中したい」という方にとっては、最も確実でスピーディーな方法と言えるでしょう。
会社設立freeeなどのサービスを利用した場合
近年、費用を抑えつつ手続きを効率化できるオンラインの会社設立サービスが人気です。代表的なサービスである「会社設立freee」などを利用した場合、おおよそ1週間~2週間程度で設立手続きを完了させることができます。
この方法は、専門家への依頼と自分で行う手続きの「良いとこ取り」とも言える選択肢です。
オンラインサービス利用時の流れと期間
- 情報入力(1日)
サービスのガイドに従って、画面上で会社の基本情報を入力します。迷うことなく直感的に進められるのが特徴です。 - 必要書類の自動作成(即時)
入力した情報をもとに、定款や登記申請書などの必要書類が自動で生成されます。 - 電子定款の作成・認証(2~4日)
多くのサービスでは、提携する専門家が電子定款の作成・認証を代行してくれます。これにより、自分で公証役場へ行く手間と定款印紙代4万円が節約できます。 - 資本金の払込・書類の押印(1日)
作成された書類を印刷・押印し、資本金の払込を済ませます。 - 法務局への申請・登記完了(7~10日)
完成した書類一式を自分で法務局へ提出します。申請後の審査期間は他の方法と同様です。
オンラインサービスは、設立費用を安く抑えながらも、書類作成の手間を大幅に削減したいという方に最適な方法です。
ただし、最終的な法務局への申請は自分で行う必要があるため、その時間だけは確保しておく必要があります。
マイクロ法人の設立方法は3つ 自分に合った方法を選ぼう

マイクロ法人の設立手続きを進める方法は、大きく分けて3つあります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、かかる費用や時間も異なります。
ご自身の状況や何を優先したいかに合わせて、最適な方法を選択することが、スムーズな法人設立の第一歩です。
ここでは、それぞれの方法の特徴を詳しく解説します。
方法1 すべて自分で設立手続きを行う
専門家や代行サービスに頼らず、定款の作成から法務局への登記申請、設立後の各種届出まで、すべての手続きを自分自身で行う方法です。
会社設立に関する一連の流れをすべて自分で経験できるため、経営者としての知識を深めることができます。
最大のメリットは、設立費用を最も安く抑えられる点です。
特に、電子定款を作成すれば、通常は紙の定款に必要な4万円の収入印紙代が不要になります。
コストを徹底的に削減したい方にとっては、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
一方で、デメリットは膨大な時間と手間がかかることです。
必要な書類を調べ、不備なく作成するには、会社法などの専門知識が求められます。
もし書類に不備があれば、法務局へ何度も足を運ぶことになり、想定以上に時間がかかってしまうリスクもあります。
本業の準備と並行して進める場合、大きな負担になる可能性を考慮しておく必要があります。
この方法がおすすめな人
- 設立費用を1円でも安く抑えたい方
- 時間に余裕があり、会社設立のプロセスを学びたい方
- 過去に会社設立の経験がある、または会社法務に詳しい方
方法2 司法書士などの専門家に設立を依頼する
会社設立の専門家である司法書士や、場合によっては行政書士、税理士に手続きを代行してもらう方法です。
煩雑な書類作成や登記申請をすべて任せられるため、安心して手続きを進めることができます。
この方法のメリットは、時間と手間を大幅に削減し、本業の準備に集中できることです。
専門家が手続きを行うため、書類の不備といったミスがなく、確実かつスピーディーに設立が完了します。
また、事業目的に関するアドバイスや、設立後の運営を見据えた定款の作成など、専門的な視点からのサポートを受けられる点も大きな魅力です。
税理士に依頼する場合、設立後の顧問契約とセットにすることで、設立手数料が割引または無料になるケースもあります。
デメリットは、当然ながら専門家への報酬(手数料)が発生することです。
報酬額は依頼する専門家や業務範囲によって異なりますが、一般的に5万円から15万円程度が相場となり、自分で設立するよりも総費用は高くなります。
この方法がおすすめな人
- 手続きの手間を省き、本業に集中したい方
- ミスなく、確実に法人を設立したい方
- 設立後の税務や法務についても相談できる専門家を探している方
- 資金に余裕があり、時間を節約したい方
方法3 オンラインの会社設立サービスを利用する
「会社設立freee」や「マネーフォワード 会社設立」に代表される、オンライン完結型の会社設立サービスを利用する方法です。
近年、多くの起業家に利用されており、費用と手間のバランスが最も良い選択肢として注目されています。
最大のメリットは、専門知識がなくても、画面の指示に従って情報を入力するだけで、必要な書類一式を自動で作成できる手軽さです。
多くのサービスが電子定款に標準対応しているため、印紙代4万円も節約できます。専門家に依頼するより費用を抑えつつ、自分で一から調べるよりもはるかに簡単かつスピーディーに手続きを進められるのが特徴です。
また、設立後の会計ソフトや法人用クレジットカードとの連携がスムーズなサービスも多く、設立後の事業運営の効率化にも繋がります。
デメリットとしては、定款の内容を細かくカスタマイズしたい場合など、特殊なケースには対応しきれない可能性があります。
また、サービス利用自体は無料でも、提携する金融機関の口座開設や法人カードの申し込みが条件となっている場合があるため、利用前に条件をよく確認することが重要です。
この方法がおすすめな人
- 費用は抑えたいが、自分で調べる時間や手間はかけたくない方
- PCやスマートフォンの操作に慣れている方
- 設立後の経理やバックオフィス業務も効率化したいと考えている方
| 設立方法 | 費用 | 手間・時間 | 専門性 | 確実性 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 自分で設立 | ◎ 最も安い | △ 非常にかかる | △ 必要 | △ 不備のリスクあり |
| 2. 専門家に依頼 | △ 高い(手数料) | ◎ ほとんどかからない | ◎ 不要 | ◎ 非常に高い |
| 3. オンラインサービス利用 | ○ 安い | ○ かからない | ○ 不要 | ○ 高い |
マイクロ法人設立後の注意点と運営のポイント

法人設立はゴールではなく、あくまでスタートです。
マイクロ法人のメリットである社会保険料の最適化や節税効果を最大限に享受するためには、設立後の適切な運営が不可欠です。
ここでは、特に重要となる3つのポイント、「役員報酬の設定」「税金と決算申告」「法人住民税均等割」について詳しく解説します。
役員報酬の設定と社会保険料のシミュレーション
マイクロ法人設立の最大の目的とも言えるのが、社会保険料の最適化です。
その鍵を握るのが「役員報酬」の設定です。個人事業主としての事業所得と、マイクロ法人からの役員報酬を組み合わせることで、世帯全体の手取り額を最大化することを目指します。
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、役員報酬の金額に応じて決まる「標準報酬月額」を基準に算出されます。
そのため、役員報酬を低く設定することで、社会保険料の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、役員報酬は事業年度の途中で自由に変更することはできません。
「定期同額給与」の原則に基づき、事業年度開始から3ヶ月以内に決定した金額を、その年度中は毎月同額で支払い続ける必要があります。
生活費や個人事業とのバランスを十分に考慮して、慎重に金額を決定しましょう。
具体的に役員報酬をいくらに設定すると、社会保険料はどのくらいになるのでしょうか。
以下にシミュレーション例を示します。
| 役員報酬(月額) | 標準報酬月額 | 健康保険料(月額) | 厚生年金保険料(月額) | 合計(月額) | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,000円 | 58,000円 | 約2,894円 | 約5,307円 | 約8,201円 | 約98,412円 |
| 63,000円 | 68,000円 | 約3,393円 | 約6,222円 | 約9,615円 | 約115,380円 |
| 100,000円 | 98,000円 | 約4,890円 | 約8,967円 | 約13,857円 | 約166,284円 |
※上記は協会けんぽ(東京都)の令和6年度保険料額表を参考に算出した概算値です。介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当する場合は、健康保険料が変動します。実際の金額は必ず最新の保険料額表をご確認ください。
個人事業主として国民健康保険と国民年金を支払う場合、所得によっては年間80万円以上の負担になるケースも少なくありません。
比較すると、マイクロ法人を活用した社会保険料の最適化効果がいかに大きいかがお分かりいただけるでしょう。
法人税などの税金と決算申告
法人を設立すると、個人事業主とは異なる税金を納める義務が生じます。
また、年に一度の決算と税務申告が必須となります。
マイクロ法人が納める主な税金は以下の通りです。
| 税金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 法人税 | 法人の所得(利益)に対して課される国税です。資本金1億円以下の中小法人の場合、所得のうち年800万円以下の部分には軽減税率(15%)が適用されます。 |
| 法人住民税 | 法人の所在地である都道府県・市区町村に納める地方税です。法人税額に応じて課される「法人税割」と、赤字でも発生する「均等割」から構成されます。 |
| 法人事業税 | 法人の所得に対して課される地方税(都道府県税)です。所得が一定額以下の場合、税負担が軽減される場合があります。 |
| 消費税 | 原則として、資本金1,000万円未満で設立した場合、設立から2事業年度は納税が免除されます。ただし、インボイス制度の登録事業者になる場合は、課税事業者を選択する必要があります。 |
これらの税金を計算し、申告するために、法人は事業年度が終了した日の翌日から2ヶ月以内に決算を行い、税務署へ確定申告書を提出しなければなりません。
日々の取引を正確に記帳し、決算書(貸借対照表、損益計算書など)を作成する必要があります。
会計ソフト(freee会計やマネーフォワード クラウドなど)を活用すれば自分で行うことも可能ですが、複雑で専門知識を要するため、税理士に依頼するのが一般的です。
特にマイクロ法人の場合、設立後の税務顧問を依頼することで、適切な節税対策や経営のアドバイスを受けることができます。
赤字でも発生する法人住民税均等割に注意
法人運営で見落としがちですが、非常に重要なのが「法人住民税の均等割」です。
これは、法人の所得(利益)がゼロ、つまり赤字であったとしても、法人が存在するだけで必ず支払わなければならない税金です。
均等割は、法人が事業所を置く自治体に対して支払う会費や場所代のようなものとイメージすると分かりやすいでしょう。
税額は資本金の額と従業員数によって決まりますが、マイクロ法人の場合、最低でも年間約7万円の負担が発生します。
| 【法人住民税均等割の最低額の例(東京都23区内の場合)】 ・都道府県民税:20,000円 ・市町村民税:50,000円 ・合計:70,000円 |
この均等割は、法人を維持していくための固定コストとなります。
たとえ売上が全くなくても支払い義務が生じるため、法人設立前にランニングコストとして必ず把握しておきましょう。
事業計画を立てる際には、この均等割の負担も忘れずに組み込んでおくことが大切です。
まとめ
本記事では、マイクロ法人の設立方法について、メリット・デメリットから具体的な手順、費用までを網羅的に解説しました。
マイクロ法人設立は社会保険料の最適化に有効ですが、コストや事務負担も考慮が必要です。
特に一人社長なら、費用を抑えられる合同会社がおすすめです。
設立方法は、ご自身の状況に合わせて、自分で行うか、司法書士や会社設立freeeなどのオンラインサービスを活用するかを選択しましょう。
この記事を参考に、最適な方法で設立準備を進めてください。