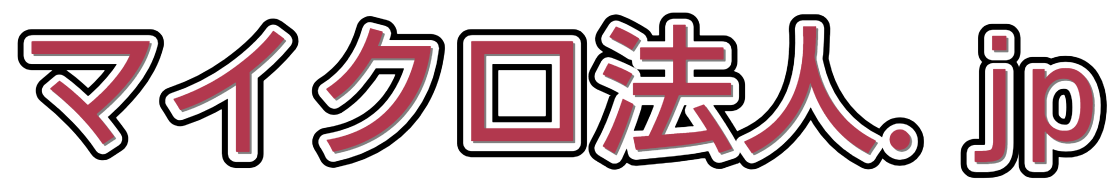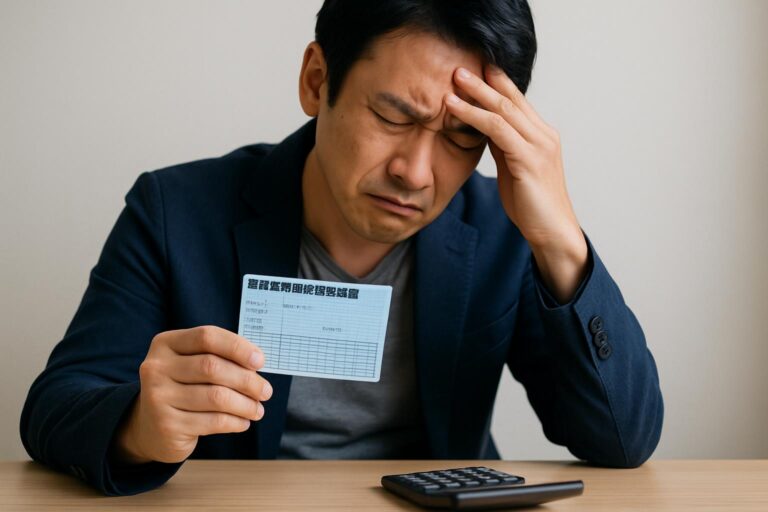個人事業主の国民健康保険料、高すぎると感じていませんか?
この記事では、会社員との違いや保険料の計算方法を踏まえ、なぜ高くなりがちなのか、その理由を明らかにします。全額自己負担であることや扶養の概念がないことが主な要因です。
さらに、青色申告やiDeCoの活用、減免制度の確認、法人化など、保険料を合法的に安くするための具体的な節約術を網羅的に解説。
負担を軽減するためのヒントが見つかります。
個人事業主の国民健康保険は本当に高すぎるのか
「個人事業主になると、国民健康保険料が想像以上に高くて驚いた」という声は少なくありません。
会社員時代と比較して、負担額が大幅に増えたと感じる方が多いようです。
しかし、なぜ個人事業主の国民健康保険料は「高すぎる」と感じてしまうのでしょうか?
まずは、その背景にある会社員の健康保険との違いや、国民健康保険料の基本的な計算の仕組みを理解することから始めましょう。
会社員の健康保険との違いを理解する
個人事業主が加入する国民健康保険(国保)と、会社員などが加入する健康保険(社会保険、主に協会けんぽや健康保険組合)では、いくつかの大きな違いがあります。
特に保険料の負担割合と扶養の考え方の違いが、「高い」と感じる主な要因となっています。
| 項目 | 国民健康保険(個人事業主など) | 健康保険(会社員など) |
|---|---|---|
| 運営主体 | 市区町村、国民健康保険組合 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合 |
| 保険料負担 | 全額自己負担 | 事業主(会社)と従業員で原則折半 |
| 扶養の概念 | なし(原則として加入者ごとに保険料が発生) | あり(被扶養者の保険料負担は原則なし) |
| 保険料計算の基盤 | 前年の所得など | 標準報酬月額(給与などに応じて決定) |
| 保険料率 | 市区町村ごとに異なる | 都道府県ごと(協会けんぽ)や健康保険組合ごとに異なる |
このように、会社員の場合は給与から天引きされる際に、すでに会社が半額を負担してくれています。
さらに、配偶者や子供などの扶養家族がいても、その家族分の保険料が追加で発生することはありません。
一方、個人事業主は保険料を全額自分で支払う必要があり、家族が国保に加入すればその人数分の保険料(均等割など)も原則として加算されます。
この違いが、負担感の差として大きく現れるのです。
国民健康保険料の計算方法の基本 所得割と均等割
国民健康保険料は、お住まいの市区町村によって計算方法や保険料率が異なりますが、一般的には以下の要素で構成されています。
- 医療分保険料: 加入者の医療費に充てられる部分
- 後期高齢者支援金分保険料: 後期高齢者医療制度を支えるための部分
- 介護分保険料: 40歳から64歳までの方が負担する介護保険料
そして、これらの保険料は主に「所得割」と「均等割」という2つの計算要素の合計で決まります(自治体によっては「平等割」や「資産割」がある場合もあります)。
- 所得割: 加入者の前年の所得(総所得金額等から基礎控除などを引いた基準額)に応じて計算される部分。所得が多いほど保険料も高くなります。
- 均等割: 加入者一人ひとりに対して均等に課される部分。所得に関わらず、加入者数に応じてかかります。
つまり、国民健康保険料は、「所得に応じた負担(所得割)」と「加入者数に応じた負担(均等割)」の組み合わせで計算されるのが基本です。
所得割の計算基礎となる所得は、収入から必要経費や各種所得控除(基礎控除など)を差し引いた後の金額です。
この計算方法の詳細は、次の章でさらに詳しく解説します。
具体的な保険料率や計算方法は、お住まいの市区町村のウェブサイトや窓口で確認することが重要です。
例えば、東京都世田谷区の令和6年度の計算例などが公開されています。
このように、会社員の健康保険との構造的な違い、そして所得や加入者数に応じて計算される国民健康保険料の仕組みが、「個人事業主の国民健康保険は高すぎる」と感じる背景にあると言えるでしょう。
なぜ個人事業主の国民健康保険料は高くなりがちなのか その理由を解説

個人事業主になると、会社員時代と比べて国民健康保険料が高いと感じることが少なくありません。
その背景には、会社員と個人事業主とで健康保険制度の仕組みが大きく異なる点が挙げられます。
ここでは、なぜ個人事業主の国民健康保険料が高くなりがちなのか、その主な理由を詳しく解説します。
理由1 全額自己負担であること 会社員との大きな違い
会社員が加入する健康保険(協会けんぽや企業の健康保険組合など)では、保険料は勤務先の会社と従業員本人とで折半して負担するのが一般的です。
例えば、月額の保険料が4万円だった場合、自己負担は2万円で済みます。
これは健康保険法第161条第1項で「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する」と定められているためです(組合管掌健康保険の場合は規約で変更可能)。
一方、個人事業主が加入する国民健康保険では、保険料の全額が自己負担となります。
会社による負担がないため、同じ所得水準であっても、会社員時代と比較して負担感が大きくなるのはこのためです。
この違いが、個人事業主の国民健康保険料が高いと感じる最も大きな理由の一つと言えるでしょう。
理由2 所得の計算方法と所得控除の仕組み
国民健康保険料は、主に前年の所得に基づいて計算される「所得割」と、加入者数に応じて計算される「均等割」の合計で決まります。
この所得割の計算基礎となる所得(賦課基準額)の考え方が、会社員の場合と異なる点も高くなりがちな要因です。
国民健康保険料の計算に使われる賦課基準額は、一般的に「前年の総所得金額等 – 住民税の基礎控除額」で算出されます。
住民税の基礎控除額は、合計所得金額2,400万円以下の場合、43万円です(令和3年度以降)。
出典: 個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (※基礎控除額に関する一般的な説明として)
会社員の場合、給与収入から給与所得控除が差し引かれた後の「給与所得」が基準となります。
給与所得控除は収入に応じて自動的に計算され、例えば年収500万円の場合、給与所得控除額は144万円(収入金額×20%+44万円。令和2年分以降)です。
個人事業主の場合、売上(収入)から必要経費を差し引いた「事業所得」が基準となります。
青色申告を行えば最大65万円または55万円の青色申告特別控除が受けられますが、会社員の給与所得控除に比べると、所得計算上有利不利が生じる可能性があり、結果として賦課基準額が高めになることがあります。
特に、経費として計上できるものが少ない業種の場合、この影響が大きくなる傾向があります。
理由3 自治体による保険料率の違いと上限額
国民健康保険の運営主体は市区町村(および国民健康保険組合)です。
そのため、保険料率や均等割額は、お住まいの自治体によって異なります。
保険料率は、各自治体の医療費水準や加入者の所得水準、年齢構成などによって毎年見直され、決定されます。
一般的に、高齢者が多い、あるいは所得水準が相対的に低い自治体では、一人当たりの医療費が高くなる傾向があり、保険料率も高めに設定されることがあります。
逆に、財政に余裕のある自治体では、独自の軽減措置を設けている場合もあります。
保険料は、以下の3つの区分で構成され、それぞれに所得割率と均等割額(一人あたり)が定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 医療分保険料 | 加入者の医療費に充てられる保険料 |
| 後期高齢者支援金分保険料 | 後期高齢者医療制度を支えるための保険料 |
| 介護納付金分保険料 | 40歳から64歳までの加入者が負担する介護サービス費用に充てられる保険料 |
これらの料率や均等割額は自治体ごとに異なるため、同じ所得であっても住んでいる場所によって保険料が変わってきます。
例えば、近隣の市町村でも料率が異なることは珍しくありません。
また、国民健康保険料には年間上限額(賦課限度額)が設けられています。
所得が非常に高い場合でも、この上限額を超える保険料が賦課されることはありません。
この上限額も、上記の医療分・支援金分・介護分それぞれに、国が示す標準的な基準を参考にしつつ、自治体ごとに条例で定められています。
令和6年度の国の基準では、医療分が65万円、後期高齢者支援金分が24万円(令和5年度は22万円から引き上げ)、介護分(40歳~64歳)が17万円とされています。
出典: 国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について – 厚生労働省 (令和6年度の国の基準)
お住まいの自治体の具体的な保険料率や上限額は、自治体のウェブサイトや広報誌、または国民健康保険担当窓口で確認することが重要です。
理由4 扶養の概念がないこと 原則として加入者ごとに保険料が発生
会社員が加入する健康保険には「被扶養者」という制度があります。
これは、生計を同一にする配偶者や子ども、両親などが一定の収入条件等を満たせば、被保険者(会社員本人)の扶養に入ることができ、被扶養者自身の追加の保険料負担は発生しないというものです。
出典: 被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
一方、国民健康保険には、この「扶養」という概念がありません。
そのため、世帯に加入者が複数いる場合、原則として加入者一人ひとりに対して保険料(主に均等割額)が発生します。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族で、夫が個人事業主の場合、妻や子どもに所得がなくても、人数分の均等割額が加算されます(所得割は世帯全体の所得に応じて計算されますが、均等割は加入者ごとにかかります)。
具体的には、所得のない子どもであっても、医療分と支援金分の均等割が課されます。
これにより、家族の人数が多い世帯ほど、国民健康保険料の総額が高くなる傾向にあります。
これが、会社員時代に家族を扶養に入れていた方が、個人事業主になって国民健康保険に切り替えた際に、保険料が大幅に上がったと感じる大きな要因の一つです。
ただし、負担軽減策として、未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割保険料については、令和4年4月から国による軽減措置が導入され、5割減額(半額)となっています。
この軽減措置は、申請が不要な場合が多いですが、自治体によって取り扱いが異なる場合があるため確認が必要です。
出典: 未就学児に係る国民健康保険料(税)の均等割額の減額措置について – 厚生労働省
これらの理由から、個人事業主の国民健康保険料は会社員と比較して高くなりがちです。
しかし、これらの仕組みを正確に理解し、利用できる控除や制度を最大限に活用することで、負担を軽減できる可能性があります。
個人事業主が国民健康保険料を合法的に安くする節約術

個人事業主の国民健康保険料は、所得や自治体によって大きく変動しますが、工夫次第で負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、合法的に国民健康保険料を安くするための具体的な節約術を詳しく解説します。
所得控除を最大限に活用する
国民健康保険料の所得割額は、前年の総所得金額等から各種所得控除を差し引いた「基準所得金額」をもとに計算されます。
したがって、所得控除を漏れなく活用し、課税対象となる所得を圧縮することが、保険料節約の基本となります。
青色申告特別控除を利用する
個人事業主が確定申告を行う際、青色申告を選択し、一定の要件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この控除は課税所得を直接減らすため、国民健康保険料の所得割額の軽減に繋がります。最大65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳、貸借対照表および損益計算書の添付、そしてe-Taxによる申告または電子帳簿保存が必要です。
55万円の控除であれば、これらの条件が少し緩和されます。
参考: 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
小規模企業共済等掛金控除 iDeCoや小規模企業共済の活用
個人事業主が利用できる代表的な制度として、iDeCo(個人型確定拠出年金)と小規模企業共済があります。
これらの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除され、課税所得を減らす効果があります。
結果として、国民健康保険料の所得割額の軽減にも繋がります。
- iDeCo(個人型確定拠出年金): 老後の資産形成を目的とした私的年金制度です。掛金は月額5,000円から拠出でき、上限額は国民年金の被保険者種別などによって異なります。個人事業主(第1号被保険者)の場合、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料と合算して月額6万8,000円(年間81万6,000円)が上限です。
- 小規模企業共済: 個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。掛金は月額1,000円から7万円までの範囲で自由に設定でき、全額が所得控除の対象となります。参考: 中小企業基盤整備機構「制度のメリット|小規模企業共済(中小機構)」
これらの制度は節税効果が高いだけでなく、将来への備えにもなるため、積極的に活用を検討しましょう。
生命保険料控除や医療費控除など忘れずに申告
上記の他にも、個人事業主が利用できる所得控除は多数あります。
これらを漏れなく確定申告で申告することで、課税所得を圧縮し、国民健康保険料の負担軽減に繋げることができます。
| 控除の種類 | 概要 | 控除額(上限など) |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に応じて一定額が控除される。 | 新制度(平成24年1月1日以降契約):各保険種類ごとに最高4万円、合計で最高12万円 旧制度(平成23年12月31日以前契約):各保険種類ごとに最高5万円、合計で最高10万円 |
| 医療費控除 | 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除。生計を一にする配偶者やその他親族の医療費も対象。 | (実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%) 上限200万円 |
| 地震保険料控除 | 支払った地震保険料に応じて一定額が控除される。 | 最高5万円 |
| 社会保険料控除 | 自身や生計を一にする配偶者・親族のために支払った国民年金保険料、国民年金基金の掛金などが全額控除される。 | 支払った全額 |
| 寄付金控除 | 特定の団体(国、地方公共団体、特定公益増進法人など)に寄付をした場合に受けられる控除。 | (特定寄付金の合計額 – 2千円)または(総所得金額等の40%相当額 – 2千円)のいずれか低い金額 |
これらの控除を忘れずに申告することが重要です。
経費を正しく計上して課税所得を抑える
国民健康保険料の算定基礎となる所得は、売上から必要経費を差し引いたものです。
したがって、事業に関連する支出を漏れなく経費として計上し、課税所得を適正に抑えることが重要です。
家賃や水道光熱費の一部を家事按分して経費に計上するなど、見落としがちな経費がないか確認しましょう。
ただし、経費として認められるのは事業遂行上必要なものに限られ、領収書や帳簿などの証拠書類の保存が必須です。
参考: 国税庁「No.2210 必要経費の知識」
国民健康保険の減免制度や軽減制度を確認する
所得が低い場合や、災害、失業、倒産などの特別な事情により保険料の支払いが困難になった場合、国民健康保険料の減免制度や軽減制度を利用できる可能性があります。
これらの制度は、自治体によって内容や適用条件が異なります。
- 法定軽減: 前年中の世帯の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額や平等割額(自治体によっては設定なし)が7割、5割、2割軽減されます。申請は原則不要ですが、所得の申告が必要です。
- 独自の減免制度: 自治体が独自に設けている減免制度もあります。例えば、失業や事業不振、災害による被害などが対象となることがあります。こちらは申請が必要な場合がほとんどです。
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口やウェブサイトで、利用できる制度がないか確認してみましょう。
参考: 厚生労働省「国民健康保険の保険料(税)の軽減・減免制度について」
特定の業種なら国民健康保険組合への加入を検討する
個人事業主の中には、市区町村が運営する国民健康保険ではなく、同種の事業または業務に従事する者で組織される国民健康保険組合(国保組合)に加入できる場合があります。
医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、建設業、理美容業、文芸美術国民健康保険組合など、様々な業種の国保組合が存在します。
国保組合のメリットは、保険料が所得に関わらず一定額であったり、市区町村の国民健康保険よりも保険料が安くなる場合がある点です。
また、独自の付加給付(傷病手当金など)がある組合もあります。
ただし、加入には業種や地域などの条件があり、保険料や給付内容は組合によって異なります。
ご自身の業種に該当する国保組合があるか調べ、加入条件や保険料を比較検討してみましょう。
参考: 全国国民健康保険組合協会「国保組合一覧 | 全国国民健康保険組合協会」
家族の社会保険の扶養に入ることを検討する 条件あり
個人事業主であっても、配偶者や親族が加入している会社の健康保険(社会保険)の被扶養者になれる可能性があります。
被扶養者として認定されれば、自身で国民健康保険料を支払う必要がなくなります。
被扶養者になるための主な条件は以下の通りです(加入している健康保険組合によって詳細が異なる場合があります)。
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること。
- 被保険者(扶養者)の年間収入の2分の1未満であること(同居の場合)。
- 被保険者によって主として生計を維持されていること。
個人事業主の場合、収入は売上から必要経費を差し引いた所得で判断されるのが一般的ですが、健康保険組合によっては売上総額で判断される場合もあるため、事前に確認が必要です。
条件を満たせるようであれば、大きな節約に繋がる可能性があります。
参考: 全国健康保険協会 協会けんぽ「被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会」
法人化 法人成りを検討して社会保険に加入する
事業が軌道に乗り、所得が一定額を超えてくると、個人事業主から法人成り(会社を設立)して、役員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する方が、国民健康保険料と国民年金保険料の合計負担額よりも安くなる場合があります。
社会保険料は会社と個人で折半して負担するため、全額自己負担の国民健康保険料と比較して、個人の手取り額が増える可能性があります。
また、社会保険の健康保険には扶養の概念があり、条件を満たせば家族を被扶養者にすることができ、その場合、家族の保険料負担は発生しません。
ただし、法人化には設立費用や維持費用(税理士費用、法人住民税の均等割など)がかかり、会計処理も複雑になります。
メリット・デメリットを総合的に比較検討し、税理士などの専門家にも相談しながら慎重に判断することが重要です。
一般的には、課税所得が800万円~1,000万円程度を超えてくると法人化を検討する目安の一つと言われています。
参考: 日本年金機構「適用事業所とは? | こんな時にはどうする?(適用事業所) | 日本年金機構」
国民健康保険料が高すぎると感じたらまずやるべきこと

個人事業主の方にとって、国民健康保険料の負担は決して軽いものではありません。
「高すぎる!」と感じたとき、感情的に対処するのではなく、まずは冷静に状況を把握し、適切な行動をとることが大切です。
ここでは、保険料が高いと感じた際に、最初に取り組むべき具体的なステップを解説します。
自身の保険料の計算根拠を市区町村に確認する
国民健康保険料の通知書が届き、その金額に驚いたとしても、まずはご自身の保険料が正しく計算されているかを確認することが最初のステップです。
計算ミスや誤解がある可能性もゼロではありません。
また、計算根拠を理解することで、今後の対策を考える上でも役立ちます。
確認は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口(例:区役所や市役所の「保険年金課」「国保年金課」など)で行うことができます。
事前に電話で予約が必要な場合や、確認に必要な持ち物がある場合もあるため、訪問前に一度問い合わせておくとスムーズです。
市区町村の窓口で確認すべき主なポイントと、持参すると良いものは以下の通りです。
| 項目 | 確認すべき内容・持参物 |
|---|---|
| 保険料決定通知書・納入通知書 | 必ず持参し、記載されている所得額、保険料率、算定基礎額、軽減・減免の適用状況などを一つひとつ確認しましょう。不明な点があれば、その場で職員に質問します。 |
| 所得の確認 | 国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されます。確定申告書の控えを持参し、通知書に記載されている所得金額と一致しているかを確認します。万が一、所得の申告内容に誤りがあった場合は、修正申告が必要になることもあります。 |
| 保険料の計算方法 | 所得割額、均等割額(自治体によっては平等割額も)のそれぞれの計算方法や、適用されている料率について説明を受けましょう。特に、ご自身の所得に対してどの料率が適用され、どのように計算されているのかを具体的に把握することが重要です。 |
| 加入者の状況 | 世帯内の加入者数や年齢構成が正しく反映されているか確認します。 |
| 軽減・減免制度の適用 | 所得が一定基準以下の場合に適用される軽減制度や、失業・災害など特別な事情がある場合に適用される減免制度があります。自身がこれらの制度の対象になっていないか、適用されている場合はその内容が正しいかを確認しましょう。対象となる可能性がある場合は、申請方法についても確認が必要です。 |
| その他持参すると良いもの | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑、国民健康保険証。 |
問い合わせの際は、感情的にならず、具体的にどの部分について知りたいのかを明確に伝えることが大切です。
事前に質問事項をメモしておくと、聞き忘れを防ぐことができます。
多くの自治体では、国民健康保険料の計算方法や料率についてウェブサイトで公開していますので、そちらも参考にすると良いでしょう。
例えば、お住まいの「〇〇市 国民健康保険料」で検索すると、該当する情報が見つかるはずです。
(参考例:具体的な自治体名ではなく、一般的な案内として)
お住まいの市区町村のウェブサイトで「国民健康保険料について」といったページをご確認ください。例として、東京都新宿区の国民健康保険料のページでは、計算方法や料率、軽減制度について詳しく解説されています。
引用元: 新宿区「国民健康保険料の計算方法・料率(令和6年度)」https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken_kokuho_hokenryo01_002019.html (アクセス日:2024年5月15日)
税理士や社会保険労務士など専門家に相談する
市区町村に確認しても納得がいかない場合や、より専門的なアドバイス、具体的な節約策について検討したい場合は、税務や社会保険の専門家に相談することも有効な手段です。
専門家は、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスや、法的な観点からのサポートを提供してくれます。
相談する専門家としては、主に税理士と社会保険労務士が考えられます。
- 税理士:国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、所得計算のプロである税理士に相談することで、適正な所得申告や経費計上、各種所得控除の活用など、節税を通じた保険料負担の軽減策についてアドバイスを受けられます。特に青色申告の活用や、見落としがちな控除について専門的な知見を得られるでしょう。
- 社会保険労務士:社会保険全般の専門家であり、国民健康保険制度の詳細や、法人化した場合の社会保険(健康保険・厚生年金)との比較、国民健康保険組合への加入検討、公的な給付金や助成金の活用など、社会保険制度全般を見渡した上でのアドバイスが期待できます。
専門家に相談するメリットは、客観的かつ専門的な視点から、ご自身の状況に最適な解決策や取るべき行動が明確になることです。
また、複雑な手続きの代行を依頼できる場合もあります。
相談先を選ぶ際のポイントと、相談時に準備しておくと良いものは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談先の選び方 | 個人事業主やフリーランスのサポート実績が豊富な専門家を選ぶ。初回相談無料やオンライン相談などを活用し、複数の専門家から話を聞いて比較検討する。料金体系が明確であるかを確認する。話しやすく、信頼できると感じる専門家を選ぶ。 |
| 相談する際の準備 | 直近数年分の確定申告書の控え国民健康保険料の決定通知書・納入通知書事業の収支状況がわかる資料(帳簿など)家族構成や収入状況がわかるもの相談したい内容や質問事項をまとめたメモ |
専門家への相談には費用がかかる場合がありますが、長期的に見れば保険料の適正化や節約につながり、結果として費用以上のメリットが得られる可能性もあります。
まずは相談料や業務範囲について事前に確認しましょう。
税理士や社会保険労務士を探す際は、以下のウェブサイトなどが参考になります。
- 日本税理士会連合会「税理士を探す」:お近くの税理士を検索できます。
引用元: 日本税理士会連合会 https://www.nichizeiren.or.jp/search-zeirishi/ (アクセス日:2024年5月15日) - 全国社会保険労務士会連合会「都道府県社会保険労務士会一覧」:各都道府県の社会保険労務士会のウェブサイトから、会員検索などが利用できる場合があります。
引用元: 全国社会保険労務士会連合会 https://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/organization/tabid/200/Default.aspx (アクセス日:2024年5月15日)
国民健康保険料が高いと感じたときは、一人で抱え込まず、まずは正確な情報を把握し、必要に応じて専門家の力も借りながら、最適な解決策を見つけていきましょう。
まとめ
個人事業主の国民健康保険料は、会社員のような事業主負担がなく全額自己負担であること、そして扶養の概念がないため、収入によっては高額になりがちです。
保険料は所得や自治体によって異なります。
節約のためには、青色申告特別控除やiDeCoなどの所得控除を最大限活用し、経費を正確に計上することが基本です。
また、減免制度の確認や、業種によっては国民健康保険組合への加入、法人化も有効な手段となりえます。
まずはご自身の保険料を確認し、最適な方法を検討しましょう。