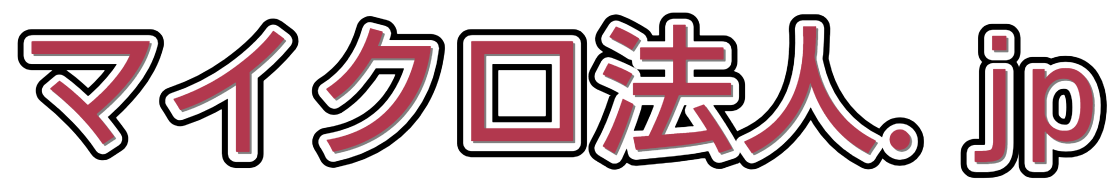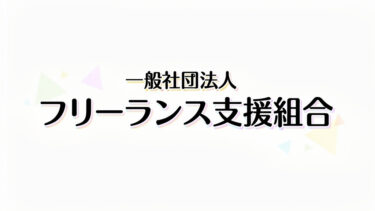マイクロ法人を設立すると、個人事業主より所得税を安くできます。
本記事では、給与所得控除や所得分散、社会保険料の最適化といった3つの仕組みで節税できる理由を徹底解説。
所得500万円から1000万円までの具体的なシミュレーションで、手取り額がいくら増えるのかを比較します。
法人化のメリット・デメリットも踏まえ、あなたがマイクロ法人を設立すべきか判断できるよう、必要な情報を網羅的にガイドします。
マイクロ法人で所得税が安くなる3つの仕組み
マイクロ法人を設立すると、なぜ所得税が安くなるのでしょうか。
その背景には、個人事業主とは異なる税金の計算方法が大きく関係しています。
具体的には「給与所得控除の活用」「所得の分散」「社会保険料の最適化」という3つの仕組みを組み合わせることで、大きな節税効果が生まれます。
ここでは、それぞれの仕組みがどのように所得税の負担を軽減するのか、一つずつ詳しく解説していきます。
仕組み1 給与所得控除の活用で課税所得を減らす
マイクロ法人を設立する最大のメリットの一つが、「給与所得控除」という強力な控除制度を活用できる点です。
個人事業主の場合、事業で得た利益(売上から経費を引いたもの)が事業所得となります。
ここから差し引ける控除は、主に青色申告特別控除(最大65万円)です。
一方、マイクロ法人を設立すると、自分自身に「役員報酬」という形でお給料を支払うことができます。
この役員報酬は税法上「給与所得」として扱われ、給与所得控除が適用されます。給与所得控除は、給与収入に応じて自動的に計算される「みなし経費」のようなもので、実際の経費の有無にかかわらず、収入から一定額を差し引くことができます。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額 × 40% – 100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
例えば、年間500万円の所得がある場合を考えてみましょう。
個人事業主であれば、青色申告特別控除65万円を差し引けます。
しかし、マイクロ法人から役員報酬として500万円を受け取ると、
給与所得控除額は「500万円 × 20% + 44万円 = 144万円」
となります。
控除額が65万円から144万円へと大幅に増えるため、所得税の計算対象となる課税所得を大きく圧縮できるのです。
この差が、所得税額に直接的な影響を与えます。
仕組み2 所得分散による所得税の超過累進税率の緩和
日本の所得税は「超過累進税率」という仕組みを採用しています。
これは、所得が高くなればなるほど、より高い税率が適用されるというものです。
個人事業主の場合、事業で得た利益のすべてが個人の所得となるため、利益が大きくなると高い税率区分に該当しやすくなります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
マイクロ法人を活用すると、この問題を解決できます。
法人が得た利益をすべて役員報酬として個人に移すのではなく、一部を個人の役員報酬とし、残りを法人の利益として会社に残す「所得分散」が可能になります。
例えば、利益が800万円あった場合、個人事業主なら800万円全体に超過累進税率が適用されます。
しかし、マイクロ法人であれば、役員報酬を400万円に設定し、残りの400万円を法人の利益とすることができます。
これにより、個人の所得に適用される最高税率を低く抑え、法人に残した利益には比較的低い法人税率が適用されるため、トータルでの税負担を軽減できるのです。
仕組み3 社会保険料の最適化がもたらす節税効果
所得税の直接的な仕組みではありませんが、社会保険料の負担を最適化することも、結果的に手取り額を増やし、所得税の節税につながる重要なポイントです。
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しますが、特に国民健康保険料は所得に応じて増加し、上限額も高いため大きな負担となりがちです。
マイクロ法人を設立すると、役員として健康保険と厚生年金(社会保険)に加入する義務が生じます。
社会保険料は、法人から受け取る役員報酬(標準報酬月額)を基準に決定されます。
ここで重要なのは、役員報酬を意図的に低く設定することで、社会保険料の負担を大幅に抑えることが可能になるという点です。
例えば、役員報酬を月額6万円程度に抑えれば、社会保険料は最低限の金額で済みます。
もちろん、生活費は役員報酬だけでは足りませんが、多くのマイクロ法人活用者は、個人事業主としての事業も並行して行い、そちらの収入で生活費を賄います。
この「法人と個人の二刀流」により、社会保険料の負担を最小化しつつ事業を継続できるのです。
社会保険料は全額が社会保険料控除の対象となるため、支払額が減れば控除額も減りますが、それ以上に保険料負担の軽減効果が大きく、可処分所得を最大化する上で極めて有効な戦略となります。
【所得別】マイクロ法人の所得税を個人事業主と比較シミュレーション

マイクロ法人を設立することで、所得税や社会保険料の負担がどれほど軽減されるのか、具体的な数字で見てみたい方も多いでしょう。
ここでは、事業所得が「500万円」「800万円」「1000万円」の3つのケースで、個人事業主とマイクロ法人(役員報酬を最適化したケース)の手取り額を比較シミュレーションします。
ご自身の所得状況と照らし合わせながら、法人化のメリットを具体的にイメージしてみてください。
※シミュレーションの前提条件は以下の通りです。
- 対象者:独身、扶養家族なし、東京都新宿区在住
- 個人事業主:青色申告(65万円控除)、国民健康保険・国民年金に加入
- マイクロ法人:役員報酬を月額4.5万円(年額54万円)に設定。社会保険(協会けんぽ・厚生年金)に加入。残りは法人利益とする。
- 控除:基礎控除、社会保険料控除、青色申告特別控除、給与所得控除のみを考慮。
- 手取り額の定義:
- 個人事業主:事業所得 – (所得税 + 住民税 + 社会保険料)
- マイクロ法人:役員報酬の手取り額 + 法人の内部留保(税引後利益)
※本シミュレーションは概算です。実際の税額や保険料は、個々の状況やお住まいの自治体によって変動します。
所得500万円の場合の所得税と手取り額
まずは、フリーランスとして独立して数年が経ち、安定した収入を得られるようになった所得500万円のケースです。
この段階で法人化を検討する方は少なくありません。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 500万円 | 500万円 |
| 役員報酬 | – | 54万円 |
| 社会保険料 | 約66万円 | 約16万円(※) |
| 所得税 | 約22万円 | 0円 |
| 住民税 | 約32万円 | 0円 |
| 法人税等 | – | 約72万円 |
| 手取り額合計 | 約380万円 | 約412万円 |
※マイクロ法人の社会保険料は労使折半後の本人負担額と法人負担額の合計です。
所得500万円の場合、マイクロ法人を設立することで、手取り額が年間約32万円増加するという結果になりました。
この差を生み出している最大の要因は「社会保険料」と「給与所得控除」です。
個人事業主の国民健康保険料は所得に応じて高くなりますが、マイクロ法人では役員報酬を低く抑えることで社会保険料を最小限にできます。
さらに、役員報酬54万円に対して55万円の給与所得控除が適用されるため、個人の課税所得が0円となり、所得税・住民税がかからなくなるのです。この効果は非常に大きいと言えるでしょう。
所得800万円の場合の所得税と手取り額
次に、事業が軌道に乗り、高所得者層の入り口ともいえる所得800万円のケースを見ていきましょう。
この所得帯では、所得税の超過累進税率の影響が大きくなり始めます。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 800万円 | 800万円 |
| 役員報酬 | – | 54万円 |
| 社会保険料 | 約103万円 | 約16万円(※) |
| 所得税 | 約71万円 | 0円 |
| 住民税 | 約57万円 | 0円 |
| 法人税等 | – | 約118万円 |
| 手取り額合計 | 約569万円 | 約666万円 |
※マイクロ法人の社会保険料は労使折半後の本人負担額と法人負担額の合計です。
所得800万円になると、その差はさらに広がり、マイクロ法人の方が年間で約97万円も手取り額が多くなる計算です。
個人事業主の場合、所得税率が20%から23%へと上がり、国民健康保険料も上限に近づくため、負担が急増します。
一方、マイクロ法人は役員報酬を低く抑えることで個人の所得税・住民税・社会保険料を最小化し、利益の大部分を法人に残します。
法人利益にかかる法人税の実効税率は、個人の所得税・住民税率よりも低いため、所得を分散させることによる節税効果が最大限に発揮されるのです。
所得1000万円の場合の所得税と手取り額
最後に、個人事業主として大きな成功を収めている所得1000万円のケースです。
このレベルになると、法人化による税務戦略が必須と言っても過言ではありません。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 役員報酬 | – | 54万円 |
| 社会保険料 | 約103万円 | 約16万円(※) |
| 所得税 | 約132万円 | 0円 |
| 住民税 | 約77万円 | 0円 |
| 法人税等 | – | 約150万円 |
| 手取り額合計 | 約688万円 | 約834万円 |
※マイクロ法人の社会保険料は労使折半後の本人負担額と法人負担額の合計です。
所得1000万円では、手取り額の差は年間で約146万円にまで達します。
個人事業主の場合、課税所得900万円超の部分には33%という高い所得税率が適用されます。
住民税と合わせると税率は43%にもなり、稼いだ額の半分近くを税金として納めることになります。
マイクロ法人を活用すれば、この高い税率の適用を回避できます。
法人の利益が800万円を超えた部分には高い法人税率(23.2%)が適用されますが、それでも個人の所得税・住民税率よりは低く抑えられます。
シミュレーションからも分かる通り、所得が高くなればなるほど、所得分散による節税効果は絶大です。
所得税だけじゃない マイクロ法人の税金メリット

マイクロ法人の設立を検討する際、多くの方が注目するのは「所得税」の節税効果です。
しかし、マイクロ法人がもたらす税金面のメリットはそれだけにとどまりません。法人化することで、所得税以外の「法人税」や「住民税」、さらには将来の「退職金」に至るまで、多角的な節税が可能になります。
ここでは、所得税以外にマイクロ法人が享受できる3つの大きな税金メリットを詳しく解説します。
法人税の実効税率の低さ
個人事業主の所得にかかる所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されており、最大で45%(住民税と合わせると約55%)にもなります。
一方、法人にかかる法人税は、所得税ほどの急激な累進構造にはなっていません。
特に、資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税には軽減税率が適用されます。
具体的には、課税所得が年800万円以下の部分については低い税率が適用されるため、所得が一定のラインを超えると、個人事業主として高い所得税率で納税するよりも、法人として法人税を納める方が税負担を抑えられるのです。
法人税に加えて、地方法人税、法人事業税、法人住民税などを合算した実質的な税負担率を「実効税率」と呼びます。
所得規模にもよりますが、中小法人の実効税率は概ね25%〜34%程度に収まります。
以下の表で、個人の所得税・住民税率と法人の実効税率を比較してみましょう。
| 課税所得金額 | 個人事業主の税率(所得税+住民税) | 法人の実効税率(中小法人の軽減税率適用時) |
|---|---|---|
| 400万円 | 約30% | 約25% |
| 800万円 | 約33% | 約25% |
| 1,000万円 | 約43% | 約27% |
| 1,500万円 | 約43% | 約34% |
このように、特に課税所得が800万円を超えるあたりから、法人の方が税率面で有利になる傾向があります。
マイクロ法人を設立し、役員報酬を調整して個人の所得を抑えつつ、残りの利益を法人に残すことで、この税率差を最大限に活用できます。
住民税への影響
マイクロ法人を設立すると、住民税の仕組みも変わります。個人事業主の場合、住民税は「所得割(課税所得の一律10%)」と「均等割」の合計額を支払います。
事業の利益がそのまま課税所得のベースになるため、利益が大きければ住民税も高額になります。
一方、マイクロ法人を設立すると、税金の支払いが「個人」と「法人」の2つに分かれます。
- 個人の住民税:法人から受け取る役員報酬(給与所得)に対してかかります。給与所得には「給与所得控除」が適用されるため、同じ収入額でも個人事業主の事業所得に比べて課税所得を低く抑えることができ、結果的に個人の住民税負担が軽減されます。
- 法人の住民税:法人に対して「法人住民税」が課されます。これには、法人税額に応じてかかる「法人税割」と、赤字でも発生する「均等割」があります。均等割は最低でも年間7万円程度の負担となりますが、役員報酬の設定によって個人の住民税負担を最適化することで、トータルの住民税負担をコントロールしやすくなるのが大きなメリットです。
つまり、役員報酬を適切な金額に設定することで、給与所得控除を活かして個人の住民税を抑え、法人と個人を合わせたトータルの税負担を最適化することが可能になるのです。
将来の退職金も経費にできる
個人事業主には「退職金」という概念が存在しません。
事業をたたむ際にまとまった資金を用意しても、それを経費として計上することはできません。
しかし、マイクロ法人を設立すれば、経営者である自分自身に役員退職金を支払うことができ、これを法人の経費(損金)に算入できます。
これは非常に強力な節税策です。退職金を支払う年度は、その分だけ法人の利益が圧縮されるため、法人税を大幅に引き下げることができます。
長年にわたって法人に蓄積してきた利益を、最後に税負担を抑えながら個人に移転させる出口戦略として極めて有効です。
さらに、受け取る側にも大きなメリットがあります。
退職金は「退職所得」として扱われ、税制上非常に優遇されています。
- 退職所得控除:勤続年数に応じて大きな控除額が認められます。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
- 2分の1課税:(退職金の額面 – 退職所得控除額) × 1/2 の金額が課税対象となります。
例えば、勤続15年で1,000万円の退職金を受け取った場合、退職所得控除は「40万円 × 15年 = 600万円」です。
課税対象となる金額は「(1,000万円 – 600万円) × 1/2 = 200万円」となり、給与として受け取る場合に比べて所得税・住民税が劇的に安くなります。
将来の資産形成と引退時の手取り額を最大化する上で、この退職金制度はマイクロ法人が持つ最大のメリットの一つと言えるでしょう。
注意点 マイクロ法人の所得税節税におけるデメリット

マイクロ法人を活用することで、所得税や社会保険料の負担を劇的に軽減できる可能性があります。
しかし、その大きなメリットの裏には、個人事業主のままでは発生しなかったコストや手間といったデメリットも存在します。
節税効果だけを見て安易に法人を設立すると、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。
ここでは、マイクロ法人の設立を検討する上で必ず知っておくべきデメリットや注意点を具体的に解説します。
法人設立と維持にかかるコスト
マイクロ法人の最大のデメリットは、設立時と事業を継続していく上での「コスト」です。
個人事業主であれば開業届を出すだけで済みますが、法人は設立するだけで数十万円の費用がかかります。
さらに、事業を運営していく中でも毎年必ず発生する維持費があり、得られる節税メリットがこれらのコストを上回らなければ、法人化した意味がなくなってしまいます。
法人設立費用
法人を設立するには、定款の認証や法務局への登記申請が必要で、その際に法定費用(法律で定められた手数料や税金)がかかります。
設立する法人の形態として一般的な「株式会社」と「合同会社」では、以下のように費用が異なります。
マイクロ法人の場合、設立費用を抑えられる合同会社が選ばれることが多いです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 不要 |
| 定款用収入印紙代 | 40,000円(電子定款の場合は不要) | 40,000円(電子定款の場合は不要) |
| 合計(紙定款の場合) | 約220,000円~ | 約100,000円 |
| 合計(電子定款の場合) | 約180,000円~ | 約60,000円 |
上記は自分ですべて手続きを行った場合の最低費用です。
司法書士などの専門家に設立手続きを依頼する場合は、これに加えて数万円から10万円程度の報酬が別途必要になります。
税理士費用や法人住民税均等割
法人を維持していくためには、ランニングコストも考慮しなければなりません。
特に大きな負担となるのが、税理士への報酬と法人住民税の均等割です。
税理士費用
法人の決算申告は、個人事業主の確定申告に比べて格段に複雑です。
会計帳簿の作成から法人税申告書の作成まで、専門的な知識が求められるため、多くの場合は税理士に依頼することになります。
税理士に依頼する場合、顧問料として月々数万円、決算申告料として顧問料の4~6ヶ月分が相場となり、年間で数十万円の費用が発生します。
法人住民税均等割
法人住民税は「法人税割」と「均等割」で構成されています。
このうち「均等割」は、法人の所得が赤字であっても、資本金の額や従業員数に応じて課税される税金です。
事業所がある都道府県と市町村にそれぞれ納付する必要があり、最低でも年間合計約7万円の支払い義務が生じます。
これは法人として存在する限り、必ず払い続けなければならないコストです。
社会保険への強制加入と事務負担の増加
マイクロ法人設立の大きな目的の一つが社会保険料の最適化ですが、法人である以上、社会保険への加入は法律上の義務となります。
たとえ社長一人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
個人事業主であれば従業員が5人未満の場合は加入が任意である点と大きく異なります。
この強制加入に伴い、個人事業主時代にはなかった煩雑な事務作業が大幅に増加します。
- 役員報酬の決定と毎月の給与計算
- 給与からの社会保険料と源泉所得税の天引き
- 会社負担分と合わせて社会保険料を年金事務所へ納付
- 源泉所得税を税務署へ納付
- 年末調整の実施
- 社会保険の算定基礎届や月額変更届の提出
これらの手続きはそれぞれに期限が定められており、正確な処理が求められます。
もし手続きを怠ったり間違えたりすると、延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。
これらの事務作業を税理士や社会保険労務士に委託することもできますが、その分、維持コストが増加することになります。
赤字でも税金の支払い義務がある
個人事業主の場合、事業所得が赤字であれば所得税や住民税は課税されません。
しかし、法人の場合は、たとえ事業が赤字で利益が一切出ていなくても、支払わなければならない税金があります。
前述した「法人住民税の均等割」がその代表例です。
これは、法人が地方自治体から受ける行政サービス(道路の整備、警察・消防活動など)の対価として課されるものであり、会社の利益とは無関係に発生します。
事業が思うようにいかず売上がゼロの年であっても、最低約7万円の納税義務は免れません。
この点は、「利益が出ていなければ税金はかからない」という個人事業主の感覚とは大きく異なるため、特に注意が必要です。
マイクロ法人を設立するということは、この毎年必ず発生するコストを許容するということでもあるのです。
マイクロ法人の所得税節税が向いている人の特徴

ここまでマイクロ法人の所得税に関する仕組みやシミュレーション、メリット・デメリットを解説してきました。
では、具体的にどのような人がマイクロ法人を設立し、所得税の節税効果を最大限に享受できるのでしょうか。
ここでは、特にマイクロ法人の設立が向いている人の特徴を2つのタイプに分けて詳しく解説します。
所得が一定額を超えている個人事業主
まず挙げられるのが、事業所得が安定して高水準にある個人事業主の方です。
個人事業主の所得税は、所得が増えるほど税率も高くなる「超過累進税率」が採用されています。
そのため、事業が順調に成長し、課税所得が800万円を超えるあたりから、税負担が急激に重く感じられるようになります。
このような方がマイクロ法人を設立すると、所得を「事業所得」と「給与所得」に分散できます。
法人から自分へ役員報酬を支払い、給与所得控除というサラリーマンと同様の控除を利用することで、課税対象となる所得を圧縮することが可能です。
残りの利益は法人に残し、低い法人税率を適用させることで、個人事業主のまま高額な所得税を納めるよりも、トータルの税負担を大きく軽減できるのです。
具体的にどのくらいの所得から法人化を検討すべきか、以下の表に目安をまとめました。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 法人化の検討度 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 5%~10% | 法人設立・維持コストを考えると、個人事業主のままが有利な場合が多い。 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 社会保険料の負担額によっては、マイクロ法人設立を検討する価値が出てくる。 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 所得税・住民税の節税メリットが法人維持コストを上回る可能性が高く、積極的に検討したいライン。 |
| 900万円超 | 33%~45% | 税率が大幅に上がるため、特別な理由がなければ法人化による節税効果が非常に大きい。 |
もちろん、これはあくまで一般的な目安です。消費税の課税事業者であるか、家族構成、事業の将来性なども含めて総合的に判断することが重要です。
社会保険料の負担を軽くしたいフリーランス
所得税の節税と並んで、マイクロ法人設立の大きな動機となるのが「社会保険料の最適化」です。
特に、Webデザイナー、ITエンジニア、コンサルタントといった高収入のフリーランスにとって、所得に比例して青天井に増えていく国民健康保険料は大きな負担となっています。
個人事業主(フリーランス)は、所得の全額を基に国民健康保険料が計算されます。
一方、マイクロ法人を設立すれば、法人から受け取る「役員報酬」の額に基づいて社会保険料(健康保険・厚生年金)が決定されます。
この仕組みを利用し、役員報酬を社会保険料が最低等級になる金額(月額63,000円未満など)に設定することで、社会保険料の負担を劇的に軽減できるのです。
事業で得た利益の大部分は、役員報酬ではなく法人の利益として残し、事業に必要な経費として利用したり、将来の退職金として積み立てたりすることが可能になります。
この方法は、特に以下のような方に大きなメリットをもたらします。
- 所得は高いが、経費があまりかからない業種のフリーランス
- 国民健康保険料が年間上限額近くになっている方
- 扶養家族がおり、国民健康保険料の負担を重く感じている方
所得税の節税だけでなく、この社会保険料の削減効果も加味することで、手取り額を大幅に増やせる可能性があります。
自身の所得と支払っている社会保険料の額を確認し、法人化した場合のシミュレーションをしてみることを強くおすすめします。
まとめ
マイクロ法人を設立すると、給与所得控除の活用や所得分散により、個人事業主のままよりも所得税を大幅に軽減できる可能性があります。
シミュレーションで示した通り、特に所得が一定額を超える方ほどその節税効果は大きくなります。
ただし、法人設立・維持のコストや社会保険に関する事務負担といったデメリットも存在するため、メリットが上回るか慎重な判断が不可欠です。
ご自身の事業規模や所得状況を踏まえ、専門家にも相談しながら最適な選択をしましょう。