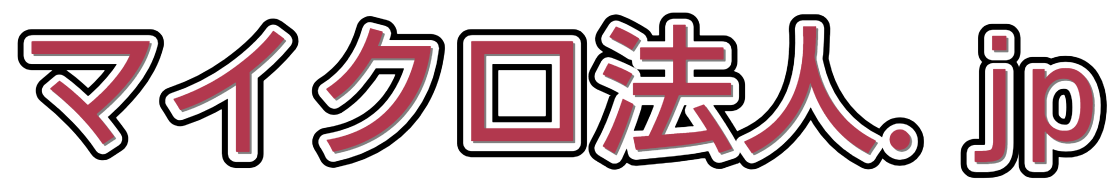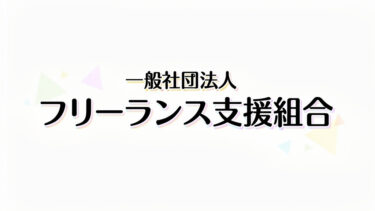マイクロ法人の設立を検討中、または既に設立された方へ。
社会保険料の負担は大きな悩みですが、正しい知識と対策で賢く節約できる可能性があります。
この記事では、マイクロ法人の社会保険料の仕組み、メリット・デメリットを基礎から解説。
さらに、役員報酬の最適化や個人事業主との二刀流など、具体的な節約テクニック(裏ワザ)とその注意点を詳しくご紹介します。
将来の負担を減らし、手元に残るお金を最大化するためのヒントが満載です。
マイクロ法人と社会保険料の基本を理解する
マイクロ法人を設立する、あるいは設立を検討する際に、多くの方が気になるのが「社会保険料」の問題です。
個人事業主のときとは異なり、法人化すると社会保険の取り扱いが大きく変わります。
この章では、まずマイクロ法人と社会保険料に関する基本的な知識を整理し、理解を深めていきましょう。
マイクロ法人とは何か 個人事業主との主な違い
「マイクロ法人」という言葉に、法律上の明確な定義はありません。
一般的には、社長一人、あるいは家族だけで経営している小規模な法人を指すことが多いです。
個人事業主から法人成りする際に、このマイクロ法人の形態を選ぶケースが増えています。
個人事業主とマイクロ法人(法人)の主な違いを理解しておくことは、社会保険料の負担を考える上でも重要です。
以下の表で主な違いを確認しましょう。
| 項目 | マイクロ法人(法人) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 法人格 | あり(法律上の人格) | なし(個人そのもの) |
| 事業主の立場 | 法人の役員(従業員も兼ねる場合あり) | 事業主本人 |
| 税金 | 法人税、法人住民税、法人事業税など | 所得税、住民税、個人事業税など |
| 社会的信用 | 一般的に高いとされる | 法人に比べると低いとされる場合がある |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険への加入が原則義務 | 国民健康保険・国民年金への加入が原則 |
| 経費の範囲 | 役員報酬は給与所得控除の対象。その他、法人として認められる経費の範囲が広い場合がある(例:役員社宅など) | 事業に必要な経費のみ |
特に社会保険については、加入する制度や保険料の計算方法、負担割合が大きく異なります。
この違いが、マイクロ法人化を検討する大きな動機の一つにもなり得ます。
マイクロ法人の社会保険加入は義務なのか
結論から言うと、マイクロ法人であっても、法律上、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は原則として義務です。
たとえ社長一人だけの法人であっても、法人から役員報酬を受け取っている限り、加入対象となります。
これは、健康保険法および厚生年金保険法において、法人(適用事業所)に使用される者(役員を含む)は、原則として被保険者となることが定められているためです。
個人事業主の場合は常時5人以上の従業員を使用する場合などを除き、社会保険の加入は任意ですが、法人は規模に関わらず強制加入となる点が大きな違いです。
「うちは社長一人だから関係ない」ということはありませんので、注意が必要です。
ただし、役員の働き方(常勤か非常勤か)によっては加入義務が生じないケースもありますが、これには厳格な要件があり、安易な判断は禁物です。
この点については後の章で詳しく解説します。
マイクロ法人が加入する社会保険の種類と保険料負担
マイクロ法人が加入する主な社会保険は以下の通りです。
- 健康保険: 業務外の病気やケガ、出産、死亡などに備える医療保険制度。
- 介護保険: 40歳以上65歳未満の方が加入。介護が必要になった際の費用負担を軽減する制度。健康保険料と合わせて徴収されます。
- 厚生年金保険: 老後の生活保障(老齢年金)に加え、障害状態や死亡に対する保障(障害年金・遺族年金)も含む公的年金制度。
従業員を雇用する場合は、上記に加えて以下の保険への加入も必要になります。
- 雇用保険: 労働者の失業や育児・介護休業などに備える保険。
- 労災保険(労働者災害補償保険): 業務中や通勤中のケガ、病気、死亡などに対する補償。
社長一人、あるいは役員のみのマイクロ法人の場合、主に焦点となるのは健康保険(+介護保険)と厚生年金保険です。
これらの保険料は、法人と被保険者(役員)が半分ずつ負担(労使折半)します。
個人事業主が国民健康保険料や国民年金保険料を全額自己負担するのとは異なり、法人も負担義務を負う点が特徴です。
健康保険料と介護保険料
健康保険に加入することで、病気やケガで医療機関にかかった際の医療費自己負担が原則3割(年齢や所得により異なる)になります。
また、高額な医療費がかかった場合の高額療養費制度や、病気やケガで働けなくなった場合の傷病手当金などの給付も受けられます。
マイクロ法人が加入する健康保険は、主に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。
健康保険料率は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが行われます。
40歳以上65歳未満の方は、これに全国一律の介護保険料率が上乗せされます。
厚生年金保険料
厚生年金保険は、日本の公的年金制度の2階部分にあたります。
加入することで、1階部分である国民年金(基礎年金)に上乗せして老齢厚生年金を受け取ることができます。
また、現役時代の収入(標準報酬月額)に応じて保険料・年金額が決まるため、一般的に国民年金のみの場合よりも手厚い保障が期待できます。
厚生年金保険料率は、現在18.3%で固定されており、全国一律です。
この保険料を法人と役員で折半して負担します。
マイクロ法人の社会保険料はどう決まる 標準報酬月額の仕組み
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、どのように計算されるのでしょうか。
その計算の基礎となるのが「標準報酬月額」です。
標準報酬月額とは、役員報酬(給料、手当など報酬として受け取るもの全てを含む)の月額を、一定の幅で区切られた等級(区分)に当てはめたものです。
実際の報酬額そのものではなく、この等級に応じた標準報酬月額に、それぞれの保険料率(健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率)を掛けて保険料が算出されます。
標準報酬月額は、以下のタイミングで決定または改定されます。
- 資格取得時決定: 法人設立時や役員就任時など、新たに社会保険に加入する際に、決定された役員報酬額に基づいて決定されます。
- 定時決定: 毎年1回、7月1日時点の被保険者全員について、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を見直します。この手続きを「算定基礎届」の提出といいます。
- 随時改定: 昇給や減給などにより報酬額が大幅に変動し、一定の条件を満たした場合に、標準報酬月額が見直されます。この手続きを「月額変更届」の提出といいます。
例えば、協会けんぽ(東京都、令和6年度)の場合、健康保険料率は10.00%(40歳未満)または11.82%(40歳以上65歳未満、介護保険料率1.82%含む)、厚生年金保険料率は18.3%です。
仮に標準報酬月額が30万円の場合、健康保険料(40歳未満)は月額30,000円(法人負担15,000円、本人負担15,000円)、厚生年金保険料は月額54,900円(法人負担27,450円、本人負担27,450円)となります。
このように、役員報酬の額が標準報酬月額を決定し、その標準報酬月額に基づいて社会保険料が決まるという仕組みを理解しておくことが、社会保険料の負担を考える上で非常に重要になります。
マイクロ法人化による社会保険料のメリットデメリット

マイクロ法人を設立し、社会保険に加入することには、個人事業主のままでは得られないメリットがある一方で、新たな負担となるデメリットも存在します。
両者を正確に理解し、ご自身の状況に合わせて最適な選択をすることが重要です。
メリット 将来の年金受給額や保障内容が手厚くなる
マイクロ法人化して厚生年金保険・健康保険(協会けんぽ等)に加入する最大のメリットの一つは、将来受け取る年金額の増加と、病気やケガ、出産などに対する保障が手厚くなる点です。
個人事業主が加入する国民年金は、基礎年金部分のみですが、厚生年金保険に加入すると、基礎年金に加えて報酬比例部分の年金が上乗せされます。
これは、支払った厚生年金保険料に応じて将来の年金受給額が増える仕組みであり、老後の生活設計において大きな安心材料となります。
また、健康保険(協会けんぽ等)では、国民健康保険にはない、あるいは内容が異なる手厚い保障が用意されています。
代表的なものとして、病気やケガで働けなくなった場合に所得の一部が保障される「傷病手当金」や、出産のために仕事を休んだ場合に支給される「出産手当金」などがあります。
これらの給付は、万が一の際の経済的な支えとなります。
メリット 家族を社会保険の扶養に入れられるケースも
マイクロ法人の役員として社会保険に加入すると、一定の要件を満たす家族を「被扶養者」として自身の健康保険に加入させられる場合があります。
これは、個人事業主が加入する国民健康保険にはない大きなメリットです。
国民健康保険には「扶養」という概念がなく、家族一人ひとりが被保険者となり、それぞれの所得などに応じて保険料を支払う必要があります。
しかし、健康保険の被扶養者となれば、扶養される家族は追加の保険料負担なしで、被保険者本人と同様の保険給付(医療費の自己負担割合など)を受けることができます。
被扶養者として認定されるためには、主に収入要件(年間収入が130万円未満など)や生計維持関係、同居要件(別居の場合は仕送り額など)を満たす必要があります。
配偶者やお子さん、両親などを扶養に入れることができれば、世帯全体での保険料負担を大きく軽減できる可能性があります。
デメリット 法人としての社会保険料負担が発生する
マイクロ法人化のデメリットとして最も大きいのが、法人自身に社会保険料の負担義務が発生することです。
個人事業主の場合、自身の国民健康保険料と国民年金保険料を支払いますが、法人を設立して役員報酬を受け取るようになると、健康保険料・介護保険料(40歳以上の場合)・厚生年金保険料について、役員個人だけでなく法人も負担しなければなりません。
社会保険料は、原則として役員個人(被保険者)と法人(事業主)が半分ずつ負担する「労使折半」となります。
つまり、役員報酬から天引きされる保険料と同額を、法人も別途納付する必要があるのです。
この法人負担分は、個人事業主の時にはなかったコストであり、マイクロ法人の資金繰りに影響を与える可能性があります。
役員報酬の金額によっては、個人事業主時代の国民健康保険料・国民年金保険料の合計額よりも、マイクロ法人での社会保険料(個人負担分+法人負担分)の合計額の方が高くなるケースも少なくありません。
どの程度の役員報酬を設定すると、どのくらいの社会保険料負担になるのか、事前にシミュレーションしておくことが不可欠です。
個人事業主の国民健康保険 国民年金との比較
マイクロ法人の社会保険と個人事業主の国民健康保険・国民年金を比較すると、以下のような違いがあります。
どちらが有利かは、個々の状況(収入、家族構成、将来設計など)によって異なります。
| 比較項目 | マイクロ法人(役員) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 加入する主な制度 | 健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金保険、介護保険(40歳以上) | 国民健康保険、国民年金、介護保険(40歳以上) |
| 保険料負担者 | 役員個人と法人が原則折半 | 個人事業主本人が全額負担 |
| 保険料の決まり方 | 標準報酬月額(役員報酬等)に応じて決定 | 前年の所得や世帯構成等に応じて決定(自治体により異なる) |
| 扶養の概念 | あり(収入等の要件を満たす家族) | なし(家族それぞれが被保険者) |
| 年金制度 | 国民年金(基礎年金)+厚生年金(報酬比例) | 国民年金(基礎年金)のみ(※国民年金基金等で上乗せ可能) |
| 主な医療保障(本人) | 医療費自己負担(原則3割)、高額療養費制度、傷病手当金、出産手当金など | 医療費自己負担(原則3割)、高額療養費制度など(※傷病手当金等は基本的にない) |
このように、マイクロ法人化による社会保険加入は、保障の手厚さや扶養制度といったメリットがある一方、法人負担というコスト増のデメリットも伴います。
次章以降で解説する社会保険料の節約術も踏まえ、慎重に検討を進めましょう。
マイクロ法人の社会保険料を賢く節約する裏ワザを公開

マイクロ法人を設立する大きなメリットの一つに、社会保険料をコントロールできる可能性が挙げられます。
ここでは、合法的かつ賢く社会保険料負担を軽減するための具体的な「裏ワザ」とも言える方法をいくつかご紹介します。
ただし、いずれの方法もメリットだけでなく注意点やリスクも存在するため、安易な判断は禁物です。
専門家への相談も視野に入れながら、ご自身の状況に最適な方法を検討しましょう。
裏ワザ1 役員報酬の金額を最適化して社会保険料を抑える
マイクロ法人の役員が受け取る役員報酬は、社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」を決定する重要な要素です。
この役員報酬の金額を戦略的に設定することで、社会保険料の負担を最小限に抑えることが可能になります。
社会保険料負担を最小限にする役員報酬設定の考え方
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、標準報酬月額の等級に応じて段階的に設定されています。
つまり、報酬が一定の範囲内であれば、保険料は変わらないということです。
この仕組みを利用し、社会保険料が最も低くなる等級の範囲内で役員報酬を設定する方法が考えられます。
具体的には、健康保険料・厚生年金保険料ともに、最も低い等級に該当する報酬額に設定することを目指します。
例えば、令和6年度の東京都の場合、健康保険の最低等級は標準報酬月額58,000円(報酬月額63,000円未満)、厚生年金保険の最低等級は標準報酬月額88,000円(報酬月額93,000円未満)です。
両方の最低等級に合わせる場合、より高い厚生年金の最低等級に該当する報酬額(例: 月額8万円程度)に設定し、健康保険料もその等級に合わせて支払う、あるいはさらに低い報酬額(例:月額4万5千円~6万円程度)に設定し、健康保険・厚生年金ともに最低等級の保険料負担を目指すといった戦略が考えられます。
ただし、役員報酬を極端に低く設定すると、個人の生活費が不足したり、将来受け取る厚生年金額が減少したりするデメリットがあります。
また、役員としての業務実態に見合わない不相当に低い報酬は、税務調査などで指摘されるリスクもゼロではありません。
生活資金や事業計画、将来設計とのバランスを十分に考慮する必要があります。
役員報酬決定前に社会保険料をシミュレーションする
役員報酬をいくらに設定すれば、社会保険料がいくらになるのかを事前に把握しておくことが極めて重要です。
協会けんぽ(全国健康保険協会)や日本年金機構のウェブサイトでは、最新の保険料額表が公開されています。
これらを利用して、いくつかの報酬パターンで社会保険料を試算してみましょう。
シミュレーションを行うことで、報酬額のわずかな違いで保険料等級が変わり、負担額が大きく変動するケースがあることを理解できます。
より正確なシミュレーションや、個別の状況に応じたアドバイスが必要な場合は、社会保険労務士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
裏ワザ2 非常勤役員として社会保険の適用を外す方法
法人の代表者や役員であっても、一定の要件を満たす「非常勤役員」であれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務がない場合があります。
これにより、法人としての社会保険料負担をなくすことが可能です。
非常勤役員と認められるための要件
どのような場合に非常勤役員と認められるかについて、法律で明確な基準が定められているわけではありません。
しかし、一般的には以下の要素を総合的に勘案して、日本年金機構が実態に基づいて判断します。
| 判断要素 | 内容例 |
|---|---|
| 勤務形態 | 定期的な出勤義務がなく、出勤日数や時間が極めて少ない(例:月に数日程度、必要な会議のみ出席など) |
| 業務内容 | 会社の経営に関する重要な意思決定(役員会など)にのみ関与し、日常的な業務執行には携わらない |
| 役員会等への参加 | 役員会など、経営判断を行う会議への参加状況 |
| 報酬額 | 社会通念上、非常勤として妥当と考えられる程度の低い役員報酬額であること(他の常勤役員や従業員との比較) |
| 他の役職との兼務 | 他の法人の常勤役員や従業員であるなど、その法人での勤務が主たるものではないことが客観的に示せるか |
これらの要素を形式的に満たすだけでなく、実態として非常勤であることが重要です。
例えば、毎日出社して業務を行っているにも関わらず、形式的に非常勤役員として届け出ることは認められません。
社会保険に加入しない場合のリスクと注意点
非常勤役員として社会保険に加入しない場合、その役員個人は、原則として国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
国民健康保険料は前年の所得などに応じて決まるため、所得が高い場合は協会けんぽの保険料よりも高額になる可能性があります。
また、国民年金のみの加入となるため、将来受け取る年金額は厚生年金に加入した場合よりも少なくなります。
さらに、実態が伴わないにも関わらず非常勤として扱っていた場合、年金事務所の調査によって指摘を受け、過去に遡って社会保険への加入と保険料の納付を求められるリスクがあります。
この場合、延滞金なども発生し、結果的に大きな負担となる可能性があります。
裏ワザ3 個人事業主との二刀流による社会保険料コントロール術
近年注目されている方法の一つが、マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」により、社会保険料負担を最適化するスキームです。
これは、マイクロ法人からの役員報酬を社会保険料が低くなる水準(例えば最低等級)に抑え、主な収入は個人事業主として得るという方法です。
マイクロ法人と個人事業の収入バランスを考える
このスキームでは、マイクロ法人からは低い役員報酬のみを受け取るため、法人で支払う社会保険料は最小限に抑えられます。
一方、生活に必要な収入の大部分は個人事業主として稼ぎます。
個人事業主としては、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この方法のメリットは、マイクロ法人での厚生年金加入による将来の年金上乗せ効果を得つつ、国民健康保険料の上限額(所得が多い場合)や、所得に応じた保険料負担を考慮して、トータルの社会保険料負担を調整できる点にあります。
例えば、個人事業の所得が非常に高い場合でも、国民健康保険料には上限があるため、法人で高い役員報酬を得て高額な社会保険料を支払うよりも、トータルコストを抑えられる可能性があります。
二刀流スキームを実行する上での留意点
この二刀流スキームを実行するには、いくつかの重要な留意点があります。
- 事業実態の明確な区分: マイクロ法人の事業と個人事業の事業内容、取引先、経理などを明確に区分し、それぞれ独立した事業として運営している実態が必要です。単に社会保険料を安くするためだけに法人と個人を使い分けていると見なされると、税務署や年金事務所から指摘を受ける可能性があります。
- 法人利益の適切な処理: マイクロ法人で利益が出た場合、役員報酬を低く抑えているため、利益が法人内部に留保されやすくなります。この利益をどのように処理(役員賞与、配当、内部留保など)するか、法人税の負担も考慮した計画が必要です。
- 事務負担の増加: 法人と個人の両方で確定申告や経理処理が必要となり、事務的な負担が増加します。税理士などの専門家のサポートが必要になるケースが多いでしょう。
- 業種による向き不向き: 事業内容によっては、法人格が必要な取引や許認可がある場合など、個人事業との切り分けが難しいケースもあります。
二刀流スキームは、社会保険料だけでなく、所得税、住民税、法人税なども含めたトータルな視点での検討が不可欠です。
メリット・デメリットを十分に理解し、慎重に導入を判断する必要があります。
裏ワザ4 役員社宅制度を活用した社会保険料節約
役員社宅制度を導入することも、社会保険料の節約につながる可能性があります。
これは、法人が所有または賃借した物件を役員に社宅として貸し付け、役員から一定の家賃(賃貸料相当額)を受け取る制度です。
役員報酬の一部を金銭ではなく「住宅の利益」という現物支給の形で提供するイメージです。
役員が法人に支払う家賃が、国税庁が定める「賃貸料相当額」以上であれば、差額は給与として課税されません。
そして、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額は、原則として金銭で支給される報酬に基づいて計算されるため、役員報酬の額面(金銭支給額)を抑えることができれば、結果的に社会保険料も低くなる可能性があります。
例えば、役員報酬を30万円支払う代わりに、役員報酬を25万円に減額し、法人が借り上げた家賃10万円の物件を社宅として提供し、役員から適切な賃貸料相当額(例えば1万円)を受け取るとします。
この場合、社会保険料の計算基礎となる報酬は25万円となり、差額の家賃負担分(実質的な手取り増)は社会保険料の対象外となります。
ただし、役員が法人に支払うべき「賃貸料相当額」の計算は、社宅の床面積や固定資産税評価額などに基づいて複雑な計算が必要です。
計算を誤り、役員負担額が低すぎると、差額分が給与として課税され、社会保険料の対象となるだけでなく、所得税・住民税の追徴課税のリスクもあります。
役員社宅制度の導入・運用にあたっては、税務・社会保険に関する専門的な知識が必要となるため、税理士や社会保険労務士に相談の上、適切な手続きを行うことが不可欠です。
マイクロ法人の社会保険料節約を実行する際の注意点

マイクロ法人を活用した社会保険料の節約術は魅力的ですが、実行にあたってはいくつかの重要な注意点があります。
目先のメリットだけに捉われず、潜在的なリスクやデメリットを十分に理解しておくことが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。
役員報酬を低く設定しすぎることの弊害
社会保険料を抑えるために役員報酬を極端に低く設定する手法は広く知られていますが、これには以下のような弊害が伴う可能性があります。
- 個人の生活への影響: 役員報酬は経営者自身の生活費の原資です。低すぎる報酬設定は、個人の可処分所得を減少させ、生活水準の維持を困難にする恐れがあります。
- 社会的信用力への影響: 住宅ローンや自動車ローン、その他の融資を申し込む際、個人の収入証明が求められます。役員報酬が極端に低い場合、個人の返済能力が低いと判断され、審査で不利になる可能性があります。特に、金融機関によっては安定した収入がないと見なされるリスクも考慮すべきです。
- 将来の保障への影響: 厚生年金の受給額は、加入期間中の標準報酬月額に基づいて計算されます。役員報酬を低く抑えることは、将来受け取る老齢厚生年金の額を直接的に減少させることにつながります。また、万が一の際の障害厚生年金や遺族厚生年金の額にも影響します。
- 役員報酬の変更制限: 法人税法上、役員報酬は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、その事業年度中は毎月同額を支給する「定期同額給与」のルールがあります。一度設定した役員報酬を事業年度の途中で安易に変更することは難しく、変更する場合は税務上のリスクも伴うため、慎重な決定が必要です。
役員報酬の設定は、社会保険料の節約効果だけでなく、個人のライフプランや資金繰り、社会的信用など、多角的な視点から検討することが不可欠です。
年金事務所などによる調査の可能性
社会保険料の負担を軽減するためのスキーム、特に役員報酬の極端な設定や非常勤役員の活用、個人事業主との二刀流による所得分散などは、年金事務所や税務署の調査対象となりやすい点を認識しておく必要があります。
調査では、以下のような点が重点的に確認される可能性があります。
- 役員報酬の妥当性: 設定された役員報酬額が、その役員の業務内容や責任、法人の利益状況などと比較して妥当な範囲内かどうかが問われます。
- 勤務実態の確認: 特に非常勤役員として社会保険の適用を外している場合、実際の勤務日数、勤務時間、業務内容、経営への関与度などが詳細に確認され、名目だけの非常勤ではないかが厳しくチェックされます。役員会議事録やタイムカード、業務日報などの客観的な記録が重要になります。
- 所得分散の合理性: マイクロ法人と個人事業で所得を分散している場合、その事業実態や所得の按分根拠などが確認され、不自然な所得操作がないかどうかが調査される可能性があります。
もし調査によって社会保険の加入逃れや不適切な報酬設定と判断された場合、過去に遡って社会保険料の差額と延滞金を一括で請求される可能性があります。
さらに、税務調査も同時に行われ、追徴課税が発生するケースも少なくありません。
こうしたリスクを回避するためにも、社会保険労務士や税理士などの専門家と相談の上、法令を遵守した適切な運用を心がけ、関連する証拠書類をきちんと整備・保管しておくことが極めて重要です。
将来受け取る年金額への影響を考慮する
マイクロ法人で厚生年金に加入し、役員報酬を低く抑える戦略は、社会保険料の負担を軽減する一方で、将来の老齢厚生年金の受給額に直接的な影響を与えることを忘れてはいけません。
日本の公的年金制度は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て構造になっています(自営業者などは国民年金のみ)。
厚生年金の受給額は、以下の要素で決まります。
- 加入期間: 厚生年金に加入していた期間の長さ。
- 加入期間中の平均標準報酬額: 加入期間中の役員報酬(給与)の平均額。
つまり、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額(役員報酬)を低く設定すればするほど、将来受け取る厚生年金の上乗せ部分が少なくなるのです。
国民年金(基礎年金)部分は報酬額に関係なく、納付期間に応じて決まりますが、厚生年金部分の減少は老後の生活設計に大きな影響を与えかねません。
また、老齢年金だけでなく、病気やケガで働けなくなった場合に支給される障害厚生年金や、加入者が亡くなった場合に遺族に支給される遺族厚生年金の額も、加入中の標準報酬額に基づいて計算される部分があります。
報酬を低く抑えることは、これらの万が一の保障が手薄になる可能性も意味します。
社会保険料の節約を考える際には、目先のコスト削減効果だけでなく、数十年後を見据えた長期的な視点、すなわち老後の生活資金や万が一の保障とのバランスを十分に考慮することが肝心です。
ご自身のライフプランに合わせて、どの程度の年金額が必要なのかを試算し、それに見合った役員報酬設定を検討することが推奨されます。
法改正等による制度変更リスク
現在有効とされているマイクロ法人を活用した社会保険料の節約スキームが、将来にわたって永続的に有効であるとは限りません。
社会保険制度や関連する税法は、社会情勢の変化や財政状況に応じて、頻繁に改正が行われる可能性があるためです。
過去にも、パートタイマーなど短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が段階的に拡大されてきた経緯があります。
今後、マイクロ法人や役員の社会保険加入に関して、以下のような制度変更が行われる可能性も否定できません。
- 役員に対する社会保険適用基準の厳格化: 役員報酬の下限設定や、非常勤役員の認定要件がより厳しくなる可能性。
- 個人事業主との二刀流に対する規制強化: 所得分散による社会保険料負担の軽減を意図したスキームに対する、何らかの制限が設けられる可能性。
- 社会保険料率の変更: 少子高齢化の進展に伴い、将来的に健康保険料や厚生年金保険料の料率が引き上げられる可能性。
これらの法改正や制度変更によって、現在行っている節約策が効果を失ったり、場合によっては法令違反となったりするリスクがあります。
したがって、マイクロ法人を運営する上では、常に社会保険制度や税制に関する最新の情報を収集し、制度変更に適切に対応していく姿勢が求められます。
法改正の内容は複雑な場合も多いため、定期的に税理士や社会保険労務士といった専門家に相談し、自社の状況に合わせたアドバイスを受けることが、リスクを管理し、コンプライアンスを遵守した上で適切な法人運営を続けるために不可欠と言えるでしょう。
マイクロ法人の社会保険加入手続きの基本的な流れ

マイクロ法人を設立し、役員報酬を支払う場合、たとえ社長一人であっても、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
これは、法人格を持つ以上、法律上「適用事業所」となるためです。
ここでは、マイクロ法人が社会保険に加入する際の基本的な手続きの流れについて、具体的に解説します。
手続きをスムーズに進めるために、事前に必要書類や提出先、手続きのタイミングを正確に把握しておくことが重要です。
社会保険加入に必要な書類と提出先
マイクロ法人の社会保険加入手続きは、原則として法人の本店所在地を管轄する年金事務所(または事務センター)で行います。
手続きは窓口への持参のほか、郵送や電子申請(e-Gov)も可能です。主に必要となる書類は以下の通りですが、法人の状況によっては追加書類が必要になる場合もありますので、不明な点は事前に管轄の年金事務所に確認することをおすすめします。
| 書類名 | 概要 | 提出先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 法人として初めて社会保険の適用を受ける(適用事業所となる)際に提出する基本的な書類です。法人の名称、所在地、法人番号などを記載します。 | 管轄の年金事務所(または事務センター) | 適用事業所となった事実発生日から5日以内に提出が必要です。 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 社会保険に加入する役員(社長を含む)や従業員ごとに提出する書類です。氏名、生年月日、基礎年金番号、報酬月額などを記載し、これをもとに標準報酬月額が決定されます。 | 管轄の年金事務所(または事務センター) | 資格取得の事実があった日(通常は法人設立日や役員就任日)から5日以内に提出が必要です。 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 社会保険に加入する役員や従業員に、生計を維持されている扶養家族(配偶者、子など)がいる場合に提出します。被扶養者となるためには収入等の一定の要件を満たす必要があります。 | 管轄の年金事務所(または事務センター) | 被保険者資格取得届と同時に提出することが一般的です。国民年金第3号被保険者関係届も兼ねています。 |
| 法人(商業)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー | 法人の設立年月日、名称、所在地、代表者などを公的に証明するために添付します。 | 管轄の年金事務所(または事務センター) | 原則として発行日から90日以内のものが必要です。新規適用届に法人番号を正確に記載すれば、添付を省略できる場合がありますが、事前に確認すると確実です。 |
| 法人番号指定通知書のコピー | 国税庁から送付される、法人のマイナンバー(法人番号)が記載された書類のコピーです。新規適用届に法人番号を記載するために必要となります。 | 管轄の年金事務所(または事務センター) | 手元にない場合は、国税庁法人番号公表サイトで確認した画面のコピーなどでも代用できる場合があります。 |
| (該当する場合)その他添付書類 | 法人の実際の所在地が登記上の本店所在地と異なる場合(例:バーチャルオフィスを利用している場合など)は、事業所の実態を確認するために賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書などが求められることがあります。 | 管轄の年金事務所(または事務センター) | どのような書類が必要かはケースバイケースなため、事前に年金事務所に確認すると手続きがスムーズに進みます。 |
これらの各種届出用紙は、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
記入方法について不明な点があれば、年金事務所の窓口や電話相談、または社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。
提出書類に不備があると、手続きが遅延し、保険証の発行などが遅れる原因となるため、正確かつ丁寧に記入することが肝心です。
手続きを行うべきタイミング 法人設立後速やかに
社会保険の加入手続きは、健康保険法および厚生年金保険法において、適用事業所となった事実が発生した日から原則として5日以内に行うことと厳格に定められています。
マイクロ法人の場合、通常は法人設立登記が完了し、役員として報酬の支払いが開始されるタイミング(=法人設立日)が「適用事業所となった日」に該当します。
「5日以内」という期限は非常にタイトであるため、現実的には法人設立の登記申請と並行して、社会保険関係の書類準備を進めておくことが賢明です。
法人設立が完了したら、間を置かずに速やかに年金事務所へ書類を提出することを強く推奨します。
万が一、手続きが遅れてしまった場合、最大で過去2年間に遡って社会保険料を納付するよう指導される可能性があります。
この場合、本来支払うべき保険料に加えて、延滞金が課されることもあります。
これは法人にとって大きな負担となり得ます。また、健康保険証の発行が遅れることで、役員やその家族が医療機関を受診する際に一時的に全額自己負担となるなどの不都合が生じる可能性も否定できません。
社会保険への加入は、法人としての法律上の義務です。適切な手続きを怠ると、年金事務所による加入状況の調査や、加入勧奨、場合によっては立入検査や職権による加入手続きが行われるリスクもあります。
コンプライアンス(法令遵守)の観点からも、定められた期限内に確実に手続きを完了させることが、マイクロ法人を健全に運営していく上で非常に重要です。
まとめ
マイクロ法人の設立は、社会保険への加入が原則として義務となります。
これにより厚生年金や健康保険の保障が手厚くなるメリットがある一方、法人としての保険料負担というデメリットも生じます。
しかし、役員報酬の金額を最適化したり、個人事業主との二刀流を検討したりすることで、社会保険料の負担を合法的に軽減できる可能性があります。
ただし、これらの方法には年金事務所の調査リスクや将来の年金受給額への影響といった注意点も伴います。
専門家にも相談し、制度を正しく理解した上で慎重に検討することが重要です。