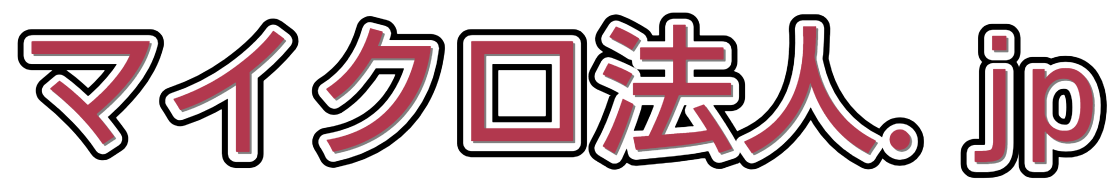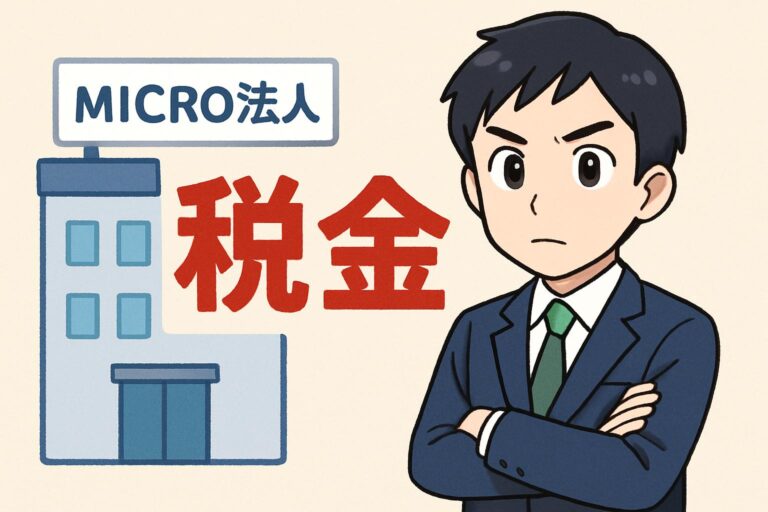マイクロ法人を設立すると税金は本当に安くなるのか、気になっていませんか?
この記事を読めば、個人事業主との税金・社会保険料の違いが、所得500万円・800万円の具体的なシミュレーションでわかります。
結論、マイクロ法人は社会保険料の負担を最適化することで、手取り額を大きく増やせる可能性があります。
設立のメリット・デメリットから、あなたが今すぐ設立すべきかまで判断できる完全ガイドです。
マイクロ法人とは?設立で税金は本当に安くなるのか
「マイクロ法人」という言葉を耳にしたことはありますか?
近年、個人事業主やフリーランス、副業を行う会社員の間で、節税対策の切り札として注目を集めています。
しかし、具体的にどのようなもので、なぜ税金が安くなるのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。
この章では、マイクロ法人の基本的な定義から、設立によって税金や社会保険料が安くなる仕組みの全体像を分かりやすく解説します。
シミュレーションの前に、まずはマイクロ法人の本質を理解しましょう。
マイクロ法人の定義と特徴
はじめに押さえておきたいのは、「マイクロ法人」という言葉は、会社法などの法律で定められた正式な用語ではないということです。
一般的に、従業員を雇わず、社長一人または家族だけで事業を運営する、ごく小規模な会社(法人)を指す俗称として使われています。
その主な目的は、事業の拡大ではなく、個人の所得にかかる税金や社会保険料の負担を最適化することにあります。
多くの個人事業主が、事業所得が増えて税負担が重くなったタイミングで、このマイクロ法人の設立を検討します。
設立される会社の形態としては、「株式会社」または「合同会社」が一般的です。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約20万円~ | 約6万円~ |
| 社会的信用度 | 高い | 株式会社に比べるとやや低い傾向 |
| 意思決定の柔軟性 | 株主総会での決議が必要 | 定款で自由に定められる(迅速) |
| 役員の任期 | 原則2年(最長10年)で再任登記が必要 | 任期なし(登記不要) |
マイクロ法人の場合、外部からの資金調達や上場を目指すわけではないため、設立費用が安く、運営の自由度が高い「合同会社」が選ばれるケースが多いです。
なぜマイクロ法人で税金が安くなる?節税の3つのカラクリ
では、なぜ法人を設立するだけで税金や社会保険料の負担が軽くなるのでしょうか。
その背景には、個人と法人で異なる税制や社会保険制度の仕組みを利用した、3つの大きなカラクリがあります。
カラクリ1:所得分散と「給与所得控除」の活用
最大のポイントは、所得の種類を分けることによる節税効果です。
個人事業主の場合、事業で得た利益はすべて「事業所得」として扱われ、所得が大きくなるほど高い税率(所得税・住民税)が課せられます。
一方、マイクロ法人を設立すると、法人から自分自身へ役員報酬(給与)を支払うことで、所得を「給与所得」として受け取ることができます。
この給与所得には「給与所得控除」という、会社員と同じみなし経費が適用されます。
例えば、年収300万円の場合、98万円もの金額が自動的に控除されるのです。
この給与所得控除を戦略的に活用することで、課税対象となる所得を大幅に圧縮できます。
カラクリ2:社会保険料の最適化
節税効果以上にインパクトが大きいのが、社会保険料の最適化です。
個人事業主が加入する国民健康保険料は、所得に応じて上限なく上がっていきます(自治体ごとに上限あり)。
しかし、マイクロ法人を設立し、役員として健康保険(協会けんぽ等)と厚生年金に加入すれば、社会保険料は役員報酬の金額に基づいて決まります。
つまり、自身の役員報酬を意図的に低く設定することで、社会保険料の負担を最低限にコントロールすることが可能になるのです。
特に所得が高い個人事業主ほど、このメリットは絶大です。
カラクリ3:経費にできる範囲の拡大
法人格を持つことで、個人事業主よりも経費として認められる範囲が広がります。
代表的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 役員社宅:自宅を法人が借り上げ、役員社宅とすることで家賃の一部を経費にできます。
- 出張手当(日当):出張時の交通費や宿泊費とは別に支給される手当で、法人は経費になり、受け取った個人は非課税です。
- 生命保険料:一定の条件を満たす保険商品は、保険料の全額または一部を法人の経費として計上できます。
これらの経費をうまく活用することで、法人の利益を圧縮し、結果的に法人税の節税につながります。
注意!所得によっては個人事業主の方が有利なケースも
ここまでマイクロ法人のメリットを解説してきましたが、誰にとっても得策というわけではありません。
法人を設立・維持するには、定款認証や登記にかかる初期費用(合同会社で約6万円~)に加え、税理士費用や法人住民税の均等割(赤字でも最低約7万円)といったランニングコストが発生します。
そのため、事業所得がそれほど多くない場合、これらのコストが節税メリットを上回ってしまい、かえって手取りが減ってしまう可能性があります。
マイクロ法人を設立して本当にメリットがあるのかどうかは、ご自身の所得状況や事業内容によって大きく異なります。
次の章以降で紹介する具体的なシミュレーションを参考に、あなたにとって最適な選択肢はどちらなのか、慎重に判断することが重要です。
マイクロ法人にかかる税金の種類一覧

マイクロ法人を設立すると、個人事業主が納める所得税や住民税とは異なり、法人として税金を納める義務が生じます。
法人の利益(所得)に対して課される税金が中心となりますが、赤字でも発生する税金もあるため、その仕組みを正しく理解しておくことが重要です。
主に以下の4つの税金が関係してきます。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
ここでは、それぞれの税金がどのようなもので、どのように計算されるのかを詳しく解説します。
法人税
法人税は、法人の事業活動によって得られた所得(利益)に対して課される国税です。
個人における「所得税」に相当する税金と考えると分かりやすいでしょう。
会計上の利益である「税引前当期純利益」を元に、税務上の調整(益金・損金の調整)を行って「課税所得」を算出し、その金額に税率を乗じて税額を計算します。
◆ 計算式:課税所得 × 法人税率
マイクロ法人のような資本金1億円以下の普通法人の場合、所得金額に応じて税率が変動する軽減税率が適用されます。
特に、年間所得800万円以下の部分には低い税率が適用されるため、大きな節税メリットが期待できます。
| 区分(年間所得) | 税率 |
|---|---|
| 800万円以下の部分 | 15% |
| 800万円超の部分 | 23.2% |
※上記は中小企業者等の特例税率です。
法人住民税
法人住民税は、法人が事業所を置く都道府県および市町村に対して納める地方税です。
個人の住民税と同様の考え方ですが、法人の場合は「法人税割」と「均等割」という2つの要素で構成されている点が大きな特徴です。
◆ 計算式:法人税割 + 均等割
法人税割
法人税割は、国に納める法人税額を基準(課税標準)として計算されます。
「法人税額 × 税率」で算出され、税率は事業所のある自治体によって異なります。
均等割
均等割は、法人の所得金額に関わらず、資本金の額や従業員数に応じて課される定額の税金です。
マイクロ法人を設立する上で最も注意すべき点の一つが、この均等割の存在です。
たとえ事業が赤字であっても、法人が存在する限り毎年必ず支払う義務があります。
資本金1,000万円以下、従業員50人以下の場合、最低でも年間合計7万円の均等割が発生します。
| 区分 | 税額 |
|---|---|
| 都道府県民税 | 20,000円 |
| 市町村民税 | 50,000円 |
| 合計 | 70,000円 |
※東京23区内に事業所がある場合は、都民税としてまとめて70,000円が課されます。
法人事業税
法人事業税は、法人が行う事業そのものに対して、事業所のある都道府県に納める地方税です。
道路や港湾といった公共サービスを利用することへの対価としての側面を持ちます。
法人税と同様に、法人の所得を基準に計算されます。
◆ 計算式:課税所得 × 法人事業税率
税率は所得金額に応じて段階的に設定されており、自治体によって異なる場合があります。
また、法人事業税とあわせて「特別法人事業税(国税)」も納付する必要があります。
| 区分(年間所得) | 税率 |
|---|---|
| 400万円以下の部分 | 3.5% |
| 400万円超~800万円以下の部分 | 5.3% |
| 800万円超の部分 | 7.0% |
法人事業税の大きな特徴は、納付した事業税額を翌期の経費(損金)として計上できる点です。
これにより、将来の法人税などを抑える効果があります。
消費税
消費税は、商品やサービスの販売・提供といった取引に対して課される間接税です。
事業者は消費者から預かった消費税を国に納付します。
納税義務は、原則として「基準期間」における課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。
基準期間とは、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。
この仕組みにより、新しく設立したマイクロ法人は、設立1期目と2期目は原則として消費税の納税が免除される(免税事業者となる)という大きなメリットがあります。
個人事業主としてすでに課税事業者になっている場合、マイクロ法人を設立することで、この免税メリットを再度活用できる可能性があります。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 資本金1,000万円以上で法人を設立した場合は、初年度から課税事業者となります。
- 特定期間(前事業年度の開始から6ヶ月間)の課税売上高と給与支払額がともに1,000万円を超えた場合、翌事業年度から課税事業者となります。
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、取引先との関係上、売上が1,000万円以下でもあえて課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択するケースも増えています。
【徹底比較】マイクロ法人の税金と個人事業主の税金の違い

マイクロ法人を設立する最大の目的は、多くの場合「節税」です。
しかし、なぜマイクロ法人にすると税金が安くなるのでしょうか。
その答えは、個人事業主と法人とで、利益(所得)にかかる税金の仕組みが根本的に異なる点にあります。
ここでは、税金の種類、経費の範囲、そして税金と密接に関わる社会保険料など、様々な角度から両者の違いを徹底的に比較・解説します。
税金の種類と税率の違い
まず最も基本的な違いとして、事業で得た利益に対して課される税金の種類と、その税率構造が異なります。
個人事業主は「所得」に対して、法人は「法人所得」に対して、それぞれ異なる税金が課されます。
個人事業主の所得税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる「超過累進課税」が採用されており、最大で45%に達します。
一方、法人税は所得額に応じて税率が変わるものの、個人事業主ほど急激な上昇はなく、比較的緩やかな税率構造になっています。
この税率構造の違いが、節税効果を生む大きな要因の一つです。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 主な国税 | 所得税 課税所得に応じて5%~45%の超過累進課税 | 法人税 法人所得に応じて15%または23.2%(資本金1億円以下の中小法人の場合) |
| 主な地方税 | 住民税(所得割・均等割) 所得割は一律約10% | 法人住民税(法人税割・均等割) 赤字でも均等割(最低7万円~)が発生 |
| その他の主な税金 | 個人事業税 所得290万円超の部分に3%~5% | 法人事業税 法人所得に対して課税 |
| 消費税 | 課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となる(インボイス制度登録事業者を除く) | |
経費にできる範囲の違い
節税を考える上で、税率と同じくらい重要なのが「経費にできる範囲」です。
マイクロ法人にすることで、個人事業主では認められなかった支出を経費として計上できるようになり、課税対象となる所得を圧縮できます。
最も大きな違いは、経営者自身への給与(役員報酬)を経費にできる点です。
個人事業主は事業主自身に給与を支払うという概念がなく、売上から経費を引いた「所得」のすべてが課税対象となります。
しかし、マイクロ法人では自分に支払う役員報酬を経費にでき、さらにその役員報酬は税制上優遇されている「給与所得控除」の対象となるため、二重の節税効果が期待できます。
その他にも、以下のような項目で経費にできる範囲に違いがあります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 経営者自身への給与 | 経費にできない | 役員報酬として経費にできる(給与所得控除の対象) |
| 退職金 | 自分自身への支払いは不可 (小規模企業共済等で備える) | 役員退職慰労金として経費にできる(退職所得控除で税制上有利) |
| 生命保険料 | 生命保険料控除(所得控除)の対象 (上限あり) | 保険の種類や契約形態により、保険料の一部または全額を経費にできる |
| 自宅兼事務所の家賃 | 事業で使う割合を家事按分して経費計上 | 法人名義で契約し、社宅とすることで家賃の大部分を経費にできる(個人負担分は役員報酬から天引き) |
| 出張手当(日当) | 認められない | 旅費規程を整備すれば、非課税で支給でき、法人の経費にもなる |
社会保険料の負担の違い
税金と並んで事業主の大きな負担となるのが社会保険料です。
マイクロ法人設立のメリットとして、この社会保険料を最適化できる点がよく挙げられます。
個人事業主が加入する国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算されるため、所得が増えるにつれて負担も大きくなります(上限あり)。
また、扶養という概念がないため、家族の分も別途保険料がかかる場合があります。
一方、マイクロ法人を設立すると、経営者は健康保険(協会けんぽ等)と厚生年金保険に加入します。
これらの保険料は、法人が支払う「役員報酬」の額(標準報酬月額)を基準に決定されます。
つまり、役員報酬を低く設定すれば、社会保険料の負担を大幅に抑えることが可能です。
また、健康保険には扶養の制度があるため、配偶者や子供の保険料負担がなくなる点も大きなメリットです。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 加入する医療保険 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ 等) |
| 加入する年金制度 | 国民年金 | 厚生年金保険(国民年金も含む) |
| 保険料の算定基準 | 前年の事業所得など | 役員報酬の額(標準報酬月額) |
| 扶養の概念 | なし | あり(被扶養者の保険料負担なし) |
| 保険料の負担 | 全額自己負担 | 法人と個人で折半 |
※個人事業とマイクロ法人を両立する「二刀流」の場合、マイクロ法人で社会保険に加入すれば、個人事業の所得にかかる国民健康保険料は発生しなくなります。
赤字の繰越控除の違い
事業がうまくいかず赤字になってしまった場合の取り扱いにも違いがあります。
赤字を翌年以降の黒字と相殺できる制度を、個人事業主では「純損失の繰越控除」、法人では「欠損金の繰越控除」と呼びます。
この制度を利用するには、どちらも青色申告を行っていることが前提となりますが、赤字を繰り越せる期間に大きな差があります。
- 個人事業主(青色申告):赤字を翌年以降3年間繰り越せる
- マイクロ法人(青色申告):赤字を翌事業年度以降10年間繰り越せる
マイクロ法人は繰越期間が非常に長いため、設立初期に赤字が出たとしても、将来事業が軌道に乗って黒字化した際に、過去の赤字と相殺して法人税の負担を軽減できる可能性が高まります。
この長期的な視点でのリスクヘッジも、法人化のメリットと言えるでしょう。
【所得別】マイクロ法人の税金と社会保険料をシミュレーション

マイクロ法人を設立する最大の目的は、税金や社会保険料の負担を軽減することにあります。
しかし、具体的にどれくらいの節税効果があるのかは、個人の所得によって大きく異なります。
そこでこの章では、個人事業主の所得が500万円と800万円の2つのケースを想定し、「個人事業主のままの場合」と「マイクロ法人を設立した場合(個人事業主との二刀流)」で、手取り額がどう変わるのかを具体的にシミュレーションします。
ご自身の状況と照らし合わせながら、マイクロ法人設立が本当に有利な選択肢なのかを判断するための参考にしてください。
シミュレーションの前提条件
シミュレーションをより現実に近づけるため、以下の共通条件を設定します。
実際の税額や保険料は、お住まいの自治体や加入する健康保険組合、個々の控除額によって変動するため、あくまでモデルケースとしてご覧ください。
- 居住地:東京都新宿区
- 年齢:35歳(介護保険第2号被保険者ではない)
- 家族構成:独身、扶養親族なし
- 事業形態:ITコンサルタント(個人事業税の法定業種)
- 会計処理:青色申告(65万円の特別控除を適用)
- 所得控除:基礎控除、青色申告特別控除、社会保険料控除のみを考慮(生命保険料控除や医療費控除などは考慮しない)
- マイクロ法人の設定:
- 役員は自分一人のみ
- 役員報酬は月額45,000円(年額54万円)に設定。これは社会保険料を最小限に抑えるための一般的な金額です。
- 法人の所得は0円(役員報酬として全額経費計上)と仮定します。
- 法人の税金は、赤字でも発生する法人住民税の均等割(年間約7万円)のみを計上します。
所得500万円の場合の税金シミュレーション
まずは、事業所得が500万円の個人事業主をモデルに比較してみましょう。
フリーランスとして安定した収入が得られるようになった方が、最初に法人化を検討するラインです。
個人事業主の場合
事業所得500万円をすべて個人事業主として得た場合の税金と社会保険料を計算します。
国民健康保険料は所得に応じて高額になる傾向があります。
| 項目 | 計算式・備考 | 金額(年額) |
|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 令和6年度の金額 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 所得に応じて算出(東京都新宿区の料率で計算) | 約51万円 |
| 所得税 | 課税所得(500-65-48-71)×10%-9.75万円 | 約22万円 |
| 住民税 | 課税所得(500-65-43-71)×10% | 約32万円 |
| 個人事業税 | (500-290)×5% | 約11万円 |
| 負担合計額 | 社会保険料+各種税金 | 約136万円 |
| 手取り額 | 500万円 – 136万円 | 約364万円 |
マイクロ法人の場合
所得500万円のうち、54万円をマイクロ法人からの役員報酬、残りの446万円を個人事業の所得として得た場合(二刀流)のシミュレーションです。
社会保険はマイクロ法人で加入します。
| 項目 | 計算式・備考 | 金額(年額) |
|---|---|---|
| 社会保険料(健康保険・厚生年金) | 標準報酬月額63,000円で計算(本人負担分) | 約16万円 |
| 法人住民税(均等割) | 資本金1,000万円以下、従業員50人以下の場合 | 約7万円 |
| 所得税 | 課税所得(事業446-65+給与0-48-16)×10%-9.75万円 | 約22万円 |
| 住民税 | 課税所得(事業446-65+給与0-43-16)×10% | 約32万円 |
| 個人事業税 | (446-290)×5% | 約8万円 |
| 負担合計額 | 社会保険料+法人税+個人の税金 | 約85万円 |
| 手取り額 | 500万円 – 85万円 | 約415万円 |
比較結果
所得500万円の場合、両者の負担額と手取り額を比較すると、その差は歴然です。
| 個人事業主 | マイクロ法人設立 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 負担合計額 | 約136万円 | 約85万円 | 年間約51万円の差 |
| 手取り額 | 約364万円 | 約415万円 |
マイクロ法人を設立することで、年間約51万円も手取り額が増えるという結果になりました。
この差額の最も大きな要因は、国民健康保険料から協会けんぽの健康保険料に切り替わることによる社会保険料の削減です。
所得500万円の段階でも、マイクロ法人設立のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
所得800万円の場合の税金シミュレーション
次に、事業所得が800万円に増えた場合で比較します。
所得が増えると、個人事業主の場合は所得税の累進課税や社会保険料の負担がさらに重くなります。
マイクロ法人による節税効果がより顕著に現れる価格帯です。
個人事業主の場合
事業所得800万円をすべて個人事業主として得た場合です。
所得税率は20%が適用され、税負担が一気に増加します。
| 項目 | 計算式・備考 | 金額(年額) |
|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 令和6年度の金額 | 約20万円 |
| 国民健康保険料 | 所得に応じて算出(上限に近い金額) | 約87万円 |
| 所得税 | 課税所得(800-65-48-107)×20%-42.75万円 | 約75万円 |
| 住民税 | 課税所得(800-65-43-107)×10% | 約59万円 |
| 個人事業税 | (800-290)×5% | 約26万円 |
| 負担合計額 | 社会保険料+各種税金 | 約267万円 |
| 手取り額 | 800万円 – 267万円 | 約533万円 |
マイクロ法人の場合
所得800万円のうち、54万円をマイクロ法人からの役員報酬、残りの746万円を個人事業の所得として得た場合のシミュレーションです。
社会保険料の負担は所得500万円のケースと変わりません。
| 項目 | 計算式・備考 | 金額(年額) |
|---|---|---|
| 社会保険料(健康保険・厚生年金) | 標準報酬月額63,000円で計算(本人負担分) | 約16万円 |
| 法人住民税(均等割) | 資本金1,000万円以下、従業員50人以下の場合 | 約7万円 |
| 所得税 | 課税所得(事業746-65+給与0-48-16)×20%-42.75万円 | 約81万円 |
| 住民税 | 課税所得(事業746-65+給与0-43-16)×10% | 約62万円 |
| 個人事業税 | (746-290)×5% | 約23万円 |
| 負担合計額 | 社会保険料+法人税+個人の税金 | 約189万円 |
| 手取り額 | 800万円 – 189万円 | 約611万円 |
比較結果
所得800万円の場合、節税効果はさらに拡大します。
| 個人事業主 | マイクロ法人設立 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 負担合計額 | 約267万円 | 約189万円 | 年間約78万円の差 |
| 手取り額 | 約533万円 | 約611万円 |
所得800万円のケースでは、マイクロ法人を設立することで年間の手取り額が約78万円も増加するという結果になりました。
所得が高くなればなるほど、国民健康保険料の負担や累進課税による所得税・住民税の負担が重くなるため、社会保険料を固定化できるマイクロ法人のメリットがより一層際立ちます。
これらのシミュレーションからわかるように、事業所得が一定額を超えている場合、マイクロ法人を設立して社会保険料と税金の負担を最適化することは、手取り額を最大化するための極めて有効な手段であると言えます。
税金だけじゃない!マイクロ法人を設立するメリット・デメリット
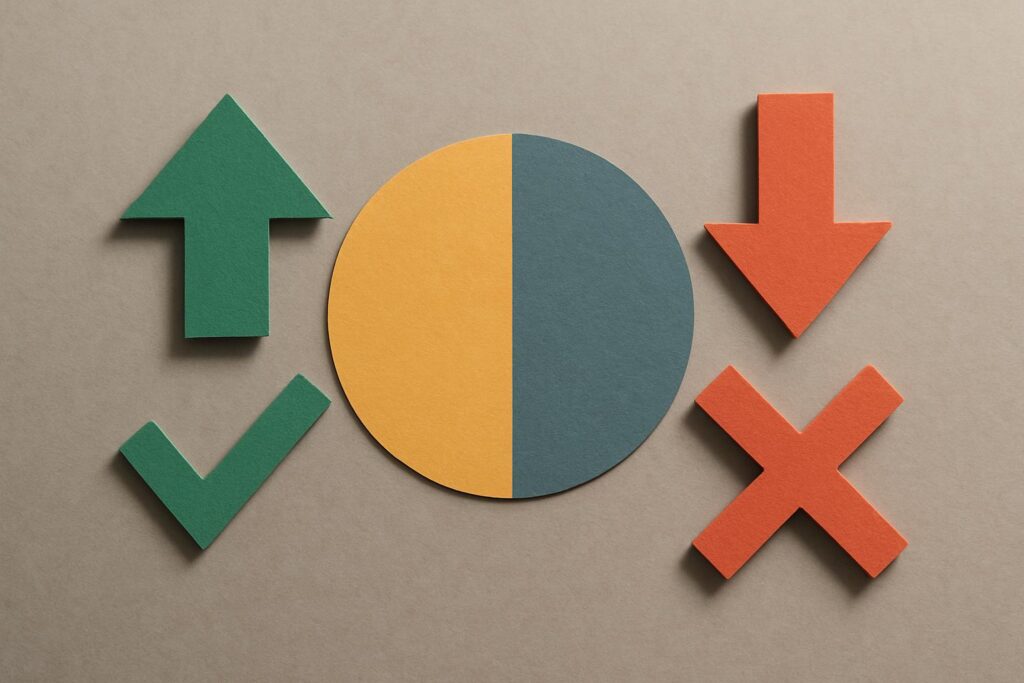
シミュレーションで税金や社会保険料の負担が軽くなることが分かると、すぐにでもマイクロ法人を設立したくなるかもしれません。
しかし、法人化は税金面だけでなく、事業運営のあらゆる側面に影響を及ぼします。
メリットだけでなく、デメリットや注意点も総合的に理解した上で、ご自身の状況に最適な選択をすることが重要です。
ここでは、税金以外の側面も含めたマイクロ法人のメリット・デメリットを詳しく解説します。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人を設立することで得られる主なメリットは、税金や社会保険料の最適化に留まりません。
事業の成長や個人のライフプランにも関わる、4つの大きなメリットをご紹介します。
社会保険料を最適化できる
マイクロ法人設立の最大のメリットと言っても過言ではないのが、社会保険料の最適化です。
個人事業主が加入する国民健康保険料は前年の所得に応じて決まり、所得が増えるほど保険料も高くなります(上限額は自治体により設定)。
一方、法人の役員は健康保険・厚生年金に加入します。
こちらの保険料は、法人から受け取る役員報酬の額(標準報酬月額)に基づいて算出されます。
そのため、マイクロ法人からの役員報酬を社会保険料が最低限になる金額に設定し、残りの利益は個人事業主として得ることで、社会保険料の負担を大幅にコントロールできるのです。
厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が国民年金のみの場合より手厚くなるという利点もあります。
経費計上できる範囲が広がる
法人化すると、個人事業主では経費として認められにくい費用も、法人の経費(損金)として計上できる可能性が広がります。
これにより、課税対象となる所得を圧縮し、結果的に法人税の節税につながります。
- 役員社宅:法人が賃貸契約した物件を役員に貸し出す「社宅」として扱うことで、家賃の大部分を法人の経費にできます。個人事業主の家事按分よりも、経費にできる割合が高くなるケースが一般的です。
- 生命保険料:法人名義で生命保険に加入し、保険の種類や契約形態によっては、支払う保険料の全額または一部を損金として算入できます。個人の生命保険料控除と比べて、節税効果が大きくなる可能性があります。
- 出張手当(日当):出張旅費規程を整備すれば、出張の際に役員へ日当を支給できます。受け取った役員側では所得税がかからず、法人側では経費として計上できるため、双方にメリットがあります。
- 退職金:役員退職金を準備し、将来支給する際に損金として計上できます。退職金は受け取る側(役員)にとっても、他の所得に比べて税制上大きく優遇されている「退職所得控除」が適用されるため、非常に有利な制度です。
所得分散による節税効果
個人事業主の場合、事業で得た利益はすべて事業主個人の所得となり、所得税の累進課税が適用されます。
所得が高くなるほど税率も上がっていく仕組みです。
マイクロ法人を設立すると、利益を「法人の利益」と「役員報酬(個人の給与所得)」に分散できます。
法人税率が適用される部分と、所得税率が適用される部分を戦略的に分けることで、トータルの税負担を最も低く抑えるポイントを探ることが可能になります。
例えば、個人の所得税率が高くなるラインの手前までを役員報酬とし、残りは法人に利益として残すといった調整が考えられます。
また、配偶者などを役員にして役員報酬を支払えば、世帯単位での所得分散も可能です。
社会的信用度の向上
「個人事業主」と「法人(株式会社や合同会社)」では、対外的な信用度に差が出ることがあります。
法人格を持つことで、以下のようなメリットが期待できます。
- 取引先の拡大:企業によっては、与信管理の観点から法人でなければ取引しないという方針を掲げている場合があります。法人化することで、ビジネスチャンスが広がる可能性があります。
- 資金調達:金融機関から融資を受ける際、一般的に個人事業主よりも法人の方が審査で有利に進む傾向があります。事業計画や財務状況が明確に示せるためです。
- 人材採用:求人募集を行う際にも、社会保険が完備されている法人の方が、応募者にとって安心感があり、優秀な人材を確保しやすくなります。
マイクロ法人のデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、マイクロ法人には無視できないデメリットや、運営上の注意点が存在します。
これらのコストや手間を十分に理解しておくことが、設立後の後悔を防ぐ鍵となります。
法人設立と維持にコストがかかる
法人を設立し、維持していくためには、個人事業主にはないコストが発生します。
これらの費用を上回る節税メリットが見込めるかどうかが、設立判断の重要なポイントです。
| 費用の種類 | 内容と目安 |
|---|---|
| 設立費用 | 株式会社で約20万円~、合同会社で約6万円~の法定費用(登録免許税、定款認証手数料など)が必要です。司法書士などに手続きを依頼する場合は、別途手数料がかかります。 |
| 維持費用 | 税理士費用:決算申告や日々の経理を依頼する場合、顧問料や決算料として年間20万円~50万円程度が相場です。法人住民税(均等割):後述の通り、赤字でも最低年間約7万円が発生します。社会保険料の会社負担分:役員報酬に応じた社会保険料の約半分を法人が負担します。その他:会計ソフトの利用料、法務局への役員変更登記費用(任期ごと)などが発生します。 |
赤字でも法人住民税の均等割が発生する
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税はかかりません。
しかし、法人の場合は、たとえ事業が赤字であっても納税義務が発生する税金があります。
それが「法人住民税の均等割」です。
これは、法人が事業所を置く地方自治体に対して支払うもので、会社の利益(所得)に関係なく、資本金の額や従業員数に応じて課税されます。税額は自治体によって異なりますが、最も小規模な法人でも最低年間7万円程度の負担は覚悟しておく必要があります。
これは法人である限り、毎年必ず発生する固定コストです。
会計処理や事務手続きが煩雑になる
個人事業主の確定申告と比べて、法人の会計処理や税務申告は格段に複雑で、専門的な知識が求められます。主な事務負担は以下の通りです。
- 厳格な経理処理:日々の取引を複式簿記で正確に記帳し、領収書や請求書などの証憑書類を適切に管理する必要があります。プライベートな支出と法人の経費を明確に区別しなければなりません。
- 複雑な決算申告:年に一度の決算では、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表に加え、法人税申告書や勘定科目内訳明細書など、多数の書類を作成して税務署に提出する必要があります。
- 社会保険の手続き:役員報酬を決定・変更した際の手続き(算定基礎届、月額変更届)や、労働保険の年度更新など、年金事務所や労働基準監督署への各種手続きが定期的に発生します。
これらの手続きをすべて自分で行うのは非常に困難なため、多くのマイクロ法人が税理士と顧問契約を結んでいます。
その費用も維持コストとして見込んでおく必要があります。
役員報酬を自由に変更できない
個人事業主は、事業で得た利益をいつでも好きな時に引き出して生活費などに充てることができます。
しかし、法人の役員になると、そうはいきません。
法人の経費として認められる役員報酬には、「定期同額給与」という厳しいルールがあります。
これは、原則として、事業年度開始から3ヶ月以内に決定した金額を、その事業年度が終わるまで毎月同じ額で支払い続けなければならないというものです。
年の途中で「今月は利益がたくさん出たから報酬を増やそう」「今月は厳しいから減らそう」といった柔軟な変更はできません。
もし変更した場合、経費として認められない(損金不算入となる)ペナルティが課され、余計な法人税を支払うことになりかねません。
このため、1年間の事業計画を慎重に見通した上で、役員報酬額を決定する必要があります。
マイクロ法人設立による節税効果が高い人の特徴

マイクロ法人は、誰が設立しても必ず税金が安くなるという魔法の杖ではありません。
個人の所得状況や事業内容によって、その節税効果は大きく変わります。
ここでは、どのような人がマイクロ法人を設立することで、税金や社会保険料の負担を軽減できる可能性が高いのか、具体的な特徴を3つのパターンに分けて詳しく解説します。
事業所得が一定以上ある個人事業主
現在、個人事業主として活動しており、事業所得(売上から経費を差し引いた利益)が年々増加している方は、マイクロ法人設立による節税効果を最も受けやすいタイプと言えます。
その最大の理由は、個人に課される所得税と、法人に課される法人税の税率構造の違いにあります。
所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されています。
一方、法人税は所得金額にかかわらず税率がほぼ一定です(中小法人の場合)。
以下の表で、所得税と法人税の税率を比較してみましょう。
| 課税所得金額 | 所得税率(参考) | 法人税率(中小法人の場合) |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 年800万円以下の部分:15% 年800万円超の部分:23.2% |
| 195万円超〜330万円 | 10% | |
| 330万円超〜695万円 | 20% | |
| 695万円超〜900万円 | 23% | |
| 900万円超〜1,800万円 | 33% | 年800万円超の部分:23.2% |
※所得税率は復興特別所得税を考慮していません。住民税は約10%が別途かかります。
※法人税率は2024年4月1日以後に開始する事業年度のものです。法人住民税・事業税が別途かかります。
この表からもわかるように、個人の課税所得が900万円を超えると所得税率は33%(住民税と合わせると約43%)に達します。
一方で、法人税の実効税率は所得800万円超の部分でもおおよそ30%台前半です。
一般的に、課税所得が800万円から900万円を超えるあたりが、個人事業主の税負担が法人の税負担を上回る分岐点とされています。
また、税金だけでなく社会保険料の観点も重要です。
個人事業主が加入する国民健康保険料は所得に応じて増加し、上限額も比較的高く設定されています。
しかし、マイクロ法人を設立して役員報酬を低く設定すれば、その報酬額に応じた厚生年金・健康保険料に抑えることが可能です。
この社会保険料の最適化が、マイクロ法人設立の大きなメリットとなります。
副業収入がある会社員
本業で会社員として給与を得ながら、副業でまとまった収入がある方も、マイクロ法人設立のメリットを享受できる可能性が高いです。
会社員の場合、副業で得た所得(事業所得または雑所得)は、本業の給与所得と合算して所得税が計算されます(総合課税)。
給与所得である程度の収入があるため、そこに副業所得が上乗せされると、高い所得税率が適用されがちです。
そこで、副業部分をマイクロ法人化し、収入を法人の売上として計上します。
そして、自分への役員報酬を低額(例えば月5万円など)に設定し、残りの利益は法人に残しておきます。
これにより、個人の所得と法人の所得に分散させ、個人に適用される高い所得税率を回避することができます。
社会保険料についてもメリットがあります。本業の会社で既に健康保険・厚生年金に加入しているため、マイクロ法人からの役員報酬を社会保険の加入義務が発生しない範囲に設定すれば、社会保険料の負担を増やすことなく法人を運営できます。
法人に残した利益は、将来の退職金として受け取るなど、出口戦略を考えることでさらなる節税につながります。
特に、Webライター、デザイナー、プログラマー、コンサルタントなど、大きな設備投資を必要とせず、利益率の高い副業を行っている会社員にとって、マイクロ法人は非常に有効な選択肢となるでしょう。
消費税の課税事業者になっている
個人事業主として、すでに消費税の課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円超、またはインボイス制度登録事業者)になっている場合も、マイクロ法人の設立が節税につながるケースがあります。
個人事業主が課税事業者であっても、新しく設立した法人は、資本金1,000万円未満などの要件を満たせば、原則として設立から最大2年間は消費税の納税が免除される「免税事業者」となります。
この仕組みを利用し、例えば個人事業で行っている事業の一部をマイクロ法人に移管することで、法人分の売上にかかる消費税の納税を免れることができます。
個人事業主として受け取った消費税をそのまま納税するのに比べ、手元に残る資金を増やす効果が期待できます。
ただし、2023年10月から開始されたインボイス制度には注意が必要です。
取引先が法人や課税事業者であり、適格請求書(インボイス)の発行を求められる場合、免税事業者のままでは取引に支障が出る可能性があります。
インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があり、その場合は消費税免除のメリットを享受できません。
そのため、この方法は、BtoC(一般消費者向け)の事業を行っている方や、取引先が免税事業者でも問題ない場合に特に有効な手法となります。
マイクロ法人の税金に関するよくある質問

マイクロ法人を設立するにあたって、多くの方が抱く税金や手続きに関する疑問について、Q&A形式で詳しく解説します。
特に質問の多い「扶養」「役員報酬」「税理士への依頼」について、具体的なポイントを押さえていきましょう。
扶養に入ったままマイクロ法人を設立できますか?
結論から言うと、「税制上の扶養」は可能ですが、「社会保険上の扶養」は原則として外れることになります。
この2つの「扶養」は全く別の制度であり、それぞれ条件が異なるため、分けて考える必要があります。
税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
税制上の扶養は、ご自身の合計所得金額によって決まります。
配偶者の扶養に入る(配偶者控除の対象となる)ためには、あなたの年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
マイクロ法人から受け取る役員報酬は「給与所得」に分類されます。
給与所得には最低55万円の給与所得控除があるため、年間の役員報酬が103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)以下であれば、所得税はかからず、配偶者は配偶者控除を受けることができます。
つまり、役員報酬の金額を調整することで、税制上の扶養を維持することは可能です。
社会保険上の扶養(健康保険・厚生年金)
問題となるのが社会保険上の扶養です。法人を設立すると、その法人は社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所となります。
そして、法人の代表者(社長)は、たとえ役員報酬がゼロであっても社会保険の被保険者となる義務があります。
そのため、マイクロ法人を設立して代表取締役に就任した時点で、配偶者が加入している健康保険組合などの扶養から外れ、ご自身のマイクロ法人で社会保険に加入しなければなりません。
たとえ役員報酬を低く設定しても、最低等級の保険料負担が発生します。
「非常勤役員」として扱われれば加入義務がないケースもありますが、法人の代表者として事業の実務を行っている場合、非常勤と認められるのは極めて困難です。
マイクロ法人設立を検討する際は、この社会保険料の負担増を必ず念頭に置いておく必要があります。
マイクロ法人の役員報酬はいくらに設定すべきですか?
マイクロ法人の節税効果を最大化するための役員報酬設定は、非常に重要なポイントです。
これは「個人の税金・社会保険料」と「法人の税金」のバランスを取る作業であり、最適な金額は個人の所得状況によって異なります。
基本戦略は「社会保険料を低く抑え、個人と法人のトータルの税負担が最も軽くなる金額」を見つけることです。
一般的に、個人事業の所得があることを前提としたマイクロ法人では、役員報酬を社会保険料が最も低くなる金額帯に設定するケースが多く見られます。
具体的には、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の最低等級である「63,000円未満」に収まるよう、月額45,000円~60,000円程度に設定することが一つの目安となります。
この金額に設定するメリットと注意点は以下の通りです。
- メリット:個人の社会保険料負担を最小限に抑えることができます。また、役員報酬を低くすることで個人の所得税・住民税の負担も軽くなり、利益を法人に残すことで、個人の高い所得税率ではなく、低い法人税率の適用を受けられます。
- 注意点:役員報酬は、事業年度開始から3ヶ月以内に決定する必要があり、その事業年度中は原則として変更できません(定期同額給与)。また、将来受け取る厚生年金の額は、支払った保険料(標準報酬月額)に応じて決まるため、報酬を低く設定すると年金額も少なくなります。
ご自身の個人事業での所得や生活費などを総合的に考慮し、税理士などの専門家と相談しながら、最適な役員報酬額をシミュレーションすることが重要です。
税理士に依頼する必要はありますか?費用はいくらですか?
個人事業主の確定申告をご自身で行ってきた方でも、法人の決算・申告手続きは格段に複雑になるため、税理士への依頼を強く推奨します。
法人の申告書は、損益計算書や貸借対照表のほかに、「勘定科目内訳明細書」や「法人事業概況説明書」など、作成すべき書類が数十種類に及びます。
これらの書類を正確に作成するには専門的な知識が不可欠であり、申告ミスがあった場合、加算税や延滞税といったペナルティが課されるリスクがあります。
税理士に依頼することで、煩雑な経理・税務処理から解放され、本業に集中できるという大きなメリットがあります。
また、最新の税制に基づいた的確な節税アドバイスを受けられる点も魅力です。
税理士への依頼費用(相場)
税理士に依頼する際の費用は、依頼する業務の範囲によって大きく異なります。
以下に一般的な費用相場をまとめました。
| 依頼内容 | 費用相場(年間) | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 決算申告のみ | 10万円~20万円程度 | 年間の会計データをもとに、決算書の作成と法人税申告書の作成・提出を行う。日々の記帳は自分で行うことが前提。 |
| 記帳代行+決算申告 | 20万円~40万円程度 | 領収書や請求書、通帳のコピーなどを渡し、日々の会計帳簿の作成(記帳)から決算申告までをすべて依頼する。 |
| 税務顧問契約 | 30万円~60万円程度 | 記帳代行や決算申告に加え、月次での業績報告や節税対策、融資相談、税務調査対応など、年間を通じた継続的なサポートを受ける。 |
マイクロ法人の場合、事業規模が小さく取引もシンプルなため、比較的安価な料金プランで対応してくれる税理士事務所も多くあります。
複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。
まとめ
マイクロ法人を設立すると、個人事業主と比較して税金や社会保険料の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
特に、役員報酬を低く設定することで社会保険料を最適化できる点が最大のメリットです。
ただし、法人設立・維持コストや赤字でも発生する法人住民税均等割などのデメリットも存在します。
本記事のシミュレーションを参考に、ご自身の所得状況でメリットが上回るかを慎重に見極め、税理士などの専門家への相談も検討しましょう。