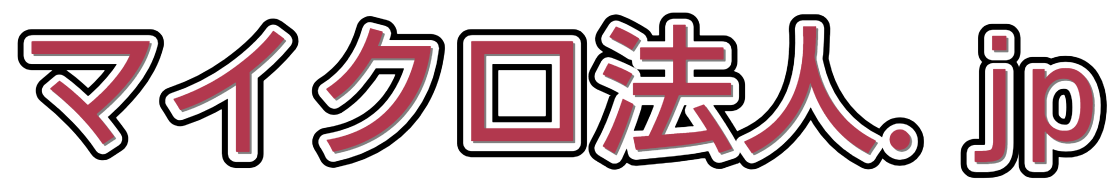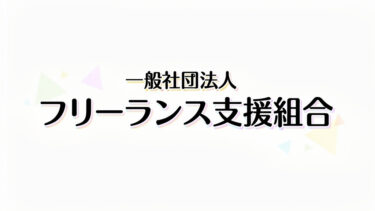マイクロ法人の設立で法人税はいくらになるか、どうすれば節税できるかお悩みではありませんか?
本記事では、法人税の計算方法から、役員報酬の活用といった具体的な節税策、個人事業主との税負担比較まで、図解やシミュレーションを交えて解説します。
マイクロ法人は税負担を大きく軽減できる可能性がある一方、社会保険料などの注意点も。
この記事を読めば、法人化で有利になる所得の目安がわかり、ご自身の最適な選択ができます。
マイクロ法人とは? 個人事業主との違いを解説
近年、個人事業主やフリーランスの間で「マイクロ法人」という働き方が注目されています。
特に、税金や社会保険料の負担を最適化できる可能性があることから、法人成り(法人化)を検討する際の有力な選択肢となっています。
しかし、「マイクロ法人」という言葉はよく聞くものの、具体的にどのようなものなのか、個人事業主と何が違うのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。
この章では、後続の法人税に関する解説を深く理解するための前提知識として、マイクロ法人の基本的な定義と、個人事業主との違いを分かりやすく解説します。
マイクロ法人に明確な定義はない
まず押さえておきたい重要な点は、「マイクロ法人」という言葉は、会社法などの法律で定められた法人格ではないということです。
一般的に、社長一人、あるいは配偶者や親族などごく少人数の役員のみで運営される、事業規模の小さな会社(法人)を指す通称として使われています。
多くの場合、設立される法人の形態は「株式会社」または「合同会社」です。個人事業主が事業を拡大するためではなく、主に節税や社会保険料の最適化を目的として設立する、いわゆる「プライベートカンパニー」がこれにあたります。
個人事業主との違いを比較
では、マイクロ法人(小規模な会社)は個人事業主と具体的に何が違うのでしょうか。
両者の違いを理解することが、マイクロ法人を設立するメリット・デメリットを判断する上で不可欠です。
主な違いを表にまとめました。
| 比較項目 | マイクロ法人(株式会社・合同会社) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 税金の種類 | 法人税、法人住民税、法人事業税など | 所得税、住民税、個人事業税など |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金(強制加入) | 国民健康保険・国民年金 |
| 経費の範囲 | 役員報酬、退職金、生命保険料など経費にできる範囲が広い | 事業に関連する費用のみ |
| 社会的信用 | 一般的に高い | 法人に比べると低い傾向 |
| 設立・維持コスト | 設立費用(数万円~数十万円)と維持コスト(赤字でも法人住民税の均等割が発生)がかかる | 開業届の提出のみで、原則コストはかからない |
| 赤字の繰越 | 最大10年間(欠損金の繰越控除) | 最大3年間(純損失の繰越控除) |
| 責任の範囲 | 有限責任(出資額の範囲内) | 無限責任(全財産が対象) |
上の表からもわかるように、マイクロ法人と個人事業主には多くの違いがあります。
特に重要なのが「税金」と「社会保険」です。
個人事業主の所得にかかる「所得税」は、所得が増えるほど税率が上がる「累進課税(5%~45%)」です。
一方、法人の所得にかかる「法人税」は、資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円以下の部分には軽減税率が適用されるなど、一定の所得を超えると個人事業主より税率が低くなる傾向があります。
また、マイクロ法人を設立する最大の動機の一つが社会保険料の最適化です。
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しますが、所得に応じて保険料が変動する国民健康保険は、所得が高いと負担が大きくなります。一方、マイクロ法人を設立すれば、役員として健康保険と厚生年金に加入することになります。
役員報酬の額を調整することで、社会保険料の負担を個人事業主の時よりも抑えられる可能性があるのです。
さらに、厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が手厚くなるというメリットもあります。
このように、マイクロ法人は個人事業主と比較して、設立や維持に手間とコストがかかるものの、税金や社会保険の面で大きなメリットを享受できる可能性があります。
どの程度の所得があれば法人化が有利になるのか、どのような節税策が有効なのかを正しく理解し、ご自身の事業規模やライフプランと照らし合わせて慎重に検討することが重要です。
マイクロ法人の法人税はいくら?税率と仕組みを理解しよう

マイクロ法人を設立する最大の目的の一つが「節税」です。
特に、個人事業主の所得税と比較して、法人税の税率構造が有利に働くケースが多くあります。
では、具体的にマイクロ法人の法人税はいくらになるのでしょうか?
ここでは、法人税の基本的な仕組みと、マイクロ法人に適用される税率について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
法人税額を決定する「税率」と「課税所得」という2つの重要な要素を理解することが、節税への第一歩です。
法人税の税率(中小法人の軽減税率)
法人税の税率は、法人の種類や資本金の額、所得金額によって異なります。
マイクロ法人のように、資本金が1億円以下の法人は「中小法人」に分類され、税制上の優遇措置である「法人税の軽減税率」が適用されます。
この軽減税率こそが、マイクロ法人の大きな節税メリットの源泉です。
具体的には、年間の所得金額のうち800万円以下の部分について、本則の税率よりも低い税率が適用されるのです。
現在の法人税率は以下の通りです。
| 所得金額 | 税率(軽減税率適用後) | 備考(本則税率) |
|---|---|---|
| 年800万円以下の部分 | 15% | 19% |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | 23.2% |
※この軽減税率は租税特別措置法によるもので、適用期限が定められていますが、これまで延長が繰り返されています。
最新の情報は国税庁のウェブサイトでご確認ください。
ご覧の通り、所得が年800万円までであれば、法人税率はわずか15%に抑えられます。
個人事業主の場合、所得が増えるほど税率が上がる累進課税(最大45%)が適用されるため、この違いが税負担の大きな差となって現れます。
法人税の課税対象となる所得とは
法人税率が分かったところで、次に重要になるのが「何に対して税金がかかるのか」という点です。
法人税は、法人の「課税所得」に対して課税されます。
ここで注意したいのが、会計上の「利益(売上-経費)」と、税法上の「所得」は必ずしも一致しないという点です。
法人は決算で会計上の利益(税引前当期純利益)を計算しますが、法人税の申告では、その利益を元に税法独自のルールに基づいて調整を行います。
この調整を経て算出された金額が「課税所得」となります。
この税法上の調整で使われるのが「益金(えききん)」と「損金(そんきん)」という考え方です。
- 益金:法人税法上の収益のこと。会計上の「収益」とほぼ同じですが、受取配当金の一部が益金に算入されない(益金不算入)など、一部違いがあります。
- 損金:法人税法上の費用のこと。会計上の「費用」とほぼ同じですが、役員への賞与や過大な役員報酬、一定額を超える交際費などが損金に算入されない(損金不算入)といったルールがあります。
つまり、法人税の計算式は以下のようになります。
◆ 法人税額 = 課税所得(益金の額 - 損金の額) × 法人税率
マイクロ法人を運営する上では、支払った経費がすべて「損金」として認められるわけではないことを理解しておくことが非常に重要です。
例えば、社長一人だけのマイクロ法人であっても、役員報酬の金額設定ルールや、自宅兼事務所の家賃按分など、損金算入には一定の要件があります。
これらのルールを正しく理解し、適切に会計処理・税務申告を行うことが、確実な節税につながります。
法人税だけじゃない マイクロ法人が支払う税金の種類

マイクロ法人を設立すると、利益に対して課される法人税の他に、複数の税金を納める義務が生じます。
これらの税金はそれぞれ課税の仕組みや納税先が異なり、法人の運営コストに直結する重要な要素です。
「法人税さえ払えば良い」というわけではないため、全体像を正しく理解しておくことが不可欠です。
マイクロ法人が支払う主な税金は、国に納める「国税」と、事業所のある都道府県や市町村に納める「地方税」に大別されます。
具体的には以下の税金が挙げられます。
- 法人住民税(地方税)
- 法人事業税(地方税)
- 特別法人事業税(国税)
- 消費税(国税)
ここでは、それぞれの税金がどのような性質を持ち、どのように計算されるのかを詳しく解説します。
法人住民税
法人住民税は、法人が事業所を置く地方自治体(都道府県および市町村)に対して納める地方税です。
これは、法人が地域社会の一員として、そのインフラや行政サービスを利用することに対する応益負担(おうえきふたん)の性質を持っています。
法人住民税は、次の2つの要素から構成されています。
- 法人税割:法人税額に応じて課税される部分
- 均等割:法人の規模(資本金や従業員数)に応じて定額で課税される部分
法人税割は、国に納める法人税の額を計算基礎(課税標準)として、「法人税額 × 税率」で算出されます。
税率は自治体によって異なりますが、標準税率が定められています。
一方で、マイクロ法人が特に注意すべきなのが「均等割」です。
均等割は、法人の所得が赤字であっても、法人が存在する限り必ず支払わなければならない税金です。
資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下のマイクロ法人の場合、多くのケースで最低額である年間合計7万円(都道府県民税2万円+市町村民税5万円)が課されます。
【法人住民税(均等割)の税額例(標準税率)】
| 資本金等の額 | 従業員数 | 都道府県民税 | 市町村民税 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 20,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
| 50人超 | 20,000円 | 120,000円 | 140,000円 | |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 50,000円 | 130,000円 | 180,000円 |
| 50人超 | 50,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
※東京都23区内に事業所がある場合は、都民税として合算して納税します(均等割の最低額は7万円)。
法人事業税
法人事業税は、法人が事業を行うにあたって道路や港湾といった公共サービスを利用することから、その経費の一部を負担するという考え方に基づき、事業所のある都道府県に納める地方税です。
課税対象は、法人税と同様に各事業年度の「所得」となります。
したがって、法人事業税は所得が赤字の年度には原則として課税されません。
この点が、赤字でも発生する法人住民税の均等割との大きな違いです。
税率は、法人の種類や資本金、所得額によって異なります。
資本金1億円以下の普通法人の場合、所得を基準とする「所得割」が適用されます。
多くのマイクロ法人は、軽減税率が適用される「年400万円以下の所得」の区分に該当するでしょう。
【法人事業税(所得割)の税率例(東京都)】
| 所得区分 | 軽減税率適用法人 | 標準税率 |
|---|---|---|
| 年400万円以下の部分 | 3.5% | 7.0% |
| 年400万円超~800万円以下の部分 | 5.3% | |
| 年800万円超の部分 | 7.0% |
※軽減税率が適用されるのは、資本金1億円以下かつ所得年1,000万円以下などの条件を満たす法人です。税率は自治体によって異なる場合があります。
特別法人事業税
特別法人事業税は、2019年の税制改正で創設された「国税」です。
名称に「事業税」とありますが、納税先は国である点に注意が必要です。
この税金は、地域間の税源の偏りを是正する目的で導入されました。
計算方法は非常にシンプルで、法人事業税(所得割)の額を基準にして算出されます。
◆ 計算式:基準法人所得割額(法人事業税の所得割額) × 税率 = 特別法人事業税額
税率は資本金や所得に関わらず一律です。
法人事業税が0円であれば、特別法人事業税も0円になります。
申告と納税は、法人事業税とあわせて都道府県に対して行います。
消費税
消費税は、商品やサービスの販売・提供といった取引に対して広く公平に課される国税です(一部は地方消費税として地方の財源となります)。
個人事業主と同様に、法人も条件を満たせば消費税を申告・納税する義務を負う「課税事業者」となります。
設立したばかりのマイクロ法人にとって重要なのが、「納税義務の免除」の制度です。
原則として、資本金1,000万円未満で設立された法人は、設立1期目と2期目は消費税の納税が免除される「免税事業者」となります。
これは、マイクロ法人設立の大きなメリットの一つです。
ただし、以下のいずれかの条件に該当すると、設立当初から課税事業者になるため注意が必要です。
- 資本金が1,000万円以上の場合
- 特定期間(事業年度開始の日から6ヶ月間)の課税売上高と給与支払額のいずれもが1,000万円を超えた場合
また、3期目以降は、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えていると課税事業者になります。
さらに、2023年10月に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も考慮しなければなりません。
取引先からインボイス(適格請求書)の発行を求められた場合、免税事業者であっても、自ら「適格請求書発行事業者」として登録し、課税事業者になることを選択するケースが増えています。
インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があり、その場合は売上規模にかかわらず消費税の申告・納税義務が発生します。
【シミュレーション】マイクロ法人の法人税の計算方法
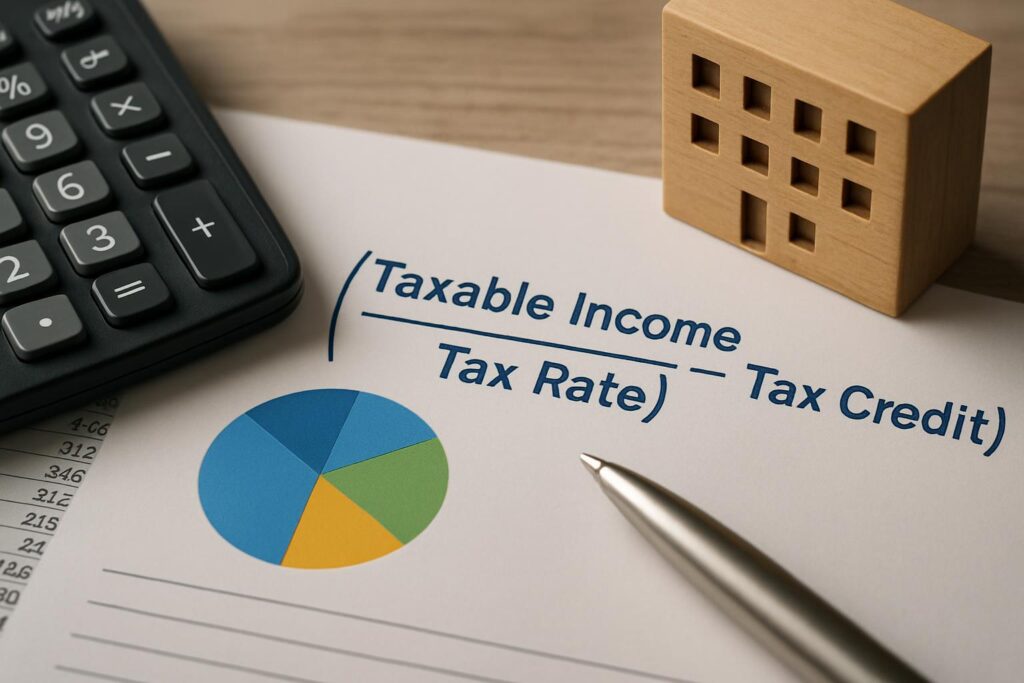
マイクロ法人の法人税が実際にいくらになるのか、具体的な計算方法がわからなければ節税計画も立てられません。
ここでは、法人税の計算式と手順を分かりやすく解説し、具体的な数値を当てはめたシミュレーションをご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、税額のイメージを掴んでみましょう。
法人税の計算式と手順
法人税は、会社の利益である「所得」に対して課税されます。
計算の基本的な流れはシンプルですが、所得を正確に算出するまでにはいくつかのステップが必要です。
まずは、その計算式と手順をしっかり理解しましょう。
法人税額を算出する基本的な計算式は以下の通りです。
◆ 課税所得金額 × 法人税率 − 税額控除額 = 法人税額
この計算式に出てくる「課税所得金額」を求めることが、法人税計算の第一歩となります。
課税所得は、会計上の利益とは異なり、税法に基づいて計算される点に注意が必要です。
具体的な計算手順は以下の通りです。
- 益金の算入
益金とは、法人税法上の収益のことです。主に商品やサービスの売上高、資産の売却益、受取利息などが該当します。会計上の「収益」とほぼ同じですが、一部異なる項目があるため税務調整が必要になる場合があります。 - 損金の算入
損金とは、法人税法上の費用のことです。売上原価、販売費及び一般管理費(役員報酬、給与、地代家賃、広告宣宣伝費など)がこれにあたります。個人事業主と比べて経費として認められる範囲が広いのが法人の特徴です。ただし、役員賞与や交際費の一部など、損金として認められない(損金不算入)項目もあります。 - 所得金額の計算
上記の益金から損金を差し引いて、その事業年度の所得金額を計算します。所得金額 = 益金の額 − 損金の額 - 課税所得の計算
所得金額から、過去の事業年度から繰り越された赤字(繰越欠損金)を差し引きます。この金額が、税率を掛ける基礎となる課税所得です。課税所得 = 所得金額 − 繰越欠損金額 - 法人税額の算出と税額控除
算出した課税所得に法人税率を掛けて法人税額を計算します。その後、適用できる税額控除(賃上げ促進税制など)があれば、その金額を差し引いたものが最終的な納付税額となります。
具体例で見る法人税の計算シミュレーション
それでは、具体的な数値を当てはめて、マイクロ法人の法人税額をシミュレーションしてみましょう。
ここでは、一人社長で事業を運営しているマイクロ法人を想定します。
【シミュレーションの前提条件】
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 法人形態 | 資本金1億円以下の中小法人 |
| 年間売上高(益金) | 1,000万円 |
| 年間経費(損金) | 700万円 |
| 経費の内訳 | 役員報酬:480万円(月額40万円)地代家賃(事務所兼自宅):60万円水道光熱費・通信費:30万円その他経費(仕入、交通費など):130万円 |
| 繰越欠損金 | なし |
| 適用する税額控除 | なし |
【計算ステップ】
- 課税所得の計算
まず、益金から損金を差し引いて課税所得を求めます。1,000万円(益金) − 700万円(損金) = 300万円
この法人の課税所得は300万円となります。 - 法人税額の計算
次に、課税所得に法人税率を掛けます。この法人は中小法人であり、課税所得が年800万円以下です。そのため、所得全額に対して15%の軽減税率が適用されます。300万円(課税所得) × 15%(軽減税率) = 45万円
法人税額は45万円と計算されます。 - 最終的な納付税額
今回のシミュレーションでは税額控除の適用はないため、法人税の納付額は45万円となります。
このように、役員報酬を適切に設定し、経費を漏れなく計上することで、課税所得を圧縮し、法人税額を抑えることが可能です。
もし役員報酬を設定していなければ、課税所得は「1,000万円 – 220万円(役員報酬以外の経費) = 780万円」となり、法人税額は「780万円 × 15% = 117万円」にまで膨らんでしまいます。
役員報酬を損金に算入できることが、法人化における最大の節税メリットの一つであることが、このシミュレーションからもお分かりいただけるでしょう。
ご自身の売上や経費の見込み額を当てはめて計算し、法人化した場合の税負担を具体的に把握することが重要です。
マイクロ法人で法人税を節税する5つの方法

マイクロ法人の設立を検討する最大の動機の一つが「節税」です。
法人化することで、個人事業主では利用できない、あるいは利用しにくい多様な節税スキームを活用できます。
ここでは、法人税負担を効果的に軽減するための代表的な5つの方法を、具体的な活用法や注意点とともに詳しく解説します。
重要なのは、法人税だけでなく、役員個人の所得税や住民税、さらには社会保険料まで含めたトータルコストで最適化を図る視点です。
これらの方法を組み合わせ、ご自身の事業規模や利益状況に合った最適な節税策を構築しましょう。
役員報酬を設定して所得を分散する
マイクロ法人の節税において、最も基本的かつ効果的な方法が「役員報酬の設定」です。
法人の利益を役員個人への給与(役員報酬)として支払うことで、法人と個人の間で所得を分散し、トータルの税負担を軽減します。
法人の利益にかかる法人税は、中小法人の場合、所得800万円以下の部分には15%の軽減税率が適用されます。
一方、個人の所得税は超過累進課税であり、所得が高くなるほど税率も上がります(住民税と合わせると最大55%)。
役員報酬は法人の経費(損金)として扱われるため、役員報酬を支払った分だけ法人の所得を圧縮でき、法人税を減らすことができます。
受け取った個人側では、給与所得として扱われ、「給与所得控除」という一種の経費が認められます。
これは、実際の経費の有無にかかわらず一定額が所得から差し引かれるため、個人事業主の事業所得がそのまま課税対象となるのに比べて有利な点です。
最適な役員報酬額は、法人に残す利益と個人の所得にかかる税率、そして社会保険料のバランスを総合的に見て決定することが最も重要です。
高すぎれば個人の税負担と社会保険料が重くなり、低すぎれば法人税の負担が大きくなります。
シミュレーションを重ねて、法人と個人の手取りが最大化されるポイントを見つけることが節税の鍵となります。
ただし、役員報酬を設定する際には以下の点に注意が必要です。
- 定期同額給与の原則:役員報酬は、原則として事業年度の開始から3ヶ月以内に決定し、その事業年度中は毎月同額を支給し続けなければ損金として認められません。期中に自由に変更することはできません。
- 社会保険料の負担:役員報酬を支払うと、法人と個人それぞれで社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の負担が発生します。この負担額も考慮して報酬額を決める必要があります。
- 不相当に高額な役員報酬:事業規模や利益状況、他の従業員の給与などと比べて不相当に高額な役員報酬は、税務調査で否認され、損金として認められないリスクがあります。
経費にできる範囲を最大限活用する
法人化することで、個人事業主時代には経費計上が難しかった支出も、法人の経費(損金)として認められる範囲が広がります。
これにより課税所得を圧縮し、法人税を節税することが可能です。
ここでは特に活用しやすい2つの例を紹介します。
家賃や水道光熱費を経費にする
自宅を事務所として利用している場合(自宅兼事務所)、その家賃や水道光熱費の一部を経費にできます。
個人事業主の場合は、事業で使っている面積や時間など、合理的な基準で「家事按分」して経費を算出します。
一方、マイクロ法人では「社宅制度」を活用することで、より有利に経費化できる可能性があります。
具体的には、法人がオーナーと賃貸契約を結び、その物件を役員に社宅として貸し出す形式をとります。
役員は法人に対して、国税庁が定める「賃貸料相当額」以上の家賃を支払う必要がありますが、法人が支払う家賃と役員から受け取る家賃の差額分を、法人の経費(地代家賃や福利厚生費)として計上できます。
この「賃貸料相当額」は、個人事業主の家事按分で経費にできる金額よりも役員の負担が少なく、法人の経費にできる金額が大きくなるケースが多いため、節税効果が高くなります。
水道光熱費についても、社宅制度と合わせて法人契約に切り替えることで、事業使用分を経費として明確に計上しやすくなります。
出張手当(日当)を支給する
出張が多い事業の場合、「出張手当(日当)」の制度を設けることで大きな節税効果が期待できます。
出張手当とは、交通費や宿泊費といった実費とは別に、出張中の食事代や細かな雑費を補填するために支給される手当のことです。
この出張手当には、法人側と個人側それぞれに大きなメリットがあります。
| 対象 | メリット |
|---|---|
| 法人側 | 支給した出張手当の全額を「旅費交通費」として損金に算入できるため、法人税の節税につながります。 |
| 受け取る役員・従業員側 | 社会通念上相当と認められる金額であれば、給与とは見なされず所得税・住民税が非課税となります。実質的な手取りが増えることになります。 |
この制度を有効に活用するためには、必ず「出張旅費規程」を事前に作成し、その規程に基づいて運用する必要があります。
規程には、出張の定義、手当の支給対象者、役職ごとの手当の金額などを明記しておきましょう。
また、出張の事実を証明するために、出張報告書などの記録を残しておくことも重要です。
金額が不相当に高額な場合は給与として課税されるリスクがあるため、同業他社の水準などを参考に常識的な範囲で設定しましょう。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入する
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度ですが、強力な節税効果も併せ持っています。
この制度の最大のメリットは、支払った掛金をその全額、法人の損金に算入できる点です。
掛金は月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、年間最大で240万円、総額800万円まで積み立てることができます。
利益が多く出た年度に掛金を増額して支払うことで、課税所得を大きく圧縮し、法人税の支払いを繰り延べることが可能です。
さらに、共済を任意で解約した際には、掛金の納付月数に応じて解約手当金が戻ってきます。
40ヶ月(3年4ヶ月)以上納付すれば、掛金全額(100%)が返還されます。
ただし、重要な注意点として、この解約手当金は受け取った事業年度の「益金(収入)」として課税対象になります。
つまり、本質的には「課税の繰り延べ」であると理解しておく必要があります。
そのため、役員の退職金支払いなど、将来的に大きな損金が発生するタイミングで解約するといった「出口戦略」をあらかじめ考えておくことが、この制度を最大限に活用するポイントです。
赤字の繰越控除を利用する
法人を設立した初年度や、事業が思うようにいかなかった年度には、赤字(税務上の「欠損金」)が発生することがあります。
この赤字を将来の黒字と相殺できる制度が「欠損金の繰越控除」です。
この制度を利用するには、青色申告の承認を受けていることが前提となります。
青色申告法人が、ある事業年度で生じた欠損金を、翌事業年度以降10年間(※)にわたって繰り越し、将来発生した所得(黒字)から差し引くことができます。
例えば、1年目に300万円の欠損金が生じ、2年目に500万円の所得(黒字)が出たとします。
この場合、繰越控除を適用すれば、2年目の課税所得は「500万円 − 300万円 = 200万円」となり、200万円に対してのみ法人税が課税されます。
もしこの制度がなければ、500万円全額が課税対象となってしまいます。
(※)平成30年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金の場合。それ以前に開始した事業年度で生じた欠損金の繰越期間は9年間です。
マイクロ法人であっても、設立費用などで初年度は赤字になるケースは少なくありません。
赤字が出た年度も必ず確定申告を行い、将来の税負担を軽減できるように備えておくことが非常に重要です。
税額控除の制度を活用する
これまで紹介してきた「損金算入」や「所得控除」が課税対象となる所得を減らすのに対し、「税額控除」は、算出された法人税額から直接一定額を差し引くことができる制度です。
納税額そのものを直接減らすため、非常に節税効果が高いのが特徴です。
中小企業向けに様々な税額控除制度が用意されており、マイクロ法人でも要件を満たせば活用できる可能性があります。
代表的なものには以下のような制度があります。
- 賃上げ促進税制:前年度よりも従業員への給与支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税額から控除できる制度です。役員報酬のみのマイクロ法人では適用が難しい場合もありますが、従業員を雇用した際には検討の価値があります。
- 中小企業投資促進税制:特定の機械装置やソフトウェアなどを取得した場合に、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人等の場合)のいずれかを選択適用できる制度です。
- 研究開発税制:製品開発や技術改良などのための試験研究費がある場合に、その費用額に応じて法人税額から一定割合を控除できます。
これらの税額控除制度は、適用要件が非常に細かく定められており、毎年の税制改正で内容が変更されることも頻繁にあります。
利用を検討する際は、必ず最新の情報を国税庁のウェブサイトで確認するか、税理士などの専門家に相談し、自社が適用対象となるかを確認することが不可欠です。
個人事業主とマイクロ法人の税負担を徹底比較

マイクロ法人の設立を検討する上で最も重要な判断基準の一つが、「個人事業主のままでいる場合と比べて、どれだけ税負担を軽減できるのか」という点です。
所得税の累進課税と法人税の比例税率という構造的な違いから、ある所得水準を超えると法人化した方が手残りが多くなる傾向にあります。
しかし、法人には社会保険料の負担や法人住民税の均等割といった特有のコストも発生するため、一概にどちらが有利とは言えません。
ここでは、具体的な所得金額を基にしたシミュレーションを通じて、両者の税金と社会保険料の負担額を比較し、マイクロ法人設立が有利になる所得の目安について詳しく解説します。
所得金額別の税負担シミュレーション
個人事業主とマイクロ法人では、負担する税金や社会保険料の種類と計算方法が大きく異なります。
ここでは、事業で得た利益(所得)が同額だった場合に、最終的な手取り額にどのような差が生まれるのかをシミュレーションしてみましょう。
【シミュレーションの前提条件】
| ・事業形態:ITエンジニア ・所在地:東京都新宿区 ・年齢:40歳未満 ・家族構成:独身、扶養親族なし ・経費:売上から経費を差し引いた後の所得(利益)を基準に比較 ・個人事業主:青色申告65万円控除を適用。国民健康保険・国民年金に加入。 ・マイクロ法人:所得の全額を役員報酬として社長個人に支給。社長は協会けんぽ・厚生年金に加入。赤字は出ないものとする。 ・各種控除:基礎控除、社会保険料控除のみを考慮し、その他の所得控除(生命保険料控除など)は考慮しない。 |
※下記の金額はあくまで簡易的な試算であり、実際の税額や保険料は個々の状況や自治体、年度によって変動します。
| 所得金額(売上-経費) | 個人事業主の年間負担額(目安) | マイクロ法人の年間負担額(目安) | 差額(個人事業主 – マイクロ法人) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約67万円 | 約83万円 | 約 -16万円 |
| 500万円 | 約121万円 | 約128万円 | 約 -7万円 |
| 800万円 | 約226万円 | 約211万円 | 約 +15万円 |
| 1,000万円 | 約311万円 | 約273万円 | 約 +38万円 |
上記のシミュレーションから、所得が低い段階では、社会保険料の負担が重くなるため個人事業主の方が有利な傾向にあります。
国民健康保険料には上限がありますが、厚生年金保険料には上限がない(標準報酬月額に上限はある)ため、役員報酬が高くなるにつれて社会保険料の負担も増え続けます。
しかし、所得が800万円を超えたあたりから状況が逆転し、マイクロ法人の有利性が増してきます。
これは、個人事業主の所得税が累進課税で税率が急激に上がるのに対し、マイクロ法人では役員報酬に給与所得控除が適用されること、そして法人税率が一定であることが大きな要因です。
マイクロ法人が有利になる所得の目安
シミュレーション結果が示すように、マイクロ法人化が税制上有利になるかどうかは、事業の所得金額に大きく左右されます。
一般的に、その損益分岐点となるのは、課税所得が800万円前後から1,000万円に達するあたりと言われています。
なぜこのあたりが分岐点になるのでしょうか。
理由は主に3つあります。
- 所得税率と法人税率の逆転
個人事業主の所得税は、課税所得が695万円を超えると税率が23%、900万円を超えると33%と急激に上昇します。一方、中小法人の法人税率は所得800万円以下の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%と、比較的緩やかに設定されています。この税率の差が、高所得になるほど法人の方が有利になる最大の理由です。 - 給与所得控除の存在
マイクロ法人から自分に役員報酬を支払うと、その報酬額に応じて「給与所得控除」が適用されます。これは、いわばサラリーマンの「みなし経費」のようなもので、税計算の際に所得から差し引くことができます。例えば、年収850万円の場合、195万円もの給与所得控除が受けられます。個人事業主にはこの制度がないため、法人化による非常に大きな節税メリットとなります。 - 社会保険料のコントロール
個人事業主の国民健康保険料は前年の所得に応じて決まり、所得が増えれば保険料も(上限に達するまで)増え続けます。一方、マイクロ法人の場合、役員報酬の額を調整することで社会保険料をある程度コントロールできます。例えば、役員報酬を低めに設定し、利益を法人に残して別の形で活用する(設備投資や退職金の積立など)といった戦略も可能です。
ただし、この「所得800万円」という目安は絶対的なものではありません。
扶養家族の有無、適用できる所得控除の種類、事業内容(個人事業税がかかるか否か)、そして法人設立・維持にかかるコスト(設立費用、税理士報酬、均等割など)を総合的に考慮する必要があります。
ご自身の状況に合わせて、税理士などの専門家と相談しながら、慎重に法人化のタイミングを見極めることが成功の鍵となります。
マイクロ法人の法人税申告と納税の流れ

マイクロ法人を設立すると、事業年度ごとに決算を行い、法人税をはじめとする各種税金の計算と申告、そして納税を行う義務が生じます。
個人事業主の確定申告とは手続きが異なるため、初めての方は戸惑うかもしれません。
しかし、一連の流れを事前に把握しておけば、慌てることなくスムーズに対応できます。
ここでは、法人税の確定申告から納税までの具体的な手順を解説します。
法人税の確定申告の時期と必要書類
法人税の申告と納税には、定められた期限があります。
期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、計画的に準備を進めることが重要です。
申告・納付の期限
法人税の申告と納税の期限は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内と定められています。
例えば、事業年度が4月1日から翌年3月31日までの「3月決算」の法人の場合、申告と納税の期限は5月31日となります。
もし期限が土日祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限となります。
また、定款で定める等の一定の要件を満たせば、「申告期限の延長の特例」を申請することで、申告期限を1ヶ月延長することも可能です。
ただし、この場合でも納税期限は延長されないため、納税は原則通り2ヶ月以内に行う必要がある点に注意しましょう。
申告に必要な主な書類
法人税の申告には、申告書のほか、決算内容を示す様々な添付書類が必要です。
マイクロ法人の場合、主に以下の書類を作成し、税務署へ提出します。
現在はe-Taxによる電子申告が主流となっています。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 法人税申告書 | 別表一から別表十九まであり、法人の所得金額や税額を計算・申告するための中心的な書類です。マイクロ法人では、主に別表一、二、四、五(一)、五(二)、七、十五などを使用します。 |
| 決算報告書 | 法人の財政状態や経営成績を示す書類で、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」などが含まれます。会計ソフトを利用して作成するのが一般的です。 |
| 勘定科目内訳明細書 | 貸借対照表や損益計算書の各勘定科目の残高の内訳を記載した書類です。預貯金や売掛金、役員報酬などの詳細を明らかにします。 |
| 法人事業概況説明書 | 法人の事業内容や業績、従業員数、役員の状況などを記載する書類です。税務署が法人の実態を把握するために用いられます。資本金1億円以上の法人は「会社事業概況書」の提出が必要です。 |
法人税の納税方法
算出された法人税は、申告期限までに納付する必要があります。
納税方法は複数用意されており、法人の都合に合わせて選択できます。
ここでは代表的な納税方法をご紹介します。
| 納税方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子納税) | インターネットを通じて自宅や事務所から納税手続きが完了します。「ダイレクト納付」や「インターネットバンキング」などの方法があります。 | ダイレクト納付を利用するには、事前に税務署への届出が必要です。 |
| クレジットカード納付 | 専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」から納付できます。時間や場所を選ばず、カードのポイントが貯まる場合があります。 | 納税額に応じた決済手数料がかかります。また、納付できる金額には上限(1,000万円未満)があります。 |
| コンビニ納付 | 税務署で発行されたQRコードを使って、コンビニエンスストアの窓口で現金で納付できます。手軽さが魅力です。 | 納付できる金額の上限は30万円までです。 |
| 金融機関・税務署の窓口納付 | 納付書を作成し、銀行や郵便局などの金融機関、または所轄税務署の窓口で現金で納付する従来の方法です。 | 金融機関や税務署の窓口が開いている時間内に行く必要があります。 |
マイクロ法人の場合、納税額がそれほど大きくならないケースも多いため、手数料のかからないe-Taxや、手軽なコンビニ納付などが便利な選択肢となるでしょう。
自社にとって最も利便性の高い方法を選び、期限内に確実に納税を済ませましょう。
マイクロ法人の法人税に関する注意点

マイクロ法人を設立することで、法人税の軽減税率の適用や経費の範囲拡大など、多くの節税メリットが期待できます。
しかし、メリットだけに目を向けて設立を決めると、「こんなはずではなかった」と後悔する可能性も否定できません。法人化には、個人事業主の時にはなかった義務やコストが伴います。
ここでは、マイクロ法人を設立する前に必ず知っておくべき法人税関連の注意点を3つの側面から詳しく解説します。
社会保険料の負担が発生する
マイクロ法人設立における最大の注意点ともいえるのが、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の負担です。
個人事業主が国民健康保険と国民年金に加入するのに対し、法人を設立すると、たとえ社長一人だけのマイクロ法人であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。
社会保険料は、役員報酬の金額に応じて決定され、その保険料を会社と役員個人で半分ずつ負担(労使折半)します。
会社の負担分は「法定福利費」として経費に計上できますが、役員個人の手取り額が減るだけでなく、会社全体のキャッシュアウトは個人事業主時代よりも大幅に増加するケースがほとんどです。
特に、扶養家族がいる場合、個人事業主の国民健康保険料は家族の人数によって増えますが、法人の健康保険は被扶養者の人数にかかわらず保険料は変わりません。
この点はメリットになる可能性もありますが、トータルの負担額を慎重にシミュレーションする必要があります。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人(役員) |
|---|---|---|
| 公的医療保険 | 国民健康保険 | 健康保険(協会けんぽ、組合健保など) |
| 公的年金保険 | 国民年金 | 厚生年金保険(国民年金を含む) |
| 保険料の負担者 | 全額自己負担 | 会社と役員で折半(労使折半) |
| 会社の負担分 | なし | 経費(法定福利費)として計上可能 |
| 扶養の概念 | なし(加入者ごとに保険料が発生) | あり(被扶養者の保険料負担はなし) |
この社会保険料の負担増が、法人税の節税額を上回ってしまう「税金・社会保険料トータルでの手取り逆転現象」が起こり得るため、法人化を検討する際は、税金だけでなく社会保険料を含めた資金繰りを計画することが極めて重要です。
役員報酬をいくらに設定するかが、この負担額をコントロールする鍵となります。
赤字でも法人住民税の均等割はかかる
法人税は、法人の所得(利益)に対して課される税金です。
したがって、事業が赤字であれば法人税額はゼロになります。
しかし、たとえ事業が赤字であっても、法人は「法人住民税の均等割」という税金を納める義務があります。
法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、法人の規模(資本金の額や従業員数)に応じて定額で課税される「均等割」の2つで構成されています。
この均等割は、法人がその地域に存在していること自体に対して課される会費のようなもので、利益の有無にかかわらず発生します。
マイクロ法人の場合、資本金が1,000万円以下、従業員数が50人以下というケースがほとんどでしょう。
この場合、法人住民税の均等割は最低でも年間で合計7万円程度かかります。
- 都道府県民税(均等割):2万円~
- 市町村民税(均等割):5万円~
個人事業主であれば、赤字の場合は所得税・住民税が課されることは基本的にありません。
しかし、マイクロ法人では、利益が出ていなくても毎年最低7万円のコストが発生し続けることを覚えておく必要があります。
これは法人を維持するための固定費と考えるべきです。
設立や維持にコストと手間がかかる
個人事業主が税務署に開業届を提出するだけで事業を始められるのに対し、マイクロ法人の設立には、法律に則った手続きと費用が必要です。
また、設立後も法人を維持していくためのコストと手間がかかり続けます。
設立時のコストと手間
法人の設立には、定款の作成・認証や法務局への登記申請といった専門的な手続きが必要です。
これらの手続きには、以下のような法定費用(実費)がかかります。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 |
| 定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 不要 | 公証役場で支払う手数料 |
| 登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ | 資本金の額によって変動 |
| 合計(電子定款の場合) | 約180,000円~ | 約60,000円~ | – |
これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途手数料が発生します。
維持するためのコストと手間
設立後も、法人を運営していくためには継続的なコストと手間を要します。
- 税務申告の複雑化と税理士費用:法人の税務申告(法人税、消費税など)は、個人事業主の確定申告に比べて格段に複雑です。会計帳簿の作成から申告書の作成まで、専門的な知識が求められるため、多くのマイクロ法人が税理士と顧問契約を結びます。その顧問料や決算申告料として、年間で20万円~40万円程度の費用が発生するのが一般的です。
- 会計処理の手間:法人は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って会計処理を行い、決算書を作成する義務があります。会計ソフトを利用するにしても、日々の記帳には一定の手間がかかります。
- 法務手続き:役員の任期が満了すれば、たとえ同じ人が再任する場合でも役員変更の登記が必要です。登記には登録免許税(1万円)がかかり、司法書士に依頼すればその手数料も必要になります。
これらの設立・維持コストは、法人税の節税メリットと比較衡量すべき重要な要素です。
節税額ばかりに目を奪われず、これらのコストや手間を差し引いても法人化するメリットがあるのかを、総合的に判断することが失敗しないマイクロ法人設立の鍵となります。
まとめ
マイクロ法人は、法人税の軽減税率や役員報酬の活用により、個人事業主よりも税負担を抑えられる可能性があります。
所得が一定額を超えると、所得税の累進課税より法人税のほうが有利になるためです。
ただし、社会保険料の負担増や、赤字でも発生する法人住民税の均等割などの注意点も存在します。
設立を検討する際は、本記事のシミュレーションを参考に、税理士などの専門家へ相談し、ご自身の状況に最適な選択をしましょう。