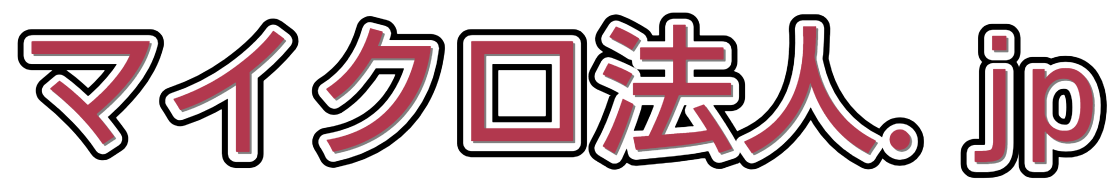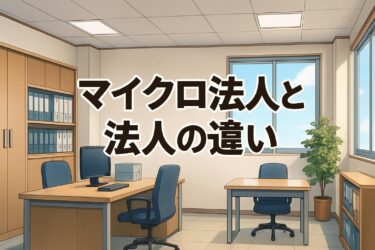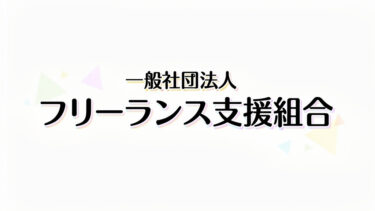マイクロ法人と個人事業主、どちらが自分にとって得なのか迷っていませんか?
この記事では、税金や社会保険料、設立の手間など5つの観点から両者の違いを徹底比較します。
結論として、事業所得が増えると社会保険料の負担を抑えられるマイクロ法人が有利になるケースが多いです。
それぞれのメリット・デメリットから、あなたの状況に合わせた最適な事業形態を選ぶための判断基準まで分かりやすく解説します。
マイクロ法人と個人事業主の基本的な定義
事業を始める際、多くの人が「個人事業主」としてスタートしますが、近年「マイクロ法人」という選択肢も注目されています。
この二つは事業の運営形態として根本的に異なり、税金や社会保険、経費の扱いなど、様々な面で違いがあります。
まずは、それぞれの基本的な定義を正しく理解することから始めましょう。
マイクロ法人とは
「マイクロ法人」という言葉は、実は会社法などの法律で定められた正式な用語ではありません。
一般的に、社長一人、もしくは配偶者や親族といった身内だけで経営する、従業員のいない小規模な法人のことを指す俗称です。
多くの場合、設立費用を抑えられる「合同会社」や、一般的な「株式会社」の形態で設立されます。
最大の特徴は、個人とは別人格である「法人格」を持つ点です。
これにより、事業に関する契約や取引はすべて法人名義で行われ、事業上の責任も原則として法人に帰属します。
マイクロ法人は、個人事業主が法人成り(法人化)するケースのほか、個人事業主としての事業は継続しつつ、別事業でマイクロ法人を設立し、社会保険料の負担を最適化したり、税制上のメリットを享受したりする目的で活用されることが増えています。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せず、個人そのものが事業の主体となってビジネスを行う人を指します。
フリーランスや自営業者と呼ばれる人の多くが、この個人事業主に該当します。
法人格を持たないため、事業で得た利益も、事業に関する負債や責任も、すべて事業主個人に直接帰属するのが大きな特徴です。
事業を始める際の手続きが非常に簡単な点も特徴の一つです。
法人のように複雑な定款認証や設立登記は必要なく、原則として管轄の税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できます。
手軽に始められる反面、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用されるため、一定の所得を超えると法人化を検討するケースが多くなります。
【一覧表】マイクロ法人と個人事業主の違いを早見チェック

マイクロ法人と個人事業主、どちらを選ぶべきか迷っている方のために、まずは両者の主な違いを一覧表にまとめました。
税金や社会保険、設立の手間など、重要なポイントを比較し、全体像を素早く把握しましょう。
各項目の詳細については、この後の章で詳しく解説していきます。
| 比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 設立手続き・費用 | 定款認証や法人登記が必要。 株式会社で約20万円~、合同会社で約6万円~の費用がかかる。 | 税務署に開業届を提出するだけ。 費用は原則0円で、手続きも非常に簡単。 |
| 税金の種類 | 法人税、法人住民税、法人事業税など。 役員報酬に対しては所得税・住民税がかかる。 | 所得税、住民税、個人事業税、消費税(条件による)。 事業で得た所得全体に課税される。 |
| 適用される税率 | 法人税率は所得800万円以下の部分は15%など、一定の税率。 (資本金1億円以下の普通法人の場合) | 所得税率は所得に応じて変動する累進課税。 所得が高くなるほど税率も上がる(5%~45%)。 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金への加入が義務。 社長1人でも強制加入となり、保険料は会社と個人で折半する。 | 国民健康保険・国民年金に加入。 保険料は全額自己負担。扶養の概念がないため、家族の人数分保険料が増える場合がある。 |
| 経費の範囲 | 事業関連費に加え、役員報酬(給与所得控除が使える)、生命保険料、退職金なども経費にできるため、範囲が広い。 | 事業に直接関連する費用のみ経費として認められる。 自分自身への給与は経費にできない。 |
| 赤字の繰越 | 青色申告の場合、欠損金を最大10年間繰り越せる。 | 青色申告の場合、純損失を最大3年間繰り越せる。 |
| 社会的信用度 | 法人格があるため、一般的に信用度が高い。 金融機関からの融資や大手企業との取引で有利になる傾向がある。 | 法人に比べると信用度が低いと見なされることがある。 ただし、事業内容や実績による。 |
| 会計・事務負担 | 複式簿記での記帳が必須。 決算申告や社会保険の手続きが複雑で、税理士への依頼が一般的。 | 青色申告(65万円控除)でも複式簿記が必要だが、法人よりは簡便。 確定申告も比較的シンプル。 |
| 廃業手続き | 解散登記や清算手続きが必要。 時間と費用(登記費用などで数万円~)がかかる。 | 税務署に廃業届を提出するだけ。 手続きは簡単で、費用もかからない。 |
マイクロ法人と個人事業主の5つの大きな違いを徹底解説

マイクロ法人と個人事業主は、どちらも小規模で事業を始める際の選択肢ですが、その性質は全く異なります。
特に「税金」「社会保険」「設立・廃業の手間」「経費の範囲」「社会的信用度」という5つの観点で大きな違いがあります。
これらの違いを理解することが、あなたにとって最適な事業形態を選ぶための第一歩です。
ここでは、それぞれのポイントを深掘りして、具体的に比較解説していきます。
違い1 税金の種類と負担額
事業で得た利益(所得)に対して支払う税金は、事業形態によって種類も税率も大きく異なります。
一般的に、所得が低い段階では個人事業主が、所得が高くなるにつれてマイクロ法人が税制上有利になる傾向があります。
個人事業主にかかる税金
個人事業主の事業で得た所得には、主に以下の税金がかかります。
- 所得税:所得に応じて税率が上がる「累進課税」が採用されており、5%から最高45%までの7段階に分かれています。
- 住民税:所得に対して一律約10%がかかります。
- 個人事業税:所得が290万円を超えた場合に、業種に応じて3%~5%がかかります(一部非課税の業種あり)。
- 消費税:課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。
個人事業主の税負担で最も特徴的なのは、所得が増えれば増えるほど所得税率も高くなる点です。
住民税と合わせると、最大で約55%もの税率が課される可能性があります。
マイクロ法人にかかる税金
マイクロ法人が事業で得た所得(法人所得)には、主に以下の税金がかかります。
- 法人税:資本金1億円以下の中小法人の場合、所得800万円以下の部分には15%、800万円を超える部分には23.2%の税率が適用されます(実効税率はもう少し高くなります)。
- 法人住民税:法人の所得に応じて課される「法人税割」と、赤字でも発生する「均等割」(最低でも年間約7万円)があります。
- 法人事業税:法人の所得に対して課される税金です。
- 消費税:個人事業主と同様、課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が発生します。
法人税率は所得税の累進課税と異なり、一定の所得までは税率が固定されています。
また、社長個人は法人から受け取る「役員報酬」に対して、別途所得税と住民税を支払うことになります。
所得が増えるとマイクロ法人が有利になる理由
事業所得が増加するとマイクロ法人が有利になる主な理由は、所得税の「累進課税」と「法人税率」の違いにあります。
個人事業主の所得税率は最大45%に達しますが、法人税率は高くても23.2%です。
そのため、事業所得がある一定のライン(一般的に800万円~1,000万円が目安)を超えると、個人事業主として高い所得税を払うよりも、法人を設立して法人税を払い、自身には役員報酬として給与を支払う方が、トータルの税負担を抑えられるのです。
さらに、役員報酬は給与所得となるため「給与所得控除」が適用されます。
これは、個人事業主の経費とは別に認められるみなし経費のようなもので、課税対象となる所得を圧縮する効果があります。
このように、法人所得と個人所得に分散し、それぞれに適用される税率や控除をうまく活用することで、大きな節税効果が期待できるのがマイクロ法人の強みです。
違い2 社会保険の加入義務と保険料
社会保険は、多くの事業者にとって税金と同じくらい大きな負担となり得るものです。
加入義務や保険料の計算方法が、個人事業主とマイクロ法人では全く異なります。
個人事業主が加入する国民健康保険と国民年金
個人事業主は、原則として「国民健康保険」と「国民年金」に加入します。
- 国民健康保険:前年の所得に基づいて保険料が計算されます。所得が増えれば保険料も高くなり、自治体によっては年間100万円近い上限額に達することもあります。また、扶養という概念がないため、家族の人数に応じて保険料が加算されるのが大きな特徴です。
- 国民年金:保険料は所得にかかわらず一律定額です。ただし、将来受け取れる年金額は、次に説明する厚生年金に比べて少なくなります。
マイクロ法人が加入する健康保険と厚生年金
マイクロ法人を設立すると、社長が1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が法律で義務付けられています。
- 健康保険・厚生年金:保険料は、社長に支払われる役員報酬(標準報酬月額)の金額に基づいて決まります。算出された保険料は、法人と個人で半分ずつ負担(労使折半)します。
法人で加入する健康保険には「扶養」の制度があります。
これにより、一定の収入以下の配偶者や子供を扶養に入れることができ、その場合、被扶養者の分の保険料は追加でかかりません。
また、厚生年金に加入することで、国民年金(1階部分)に上乗せして年金(2階部分)を受け取れるため、将来の保障が手厚くなります。
社会保険料の負担を抑えられるのはマイクロ法人
一見、加入が義務で負担が重そうに見える法人の社会保険ですが、実はマイクロ法人の仕組みをうまく活用することで、社会保険料を最適化できます。
個人事業主の国民健康保険料は所得に連動して自動的に決まってしまいますが、法人の社会保険料は役員報酬額によって決まります。
つまり、自身の役員報酬を低めに設定することで、社会保険料の負担を意図的にコントロールできるのです。
例えば、生活に必要な資金は事業の利益から役員報酬として受け取り、残りは法人に利益として留保する、といった戦略が可能になります。
特に、扶養家族がいる場合や事業所得が高額な場合には、所得に連動して高額になりがちな国民健康保険料を支払うよりも、役員報酬を調整して法人の社会保険に加入した方が、世帯全体での社会保険料負担を大幅に軽減できるケースが多くあります。
違い3 設立と廃業の手間とコスト
事業を始める際の手軽さや、万が一事業をたたむときの手間とコストも、両者を比較する上で重要なポイントです。
設立時の違い
設立の手間とコストは、個人事業主の方が圧倒的に少なく、手軽です。
| 項目 | マイクロ法人(株式会社の例) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 主な手続き | 定款の作成・認証、法務局への登記申請、税務署・都道府県・市町村への法人設立届の提出など | 税務署への開業届の提出 |
| 費用の目安 | 約20万円~25万円(定款認証手数料、登録免許税など) | 0円 |
| 手軽さ | 手続きが複雑で時間がかかる。司法書士など専門家への依頼も一般的。 | 書類1枚で完了するため非常に手軽。 |
マイクロ法人(特に株式会社)を設立するには、法的な手続きが必要で、最低でも20万円以上の実費がかかります。
一方、個人事業主は税務署に「開業届」を提出するだけで、費用は一切かかりません。
廃業時の違い
廃業時も同様に、個人事業主の方が手続きは簡単です。
個人事業主は「廃業届」を提出すれば完了しますが、マイクロ法人の場合は、法務局で「解散登記」と「清算結了登記」という2段階の法的手続きが必要となり、数万円の登録免許税や官報公告費用がかかります。
また、手続きも複雑で、完了までに数ヶ月を要します。
さらに、法人は事業活動をしていなくても、存在する限り法人住民税の「均等割」(最低でも年間約7万円)を支払い続けなければなりません。
設立だけでなく、廃業にも手間とコストがかかる点は、法人化を検討する際の注意点です。
違い4 経費として認められる範囲
経費にできる範囲の広さは、法人が個人事業主よりも優れている点の一つです。
これが節税メリットに直結します。
役員報酬と給与所得控除の活用
最大の違いは、自分自身への給与を経費にできるかどうかです。
個人事業主の場合、事業で得た利益はすべて事業主個人の所得となり、「自分に給与を支払う」という概念はありません。
そのため、事業主の生活費は経費にできません。
一方、マイクロ法人では、社長である自分自身に「役員報酬」という形で給与を支払うことができ、その全額を法人の経費として計上できます。
これにより、法人の利益を圧縮し、法人税の負担を軽減できます。
さらに、役員報酬を受け取った社長個人は、所得税を計算する際に「給与所得控除」という、いわばサラリーマンの必要経費のような控除を受けることができます。
法人側で経費にしつつ、個人側でも控除が受けられるため、税負担を二重に軽減する効果が期待できるのです。
退職金や出張手当の可否
法人格を持つことで、個人事業主では認められない経費の計上が可能になります。
- 退職金:個人事業主には退職金という制度はありませんが、法人は社長自身に対して退職金を支払うことができ、これを経費に計上できます。受け取る側の退職金は、税制上非常に優遇されている「退職所得控除」が適用されるため、老後の資金を効率的に準備する手段となります。
- 出張手当(日当):個人事業主の出張経費は交通費や宿泊費などの実費のみが認められます。一方、法人は「出張旅費規程」をあらかじめ定めておくことで、実費とは別に役員や従業員に出張手当(日当)を支給できます。この手当は、法人側では経費となり、受け取った個人側では非課税所得となるため、双方にメリットがあります。
- 社宅制度:法人が賃貸物件を契約し、役員に社宅として貸し出すことで、家賃の一部を法人の経費にできます。個人が直接支払う家賃は経費になりませんが、この制度を使えば住居費の負担を軽減できます。
違い5 社会的な信用度
一般的に、個人事業主よりも法人の方が社会的な信用度は高いとされています。
これは、ビジネスを展開する上で様々なメリットにつながります。
法人が信用されやすい理由は以下の通りです。
- 存在の公的証明:法人は法務局に登記されており、商号、本店所在地、役員、資本金などの情報が公開されています。誰でもその存在を公的に確認できるため、信頼性が高まります。
- 経営の透明性:法人は決算書の作成が義務付けられており、財産状況や経営状態が個人事業主よりも明確です。
- 事業と個人の分離:法人の財産と個人の財産は明確に区別されており、経理処理も厳格に行われるため、取引相手に安心感を与えます。
この社会的な信用度の高さは、具体的に以下のような場面で有利に働きます。
- 金融機関からの融資:事業拡大のための資金調達において、法人の方が融資審査で有利になる傾向があります。
- 大手企業との取引:企業によっては、コンプライアンス上の理由から取引相手を法人のみに限定している場合があります。法人化することで、ビジネスチャンスが広がります。
- 人材採用:求人募集の際、社会保険が完備されている法人の方が、求職者にとって魅力的に映り、優秀な人材を確保しやすくなります。
ただし、設立したばかりのマイクロ法人の場合、実績のある個人事業主よりも信用度が低いと見なされることもあります。
信用度は法人格の有無だけで決まるのではなく、事業の実績や財務状況が総合的に判断されることを覚えておきましょう。
マイクロ法人と個人事業主それぞれのメリットとデメリット
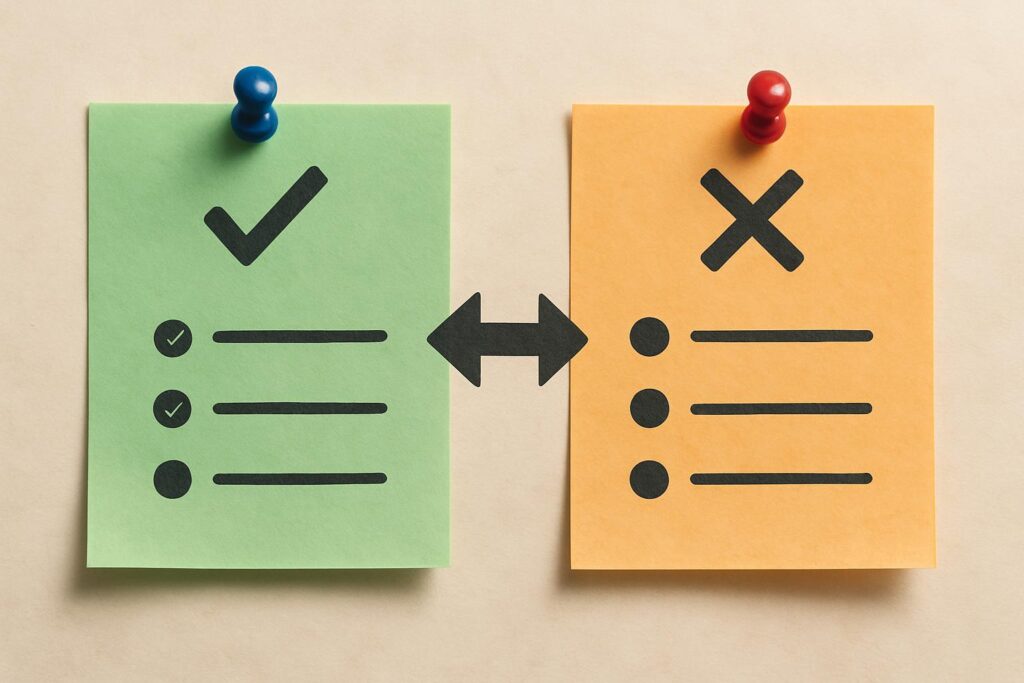
ここまでマイクロ法人と個人事業主の具体的な違いを解説してきました。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを改めて整理し、どのような方にどちらの形態が向いているのかをより明確にしていきます。
マイクロ法人のメリットとデメリット
マイクロ法人は、特に税金と社会保険の面で大きなメリットを享受できる可能性がある一方で、設立や運営に手間とコストがかかるという側面も持ち合わせています。
マイクロ法人のメリット
- 社会保険料を最適化できる
- 所得が増えるほど税制上有利になる
- 経費として認められる範囲が広い
- 社会的信用度が高い
- 有限責任である
最大のメリットは、社会保険料の負担をコントロールできる点です。
役員報酬を低く設定することで、健康保険と厚生年金の保険料を大幅に抑えることが可能です。
また、事業所得が一定額(一般的に800万円~1,000万円)を超えると、所得税の累進課税よりも法人税の方が税率が低くなるため、節税効果が高まります。
さらに、役員報酬に対する給与所得控除の適用や、退職金、社宅制度などを活用することで、個人事業主よりも経費にできる範囲が広がるのも大きな魅力です。
マイクロ法人のデメリット
- 設立・廃業に手間とコストがかかる
- 赤字でも税金(法人住民税均等割)が発生する
- 事務処理や経理が複雑になる
- 会社の資金を自由に使えない
法人設立には、定款認証や登記費用として約20万円〜25万円の実費が必要です。
また、事業が赤字であっても、法人住民税の均等割(最低でも年間約7万円)を毎年納付しなければなりません。
社会保険の加入手続きや法人決算など、個人事業主と比べて経理・労務の事務負担が格段に増えるため、税理士など専門家への依頼費用も考慮する必要があります。
事業で得た利益は会社の資産であり、役員報酬として定められた額しか受け取れないため、資金の自由度は低くなります。
【一覧表】マイクロ法人のメリット・デメリットまとめ
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 税金 | ・所得が増えると法人税の方が税率が低い ・給与所得控除が使える ・欠損金の繰越期間が10年と長い | ・赤字でも法人住民税均等割(年約7万円~)がかかる |
| 社会保険 | ・役員報酬の調整で保険料をコントロールできる ・扶養家族の保険料負担がない ・将来の年金額(厚生年金)が増える | ・役員1人でも加入が義務 ・手続きが煩雑 |
| 経費 | ・役員報酬、退職金、社宅、出張手当などが経費になる | ・交際費の損金算入に上限がある |
| 手続き・コスト | ・社会的信用が高く、融資や取引で有利 | ・設立費用(約20~25万円)がかかる ・維持コスト(税理士費用など)が高い ・会計処理や申告が複雑 ・廃業手続きが煩雑で費用もかかる |
| 責任・資金 | ・有限責任(出資額の範囲で責任を負う) | ・会社の資金を自由に使えない |
個人事業主のメリットとデメリット
個人事業主の魅力は、何と言ってもその手軽さと自由度の高さにあります。
事業を始めやすく、利益の使い道も自由ですが、所得が増えるにつれて税金や社会保険料の負担が重くなる傾向があります。
個人事業主のメリット
- 開業・廃業の手続きが簡単でコストがかからない
- 会計処理や確定申告が比較的シンプル
- 事業で得た利益を自由に使える
- 赤字の場合、税金はかからない
最大のメリットは、事業の始めやすさと運営のしやすさです。
税務署に開業届を提出するだけで、費用をかけずに事業を開始できます。
廃業も同様に簡単です。会計処理も法人に比べると簡素で、自分自身で確定申告を行うことも十分可能です。
また、事業で得た利益はすべて事業主個人のものとなるため、生活費などに自由に使える点も大きな魅力と言えるでしょう。
個人事業主のデメリット
- 所得が増えると税率が高くなる
- 社会保険料の負担が大きくなる可能性がある
- 社会的信用度が法人に比べて低い
- 無限責任である
所得が増えるほど税率が上がる累進課税が適用されるため、高所得になると法人よりも税負担が重くなります。
国民健康保険料も所得に連動して高額になりがちで、自治体によっては上限額も高いため、税金と社会保険料を合わせたトータルの負担額が大きくなる可能性があります。
自分自身への給与は経費にできず、退職金制度などもありません。
また、事業上の負債はすべて個人の財産で返済義務を負う「無限責任」である点も、事業規模が大きくなるほどリスクとなります。
【一覧表】個人事業主のメリット・デメリットまとめ
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 税金 | ・所得が低い場合は税率が低い ・赤字の場合、税金はかからない ・青色申告特別控除が使える | ・所得が増えると累進課税で税率が非常に高くなる ・欠損金の繰越期間が3年と短い |
| 社会保険 | ・所得が低い場合は保険料が安い | ・所得に比例して国民健康保険料が高くなる ・扶養の概念がなく、家族の保険料も発生する場合がある ・年金は国民年金のみ |
| 経費 | ・会計処理がシンプル | ・自分への給与や退職金は経費にできない ・経費にできる範囲が法人より狭い |
| 手続き・コスト | ・開業・廃業が無料で簡単 ・維持コストが低い | ・社会的信用が低く、融資や取引で不利になることがある |
| 責任・資金 | ・事業の利益を自由に使える | ・無限責任(事業の負債は全財産で負う) |
結局どっち?マイクロ法人と個人事業主の選択で迷ったときの判断基準

ここまでマイクロ法人と個人事業主の様々な違いを解説してきましたが、結局自分はどちらを選べば良いのか、迷ってしまう方も多いでしょう。
税金、社会保険、手続きのコストなど、考慮すべき点が多く、最適な選択は個人の状況によって大きく異なります。
この章では、あなたがどちらを選ぶべきか判断するための具体的な3つの基準を、それぞれの状況に合わせて詳しく解説します。
事業所得の金額で判断する
最も重要な判断基準となるのが、事業で得られる所得(売上から経費を差し引いた利益)の金額です。
所得税が超過累進課税である個人事業主と、税率がほぼ一定の法人とでは、所得額によって納税額に大きな差が生まれます。
一般的に、課税所得が800万円から1,000万円を超えるあたりが、個人事業主よりもマイクロ法人のほうが税負担上有利になる目安と言われています。
これは、所得税率が法人税の実効税率を上回る分岐点だからです。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。
消費税の課税事業者であるか、どのような経費を計上するか、社会保険料の負担額などによって、有利になるタイミングは前後します。
以下の表を参考に、ご自身の所得状況と照らし合わせてみてください。
| 課税所得金額の目安 | おすすめの事業形態 | 主な理由 |
|---|---|---|
| ~500万円 | 個人事業主 | 所得税・住民税の税率が低く、設立・維持コストもかからないため、手元に残る金額が多くなる可能性が高い。 |
| 500万円~800万円 | どちらも検討の価値あり(個人事業主が有利な場合が多い) | 所得は増えるが、法人設立コストや社会保険料負担を考慮すると、まだ個人事業主の方が有利なケースが多い。ただし、扶養家族の状況によってはマイクロ法人が有利になることも。 |
| 800万円~ | マイクロ法人 | 所得税・住民税の合計税率が法人税率を大きく上回り始めるため、法人化による節税メリットが設立・維持コストを上回る可能性が高くなる。役員報酬の調整による所得分散も有効。 |
正確なシミュレーションを行うには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
扶養家族の有無で判断する
社会保険料の観点から見ると、扶養家族の有無は非常に重要な判断基準となります。
特に、配偶者やお子さんを扶養している場合、マイクロ法人のメリットが大きくなります。
扶養家族がいる場合:マイクロ法人が有利
個人事業主が加入する国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
そのため、世帯の加入人数に応じて保険料が増加する仕組みになっています(自治体により上限あり)。
一方、マイクロ法人で役員として加入する健康保険(協会けんぽなど)には扶養制度があります。
これにより、ご自身の役員報酬を低めに設定すれば、配偶者やお子さんなど、何人扶養家族がいても社会保険料は変わりません。
これは、家計全体の支出を抑える上で非常に大きなメリットです。
扶養家族がいない(単身の)場合:個人事業主が有利なことも
単身者の場合、国民健康保険料の負担は一人分で済みます。
そのため、所得がそれほど高くないうちは、法人化して社会保険に加入するよりも、国民健康保険と国民年金の組み合わせの方が、年間の保険料負担を抑えられるケースが多くなります。
ただし、将来的に厚生年金に加入することで受け取れる年金額を増やしたいという考えがあれば、所得が低い段階からマイクロ法人を設立する選択肢も十分に考えられます。
今後の事業拡大の予定で判断する
短期的な損得だけでなく、将来の事業計画も選択を左右する大切な要素です。
あなたのビジネスの将来像を思い描き、それに合った形態を選びましょう。
事業を拡大したい、融資や採用を考えている場合
将来的に事業を大きくしていきたいと考えているなら、マイクロ法人が断然有利です。
- 社会的信用度:法人は個人事業主よりも社会的信用度が高く、金融機関からの融資審査や、大手企業との取引において有利に働きます。
- 資金調達:融資だけでなく、出資を受け入れるといった資金調達の選択肢も生まれます。
- 人材採用:求人募集の際、社会保険が完備されている法人の方が、優秀な人材が集まりやすい傾向にあります。
- 事業承継:将来的に事業を誰かに引き継ぐ際も、法人の方が株式譲渡などの形でスムーズに進められます。
初めは小さくても、将来的なスケールアップを視野に入れているのであれば、最初からマイクロ法人としてスタートすることを強くおすすめします。
副業やスモールビジネスとして継続する場合
事業を大きくするつもりはなく、副業として、あるいは自分のペースでスモールビジネスを続けていきたいという場合は、個人事業主の手軽さが魅力です。
- 手続きの手間とコスト:開業・廃業の手続きが簡単で、費用もほとんどかかりません。
- 自由度の高さ:事業で得た利益はすべて自分のものとして、自由に使えます。
- 維持コストの低さ:法人住民税の均等割のような、赤字でも発生する税金がないため、維持コストを低く抑えられます。
まずは個人事業主としてスタートし、事業が軌道に乗って所得が増えてきたタイミングで法人化(法人成り)を検討するというのも、非常に現実的で賢い選択と言えるでしょう。
まとめ
マイクロ法人と個人事業主の違いを、税金や社会保険など5つの観点から解説しました。
どちらが有利かは事業所得や扶養家族の有無で変わります。一般的に、所得が少ないうちは手軽な個人事業主、所得が増え社会保険料の負担を抑えたい場合はマイクロ法人が有利になる傾向があります。
設立コストや経費の範囲も考慮し、ご自身の事業計画に合った最適な働き方を選択しましょう。