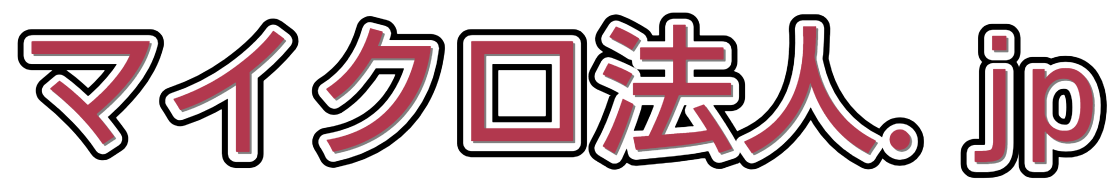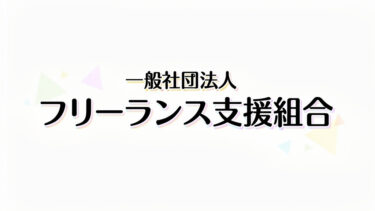マイクロ法人と個人事業主の二刀流とは?基本を解説
マイクロ法人とは何か
マイクロ法人とは、社員(役員も含めて1〜数名規模)のみ、家族経営や個人で管理可能な最小限の法人形態を指します。
主に節税や社会保険の最適化、小規模な事業展開を目的に設立されることが多く、株式会社や合同会社(LLC)が主流です。
特に昨今は事業の多様化や副業解禁の流れを受け、フリーランスや個人事業主が自らのビジネスを法人化(法人成り)することで、手取りの最大化や社会的信用の強化を図るケースが増えています。
なお、マイクロ法人ならではの手法や注意点については、中小企業庁など公的情報も参照が推奨されます(https://www.chusho.meti.go.jp/)。
個人事業主とは何か
個人事業主とは、法人を設立せず個人の名義で事業活動を行う形を指します。
自分自身が屋号や本名で税務申告・納税を行い、起業のハードルが低いことが特徴です。
会社設立の手続きやコストが不要で、開業届の提出だけでスタートできます。
しかし経費計上や社会保険の加入範囲、事業拡大時の信用力などに限界が生じる場合もあります。
マイクロ法人と個人事業主で二刀流を実現する仕組み
「マイクロ法人と個人事業主の二刀流」とは、同一人物が同時に個人事業主と法人代表(役員)を兼務し、両方の特長を活かしながら事業活動と税務最適化を図る手法です。
日本の法律上、個人事業と法人運営は明確に分けて管理し、それぞれ所得計算・確定申告を独立して行う必要があります。
たとえば、受託業務やコンサルなどで個人名義で請けやすい案件は個人事業で、規模が大きくなったり経費や社会的信用を重視する部分はマイクロ法人名義で請けるなど、売上や業務内容・各種経費の按分などを分けて運用します。
| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 設立手続き | 会社設立登記・定款作成が必要 | 税務署に開業届を提出 |
| 税金・社会保険 | 法人税/社会保険(役員報酬ベース) | 所得税・住民税/国民健康保険 |
| 経費計上範囲 | 法人活動にかかったものを幅広く計上可 | 個人名義の支出から必要経費を計上 |
| 社会的信用 | 高い(法人登記あり) | やや低い(個人名義) |
このように二刀流による最適化を狙う場合、税務・労務の明確な区分や事業計画の整合性が求められます。
詳しい利用例や注意点については、金融庁や国税庁の公式サイトも参照が推奨されます。
どんな人がマイクロ法人と個人事業主の二刀流を検討するのか
次のような方に二刀流は積極的に検討されています。
- 年間所得が増えてきて、社会保険料や所得税の負担を適正化したい個人事業主
- 特定案件だけ法人として請け負いたいフリーランス・クリエイター
- 副業収入と本業収入を分けて管理したいパラレルワーカー
- 将来的な事業拡大や会社設立を視野に入れている起業家
- 節税・社会的信用の向上を狙う方
なお、二刀流には適切な管理や税務知識が不可欠で、不適切な運用は「税法上の否認リスク」などもあるため、必ず専門家への相談や最新の法令確認が推奨されます。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流 7つのメリット

社会保険料の最適化で節約効果を期待
マイクロ法人と個人事業主を併用することで、社会保険負担を最適化できることが最大のメリットの一つです。
具体的には、マイクロ法人の役員報酬を年間130万円未満(毎月108,334円以下)に設定すれば、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じず、扶養範囲内での保険料負担を大幅に軽減可能です。
また、配偶者がマイクロ法人の役員になることで家族の保険料負担も管理しやすくなります。
所得分散による所得税と住民税の軽減
事業収入を個人事業主とマイクロ法人に分散させることで、累進課税である所得税や住民税の負担を抑えることが可能です。
年間の個人所得を増やしすぎると高い税率が適用されますが、法人に事業収入の一部を計上し、その分を役員報酬や配当という形で受け取ることで、税率の低いゾーンに所得を分散でき節税効果が期待できます。
消費税の免税メリットを最大限活用する方法
新設法人は設立から最長2期、消費税の納税義務が免除される「消費税免税事業者」特例を活用できます。
これにより、個人事業主側で課税売上高が1,000万円を超えた場合でも、法人の売上は別カウントとなるため、消費税負担の最適な分散が可能です。
インボイス制度対応においても、この二刀流運用はメリットがあります。
役員報酬による給与所得控除の活用メリット
マイクロ法人の役員報酬を受け取ることで、給与所得控除が利用でき、「所得控除枠」を活かした節税が可能です。
個人事業主としての事業所得は経費しか差し引かれませんが、役員報酬なら給与所得控除(例:年間180万円の給与なら約54万円の控除)が追加され、総合的な所得税負担を軽減できます。
法人としての経費計上範囲の拡大
マイクロ法人を設立することで、個人事業主時代よりも経費として認められる範囲が広くなります。
例えば法人として従業員や役員への福利厚生費、会議費、分かりやすい法人名義の経費等を計上しやすくなるため、可視化できる節税メリットが増します。
また、出張手当や社宅利用など法人独自の経費枠も利用できます。
退職金制度、小規模企業共済などの活用
マイクロ法人では役員退職金制度の導入が可能で、個人事業主時代には取れなかった「退職金控除」の適用や、小規模企業共済への加入も両立できます。
これは長期的な資産形成・節税策として有効です。
また、事業主個人も引き続き小規模企業共済やiDeCo等のメリットを享受できます。
マイクロ法人設立による社会的信用の向上
法人格を持つことで、銀行口座開設やクレジットカード発行、取引先との契約面等で社会的信用が大幅に向上します。
特にBtoB(法人間取引)や自治体などと取引を検討している場合に有利となります。
また、資金調達・助成金・融資などの幅も広がります。
| メリット | 具体的な効果・特徴 |
|---|---|
| 社会保険料の最適化 | 役員報酬を調整し、保険負担を大幅に軽減 |
| 所得分散で税負担軽減 | 累進課税回避・所得分散により節税 |
| 消費税の免税特例活用 | 新設法人の免税期間重複で負担分散 |
| 給与所得控除活用 | 役員報酬の給与所得控除で可視的節税 |
| 経費計上範囲の拡大 | 法人費用枠拡充で各種経費が通りやすい |
| 退職金・共済等の活用 | 退職金枠や小規模共済を個人・法人両方で使える |
| 社会的信用の向上 | 法人格で信用力アップ・融資や契約が有利 |
マイクロ法人と個人事業主の二刀流 5つのデメリットと注意点

法人設立と維持コストの発生
マイクロ法人を設立する場合、法人登記費用・定款認証費用・資本金準備・法人印鑑作成など、初期コストが必要になります。
さらに、毎年法人住民税均等割(最低7万円)が必ず発生し、たとえ赤字でも支払義務が生じます。
加えて、会計や決算書類の作成・税理士への報酬など維持にかかるランニングコストも無視できません。
個人事業主の場合とは違い、「とりあえず始めてみる」といった気軽さはなく、明確な事業計画と採算性の確認が重要です。
経理処理や事務作業の負担増と対策
法人と個人事業主を同時に運営すると、それぞれで帳簿管理・確定申告など事務作業が倍増します。
会計ソフトの併用や帳簿の仕分け、契約書の整理など、煩雑な作業が日常的に求められます。
特に導入初期は、経理の知識不足や作業ミスによる税務リスクも増加します。
合理的な業務フロー設計や税理士・会計士に業務委託するなど業務効率化が必須です。
税務調査のリスクとマイクロ法人の注意点
マイクロ法人の節税を目的とした設立は、税務署から不自然な所得分散や役員報酬の設定などについて注視されるケースが増えています。
税務調査が入った際、所得の分け方や経費の按分が不適切と判断される場合、追徴課税など厳しい指摘を受けるリスクがあります。
租税回避とみなされるような設計・運用は控え、正当かつ根拠ある運営を心がける必要があります。
個人事業と法人事業の適切な振り分けの難しさ
事業内容をどちらの名義で行うかは、税務署の基準に照らして事前に明確に区分しなければなりません。
売上・経費・契約主体の切り分け基準があいまいなまま運用すると、後々の税務調査で否認されることもあります。
たとえば、個人と法人で契約を分けたり、請求書発行主体を明確にしたりといった厳密なルール作りと運用が求められます。
赤字の場合の法人住民税均等割の負担
マイクロ法人は利益がゼロ、つまり赤字であっても、毎年法人住民税均等割(標準7万円)が必ず発生します。
個人事業主であれば所得ゼロなら税負担が原則的にありませんが、法人の場合は「休眠状態」でも納税義務が継続します。
収益化まで時間がかかると、費用負担が経営を圧迫するリスクがありますので、事業計画の精密なシミュレーションが必須です。
| デメリット・注意点 | 対策・留意点 |
|---|---|
| 設立・維持コストの発生 | 明確な事業計画作成とコストシミュレーションが重要 |
| 経理・事務負担の増加 | 業務効率化のための経理システム導入、専門家活用 |
| 税務調査リスク | 根拠ある運営と適切な所得・経費区分、定期的な専門家相談 |
| 事業内容の切り分けの難しさ | 契約・請求主体の明確化、ルール作成・運用の徹底 |
| 赤字時の法人住民税負担 | 長期的な収益シミュレーションとリスクヘッジ策の準備 |
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を始めるためのステップ

マイクロ法人と個人事業主の二刀流を行うには、入念な準備と法的手続きを踏むことが不可欠です。
ここでは、スムーズかつ適法に二刀流を始めるための具体的なステップを解説します。
なお、2024年6月時点の最新制度に基づき解説します。
ステップ1 事業計画と収益シミュレーションの重要性
まず、二刀流を始める前に自身の事業内容や収益構造を明確に洗い出し、個人事業と法人の役割をシミュレーションすることが必須です。
経費の配分、売上の見込み、社会保険や税金負担増減などを数値でシミュレーションすることで、最適な分岐点やリスクを把握できます。
事前に税理士や公認会計士と相談し、将来的な見通しも含めて検討することをおすすめします。
ステップ2 マイクロ法人の設立手続き完全ガイド
続いて、法人形態選定から登記までの流れを把握しましょう。
個人事業主としては、既存事業と法人間の棲み分けも考慮し、用途に適した法人形態を選びます。
| 手順 | 詳細とポイント |
|---|---|
| 会社形態の選択 | 日本で選択される主な形態は合同会社(LLC)と株式会社です。 合同会社は設立費用が安く、企業規模が小さい方には人気です。株式会社は社会的信用力に優れる反面、定款認証費用などが発生します。 事業内容・規模・コスト面を総合的に検討しましょう。 |
| 定款作成と認証(株式会社の場合) | 株式会社設立時は定款の作成と公証役場での認証が必須です。合同会社は認証不要です。紙定款では印紙代(4万円)が発生しますが、電子定款なら不要です。 |
| 資本金の準備と払い込み | 資本金は1円から設定可能ですが、事業計画や信用力に応じた金額を決め、発起人個人名義の口座に払い込みます(法人設立後、事業用口座を開設)。 |
| 法人登記申請の手順 | 法務局で設立登記を行います。登記申請書、定款、印鑑証明書など必要書類を準備し、設立日や業務開始日に注意しましょう。詳しいフローは法務省のサイトで確認できます。 |
| 税務署等への各種届出 | 法人設立後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ各種届出が必要です。主なものは「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」など。 提出期限や必要書類を漏れなく準備し、社会保険の新規適用届も忘れずに行いましょう。 |
ステップ3 個人事業と法人事業の役割分担と業務設計
法人を設立した後は、個人と法人の収益・経費の線引き、業務ごとの責任分担を明確にします。
曖昧な曽業内容の重複は税務リスクの原因にもなるため、サービスごと・顧客ごとにしっかり切り分けましょう。
両者が取引を行う場合は、契約書を交わして適切な取引価格と内容を設定します。
Googleドライブや会計ソフトなどで帳簿書類を明確に分けることもおすすめです。
ステップ4 必要な契約や法人口座の準備
法人名義の銀行口座、クレジットカード、取引先との新規契約など、法人用インフラを速やかに整備しましょう。
特に銀行口座は、設立登記後、法人の履歴事項全部証明書、印鑑証明書を使って開設手続きします。
新規契約としては、オフィス賃貸契約や各種業務の外注契約などがあります。
必要に応じて電子契約サービスの活用も検討しましょう。
ステップ5 専門家 税理士などへの相談ポイント
最後に、税理士・社会保険労務士など専門家と定期的に連絡を取り、業務・税務・社会保険の最適化やリスク管理を継続的に行うことが不可欠です。
特に、消費税や所得税、社会保険の適用範囲、役員報酬の最適設定、有事の相談先の確保など、プロの目でチェックしてもらいましょう。
会計ソフトの選定や毎月の記帳・申告サポートも込みで顧問契約を検討するのがおすすめです。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流が向いている人 向いていない人

二刀流がおすすめなケース マイクロ法人と個人事業主の組み合わせ
| ケース | 具体例・理由 |
|---|---|
| 一定以上の所得がある個人事業主の方 | 年間所得が900万円~1,000万円以上の場合、個人事業主としての所得税や社会保険料の負担が増大しやすくなります。このような方がマイクロ法人を設立することで、給与所得控除や社会保険料の最適化など、複数の節税対策が可能になります。 |
| 社会保険料の負担を軽減したい方 | マイクロ法人を活用し、役員報酬を標準報酬月額の下限で設定すれば、社会保険料負担を最小限に抑えることができます。将来的な年金受給額や健康保険料も考慮しつつ、バランスよく対応したい場合に適しています。 |
| 将来的に事業拡大を目指す個人事業主の方 | 個人事業主としての活動では限度のある取引先や業務内容を、法人化することで広げられます。法人格があると社会的信用を得やすく、融資や契約の面で有利になるため、今後の成長を見据える場合に効果的です。 |
このようなケースに該当する方は、税負担の最適化・社会保険面での戦略的運用・事業の信用力向上をバランス良く実現できる可能性があります。
二刀流を慎重に検討すべきケース 個人事業主とマイクロ法人の組み合わせ
| ケース | 具体例・理由 |
|---|---|
| 所得がまだ少ない個人事業主の方 | 年間所得300万円未満など利益が小さいうちは、法人を設立・維持するコストが節税等のメリットを上回る可能性があります。均等割の法人住民税や決算書類の作成費用など、経費負担が増加します。 |
| 事務作業が苦手で時間がない方 | 法人化すると会計処理や税務申告など、書類作業が複雑かつ増加します。経理の知識が不足していたり、作業に割く時間がない場合は事務的な負担が大きくなり、業務の効率を損ねかねません。 |
| 事業内容の明確な切り分けが難しい方 | 個人・法人それぞれで行う業務や売上・経費の線引きが曖昧な場合、不適切な経費計上や税務リスクが生じやすくなります。特に同じ事業で二刀流を実践する場合、適正な区分管理が求められます。 |
これらの場合は、やみくもな二刀流よりも事業拡大や収益安定を優先し、タイミングや準備を見極めることが重要です。
専門家(税理士や社会保険労務士)との相談やシミュレーションを必ず行いましょう。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流 成功のためのQ&A
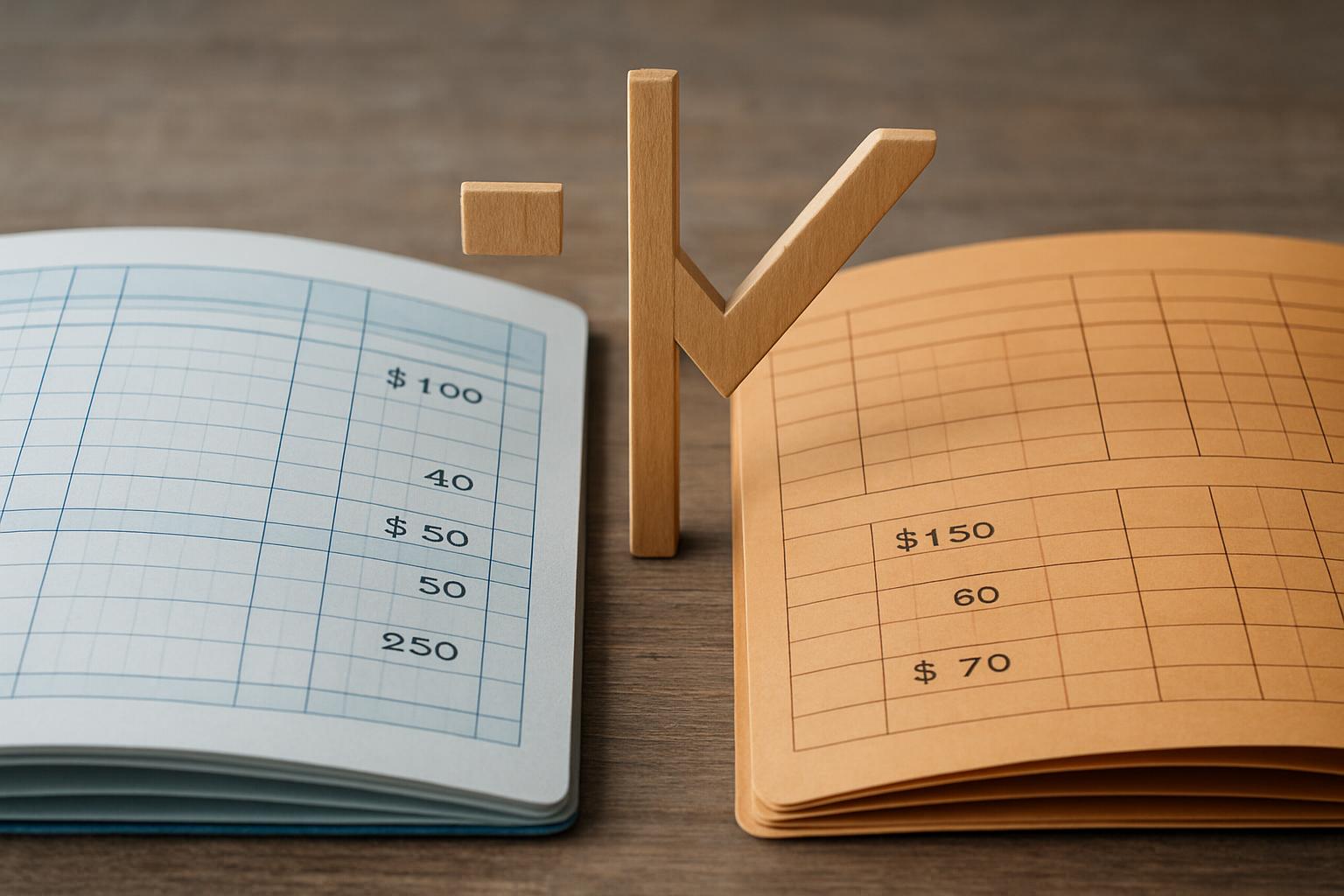
個人事業と法人事業の売上や経費はどう分けるべきか
具体的には、個人名義で請け負った仕事の収入・経費は個人事業の口座と帳簿へ、法人名義で受注した業務の収入・経費は法人の口座・帳簿へ必ず分けて記載します。
請求書や領収書も、各名義で発行・管理してください。
こうした区分を徹底することで、税務処理や法的リスクを最小限に抑えられます。
マイクロ法人の役員報酬はいくらに設定すれば良いか
役員報酬の金額は「社会保険料負担」「法人の所得課税」「消費税の免税」などを総合的に考慮して設計する必要があります。目安としては、年収130万円未満なら社会保険の扶養に入れる一方、法人側で経費計上できる分節税効果もあります。
| 役員報酬額 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 0円 | 法人利益が全て残る 社会保険料なし | 給与所得控除が利用できない |
| 60万円〜130万円未満 | 給与所得控除あり 社会保険の扶養範囲 | 年収増に制限 |
| 130万円以上 | 社会保険に加入可 事業主の老後資金形成も | 社会保険料の負担増 |
二刀流の場合の確定申告はどうなるのか
個人事業主として「所得税確定申告」と、マイクロ法人として「法人税申告」2種類の申告が必要です。
個人の確定申告では、個人事業所得だけでなく、法人から受け取った役員報酬も「給与所得」として申告します。
一方、法人側は決算終了後2か月以内に法人税・法人住民税・法人事業税の申告・納付が必要です。
詳しい流れや必要書類は、国税庁『確定申告書の作成と提出』等で確認してください。
税理士に依頼するメリットと費用相場
事業区分や税制の最適化、日々の経理・帳簿管理、税務調査対応などにプロの力を活用することは、節税やリスク回避に大きなメリットがあります。
特に、マイクロ法人と個人事業主の併用の場面では、複雑な税務処理のアドバイスや、税務署からの問い合わせ対応も重要となります。
| サービス内容 | 相場料金(年額目安) |
|---|---|
| 法人税申告のみ | 7万円〜15万円 |
| 月次顧問+法人申告 | 20万円〜35万円 |
| 個人・法人セット申告 | 25万円〜40万円 |
マイクロ法人の赤字は個人事業の所得と損益通算できるのか
マイクロ法人(法人格)の赤字は、個人事業主の所得とは「損益通算できません」。
これは法人と個人は『別人格』であるためです。
したがって、法人の赤字は法人税法により、翌期以降に法人自身が繰越控除を適用できますが、個人の所得税申告には影響しません。
また、法人が赤字でも、均等割(住民税の最低納税額)は必ず支払う必要があります。
まとめ
マイクロ法人と個人事業主を組み合わせた二刀流は、「社会保険料や税負担の最適化」「消費税や経費計上範囲のメリット」など多くの利点があります。
ただし「設立コストや事務負担増、税務調査リスク」など注意点も存在します。
始める際は収益シミュレーションと専門家(税理士)相談を行い、自身の状況や事業スタイルに合致するか慎重に判断しましょう。