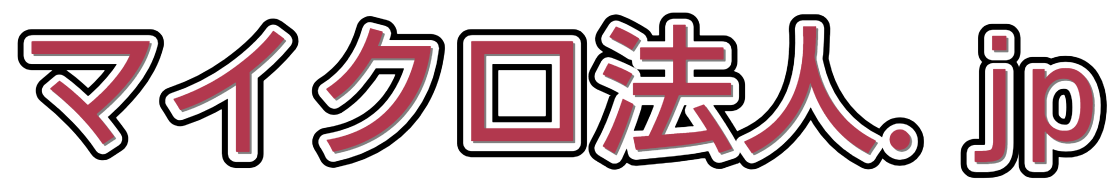国民健康保険とは何か基本をおさらい
国民健康保険の仕組み
国民健康保険(国保)は、日本国内に住所を有する人のうち、会社などの健康保険(社会保険)に加入していない人やその家族が加入する公的医療保険制度です。
自営業者やフリーランス、無職の人、年金生活者などが主な対象となります。
全国の市区町村が保険者(運営主体)となり、住民に対して医療費の一部負担と給付を行うことが特徴です。
医療機関で診療や治療を受けた際、加入者は費用の原則3割(未就学児や70歳以上などは2割・1割の場合もあり)だけを自己負担し、残りを健康保険でまかなう仕組みとなっています。
加入対象者と扶養の範囲
国民健康保険の加入対象者は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していないすべての人です。
具体的には、自営業者・個人事業主・農業従事者・退職者やその家族、パートやアルバイトで勤務先の保険に加入できない人などが該当します。
外国人でも、日本に3ヶ月以上居住予定があれば原則加入義務があります。
| 区分 | 加入の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社員(被用者保険加入) | 不要 | 社会保険が優先 |
| 自営業・フリーランス | 必要 | 国民健康保険に加入 |
| 年金受給者 | 必要または不要 | 75歳以上は後期高齢者医療制度 |
| 家族(扶養) | 必要 | 国保には扶養の概念がなく、1人ずつ個別に加入 |
国民健康保険には「扶養」の取り扱いがないという大きな特徴があります。
会社員の社会保険では一定の条件を満たせば扶養家族として保険料負担なしでカバーされますが、国民健康保険の場合は原則として 世帯の全員がそれぞれ被保険者となり、各人分の保険料が必要です。
保険料の計算方法と仕組み
国民健康保険料は、加入者ごとの所得や資産、世帯構成などを基に市区町村が独自に計算して決定します。
年度ごとに見直され、一般的に次の二つの合計で決まります。
| 保険料の内訳 | 課税対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得 | 所得が多いほど高くなる |
| 均等割 | 加入者人数 | 1人ごとに定額負担 |
| 平等割 | 世帯単位 | 1世帯あたりの定額負担 |
| 資産割(実施自治体のみ) | 保有資産額 | 一部地域で課される |
保険料の計算方法や軽減措置、納付回数などは自治体ごとに異なります。
詳しくは、住民票がある市区町村のホームページや窓口で確認しましょう。
保険料の納付方法も口座振替やコンビニ払いなど複数用意され、分割納付も可能となっています。
国民健康保険料を節約する裏ワザ

世帯分離で保険料を安くする方法
国民健康保険料は、世帯単位で計算されるため、同じ住所に住んでいる家族でも住民票上の「世帯」を分けることで保険料が下がる可能性があります。
特に高齢者と若い世代が同居している場合や、所得格差が大きい家族の場合は、世帯分離によって所得割や均等割の負担を軽減できることがあります。
ただし、世帯分離は税金や他の福祉制度にも影響を及ぼすため、事前に市区町村の窓口で試算してもらうのが安心です。
| ケース | 世帯分離前のデメリット | 世帯分離後のメリット |
|---|---|---|
| 高齢者と自営業が同居 | 保険料が合算されるため高くなりがち | 高齢者分の均等割・所得割を分離できる可能性 |
| 所得格差のある家族 | 高所得者の影響で全員の保険料が高い | それぞれの所得で保険料が算出されるため安くなる |
収入申告漏れによる損を防ぐポイント
市区町村は毎年6月前後に住民の前年所得を元に保険料を算出します。
収入がない、または減少した場合でも必ず所得申告書を提出しないと、「収入なし」とみなされずに最大額で算定されることがあります。
また年金所得・配当所得なども抜け漏れなく報告しましょう。
特に世帯主や家計主など、家族全員分の申告を忘れずに行うことが重要です。
扶養控除や配偶者控除の有効活用
国民健康保険では「扶養」という概念が社会保険のように直接ありませんが、所得税法上の扶養控除や配偶者控除を使うことで所得額を下げることができ、その結果として住民税や国民健康保険料が軽減されます。
子どもや同居の親をしっかり扶養控除の対象にすることで、所得割部分の節約が期待できます。
控除漏れがないか、確定申告や年末調整の際には必ずチェックしましょう。
医療費控除による節約テクニック
毎年1月~12月の間に一家で支払った医療費が一定額(10万円または所得の5%を超える場合)を超えた場合、確定申告で医療費控除を行うことにより所得が減額され、翌年度の国民健康保険料が下がる効果があります。
医療機関の領収書や薬局のレシートは必ず保管し、忘れずに申告することが大切です。
| 控除対象となる主な医療費 | 備考 |
|---|---|
| 病院・診療所の治療費 | 通常の診察・入院・手術など |
| 薬局で購入した医薬品 | 市販薬も条件によって対象 |
| 通院にかかった交通費 | 公共交通機関のみ |
| 出産費用 | 分娩費や産後の通院など |
これらの裏ワザを組み合わせて活用することで、家計への負担を軽減しつつ賢く国民健康保険料を節約することが可能です。
詳細はお住いの市区町村によって条件が異なる場合があるため、ご自身の状況に合わせて相談や確認を行うようにしましょう。
高額療養費制度を活用するコツ

高額療養費制度の基礎知識
国民健康保険の加入者が医療機関で自己負担する医療費が、1カ月あたり規定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超過分が後日払い戻される制度が「高額療養費制度」です。
この制度を知っていることで、多額の入院や治療でも家計への負担を大幅に軽減できます。
自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
| 年齢・所得区分 | 自己負担限度額(月額, 医療機関ごと) |
|---|---|
| 70歳未満(年収約370万円未満) | 57,600円 |
| 70歳未満(年収約370万円〜770万円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 70歳以上(住民税非課税世帯) | 8,000円または15,000円 |
一家全員の1ヵ月の自己負担を合算(世帯合算)して限度額を判断できる点も重要です。
たとえば家族で複数人の医療費が高額となった際に限度額まで合算されます。
限度額適用認定証の取得と申請方法
医療機関での支払い時点から自己負担額を抑えたい場合は、事前に「限度額適用認定証」の申請手続きをしましょう。
この認定証を医療機関に提出すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられ、高額な立替払いをせずに済みます。
限度額適用認定証の申請手順は以下です。
- 住んでいる市区町村の国民健康保険担当窓口にて申請書を記入
- 身分証明書や保険証を提示して申込
- 認定証は即日交付または後日郵送(自治体により異なる)
手術や入院が決まったときは、早めに申請しておきましょう。
認定証がない場合、いったん高額な医療費を全額自己負担し、後日償還払い手続きをする必要があるため、受け取り忘れにご注意ください。
高額療養費貸付制度の活用例
もし、認定証が間に合わず高額な医療費をいったん全額立替えが必要になった時は、「高額療養費貸付制度」という一時金貸付の仕組みを利用できます。
これは療養費の支給を受けるまでの間、見込額の8割相当のお金を無利子で借りられる仕組みで、急な入院・手術などで手持ち資金が不足する場合に大変有効です。
利用方法は、市区町村の国民健康保険担当窓口で申請し、必要書類(診療明細や医療機関の請求書など)を提出します。
貸付金は償還払い確定後に相殺されますので、返済の心配がない安心制度です。
高額療養費制度を正しく理解し、早めの申請や認定証の取得によって無駄な立替払いや支払いの不安を防ぎましょう。
減免や免除を最大限に活用する方法

国民健康保険料は、所得や生活状況に応じて減免・免除を受けられる場合があり、これらの制度を正しく理解し活用することで、無理のない保険料負担が可能になります。
制度ごとに対象や申請方法が異なるため、自分の状況を整理し適切に手続きを行いましょう。
所得減少時の減免申請方法
失業や収入の大幅な減少があった場合、国民健康保険料の減免申請ができるケースがあります。
たとえば、倒産・解雇・事業不振などにより前年に比べて所得が著しく減少した場合は、居住地の市区町村に申請することで、保険料の減額や免除が認められることがあります。
減免対象の具体例は以下の通りです。
| 対象者の例 | 主な減免内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 失業者(雇用保険受給資格者) | 所得を実際より低くみなして計算 | 雇用保険受給資格者証、離職票など |
| 事業不振による収入減少者 | 所得割合に応じて減免 | 収支内訳書、収入証明書 |
| 病気やケガで就労不能の場合 | ケースにより免除または減額 | 診断書、所得証明など |
申請は納付期限前に自治体窓口や郵送で行う必要があり、申請時には所得証明や証拠資料の提出が求められます。
詳しい基準や申請方法は自治体ごとに異なることがあるため、事前に確認しましょう。
災害や失業時の特例措置
自然災害や失業などで収入が著しく減った場合、国民健康保険料の特例減免・免除制度があります。
例えば、令和元年東日本台風などの災害時には、被災者を対象とした保険料の全額免除や一定期間の減額措置が実施されました。
また、大規模な事業所閉鎖などによる離職に対しても特例認定を受けられる場合があります。各種特例措置の概要を以下にまとめます。
| 項目 | 措置内容 | 申請手続き |
|---|---|---|
| 災害(風水害・地震等) | 被害状況により全額・一部免除 | 罹災証明書を添えて申請 |
| 大規模リストラ・倒産 | 所得減少を基準に減免 | 離職証明・失業証明書などが必要 |
こうした特例措置は、行政からの告知や新聞・役所HPなどで随時案内されます。
対象になりそうな場合はなるべく早めに自治体窓口へ相談しましょう。
法定軽減措置・特例軽減措置の違いと申請手順
国民健康保険には、法律で定められた「法定軽減」と、各自治体が独自に設ける「特例軽減」が存在します。
それぞれの特徴と申請の流れを以下にまとめます。
| 軽減措置 | 対象条件 | 軽減率 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 法定軽減 | 世帯所得が基準額以下 | 7割・5割・2割のいずれか | 申告に基づき自動適用(要所得申告) |
| 特例軽減 | 低所得世帯やひとり親世帯等 | 自治体独自で追加軽減 | 市区町村窓口で個別に申請 |
法定軽減は所得申告をするだけで自動的に適用されますが、特例軽減は窓口での確認・申請が必要となる場合が多いです。
「自分が対象かわからない」「申請忘れで損したくない」という場合は、早めに役所に相談することで、条件に合ったサポートを受けやすくなります。
なお、法定軽減は国の制度として全国一律で適用され、特例軽減は各自治体の判断で独自に行われるため、住んでいる地域によって内容が異なることもあります。
減免・免除申請は、生活を守るための大切な制度です。困ったときは、ひとりで悩まず自治体窓口や社会保険労務士に相談するのも有効です。
医療費に関する裏ワザと制度

ジェネリック医薬品の上手な使い方
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と有効成分・効果が同じでありながら、開発コストが抑えられているため、自己負担額を大幅に減らすことができる有効な方法です。
医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品に変更したい」と相談することで、多くの医療費が節約できます。
また、ジェネリック医薬品は全国の薬局で利用できるため、処方箋を持っていれば簡単に切り替えることが可能です。
薬の名称や形が変わるケースもあるため、不安な場合は薬剤師に詳細を確認しましょう。
| 項目 | 先発医薬品 | ジェネリック医薬品 |
|---|---|---|
| 価格 | 高い | 安い |
| 効果・成分 | 同じ | 同じ |
| 入手方法 | 医師の処方 | 医師または薬剤師への相談 |
出産育児一時金など各種給付金の利用法
出産時には「出産育児一時金」として、1児につき50万円(令和5年4月以降)が国民健康保険から支給されます。
加入者やその扶養者が出産した場合、申請により直接医療機関へ支給する「直接支払制度」も利用でき、窓口での負担が軽減されます。
さらに、出産時にかかった自己負担額が出産育児一時金を下回る場合は、差額分が還付されます。
その他にも、出産・育児に関連する医療費に対して高額療養費制度や医療費控除を活用すれば、さらに経済的な負担を減らすことが可能です。
| 給付名 | 内容 | 申請先 | 申請時期 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 1児につき50万円(令和5年4月以降) | 市区町村の国民健康保険担当窓口 | 出産後すみやかに |
| 高額療養費 | 医療機関窓口負担の自己負担限度超過分 | 市区町村または保険組合 | 支払いから2年以内 |
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費は所得税控除対象 | 税務署(確定申告) | 翌年2月~3月 |
傷病手当金の対象と手続き
市区町村の国民健康保険では傷病手当金は通常ありませんが、新型コロナウイルス感染症など特別措置や一部の国保組合で傷病手当金が設けられている場合があります。
対象となるのは、被保険者本人が業務外の傷病(病気やケガ)によって働けなくなり、給与が支給されない期間です。
申請には医師の診断書や会社からの証明が必要となるため、勤務先や自治体の担当窓口に確認をしましょう。
申請手続きのポイントを以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 一部国保組合や特例措置の該当者 |
| 必要書類 | 傷病手当金申請書・医師の意見書・勤務先の証明 |
| 給付額 | 標準報酬日額の3分の2程度(自治体や組合により異なる) |
| 申請場所 | 国民健康保険担当窓口・国保組合等 |
乗り換えや変更にまつわる注意点

国民健康保険(国保)は、ライフスタイルや就業状況の変化によって、制度の乗り換えや各種手続きが必要になるケースがあります。
思わぬ保険料の増減や給付漏れを防ぐためにも、変更時の注意点や流れを正しく理解しておくことが重要です。
会社を退職した時の国保と任意継続の比較
会社を退職すると、健康保険の加入先を選択する必要があります。
主に「国民健康保険へ加入」または「今までの健康保険を2年間任意継続する」の2つの方法があり、それぞれのメリットやデメリットを理解しましょう。
| 項目 | 国民健康保険 | 健康保険任意継続 |
|---|---|---|
| 加入手続き | 市区町村で申請 | 退職後20日以内に前の健康保険組合で申請 |
| 保険料 | 前年の所得に基づいて計算。世帯全員分が対象 | 現役時と同額(ただし上限あり)。扶養者の追加不可 |
| 給付内容 | 基本的に変わらない | 失業給付受給中も条件を満たせば加入可 |
| 扶養の扱い | 扶養制度なし。1人ひとりが被保険者 | 家族も被扶養者として加入可(条件あり) |
| 加入可能期間 | 定めなし | 最大2年間 |
所得や家族構成によって保険料が異なるため、事前のシミュレーションが不可欠です。
また、扶養家族の有無や保険給付の範囲も含め、自身にとって最適な選択を考えましょう。
引越し時の国民健康保険の手続き
住所変更や転居をする際は、国民健康保険の手続きが必須です。
新しい自治体ごとに国保が運営されているため、引越しをした場合は必ず届出・手続きを済ませましょう。
| ケース | 必要な手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 市区町村内での転居 | 住所変更届けを提出 | 転居後14日以内 |
| 市区町村外への転出 | 転出前に現在の自治体で脱退手続き、転入後に新自治体で加入手続き | 転出・転入後14日以内 |
この手続きを忘れると、保険証が使えなくなったり、二重徴収や未納のリスクが高まります。
特に他府県への引越しでは、旧自治体の国保と新自治体の国保は繋がっていないため、必ずそれぞれの窓口で手続きが必要です。
世帯主変更とその影響
国民健康保険では、「世帯主」と「被保険者名義」は保険料の計算や納付義務に影響します。
たとえば、世帯主として登録されていた人が転出や死亡した場合、世帯主を変更する必要があります。
世帯主の変更によって、保険料の納付通知先や口座振替、控除申請の内容が変わることがあるため、手続き後はしっかり確認しましょう。
また、世帯主が変わることで「世帯分離」を利用した保険料軽減策も検討可能です。
世帯分離は適切な場合にのみ行い、メリット・デメリットを市区町村に確認しましょう。
乗り換えや変更にともなう手続きや制度の違いを把握し、ご自身の状況に合わせて適切に手続きを進めることが、トラブルを防ぎ、保険料負担を抑えるポイントとなります。
国民健康保険料の支払いを楽にする方法

国民健康保険料は、決して安いものではありません。
支払いが負担になる場合でも、計画的に管理し、適切な方法を選択することで滞納リスクを減らし、家計の負担を軽減することが可能です。
この章では、分割納付や口座振替、さらにはトラブル時の対処法など、支払いをスムーズにする実践的な方法を解説します。
分割納付・口座振替で管理をラクにする
国民健康保険料は、一括での納付が原則ですが、希望すれば分割納付や口座振替を利用できます。
これにより支払い管理が容易になり、納付忘れによる延滞を防ぐことができます。
| 支払い方法 | ポイント | 手続き方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 分割納付 | 納付書に記載の期日ごとに支払い可能 | 自治体から送付される納付書を使用 | 一度に大金を用意する必要がない | 納付書紛失に注意、支払い管理が必要 |
| 口座振替 | 銀行口座から自動引き落とし | 金融機関で所定の申込用紙を提出 | 納付忘れなし・ポイント付与等特典がある場合も | 残高不足だと未納になる可能性 |
分割納付は、納付書に記載された期日ごとに小分けで支払うことができるため、月々の出費を抑えたい方に最適です。
一方で、口座振替は自動で引き落としが行われるため、手続きに手間をかけたくない方や納付を忘れがちな方におすすめです。
分割納付を利用する際の注意点
納付書を紛失した場合や、納付のスケジュールを忘れてしまうと延滞金が発生する恐れがあります。
各自治体の納期をあらかじめ確認し、カレンダーなどで管理しましょう。
また、どうしても支払いが難しい場合は、早めに自治体の保険担当窓口へ相談することが重要です。
口座振替の手続き方法
口座振替の申込は、自治体が指定する用紙に必要事項を記入し、金融機関や自治体窓口で手続きします。
手続きから実際の振替開始までには1~2か月程度かかる場合がありますので、余裕をもって申し込むことが大切です。
延滞金や督促状への対処法
国民健康保険料の納付が遅れると、自治体から督促状が送付され、延滞金が発生する場合があります。
支払いが困難になった際は、絶対に放置せず自治体窓口に相談しましょう。
放置すると短期被保険者証の発行や最悪医療機関で自己負担額が100%になる場合もあります。
| 状況 | 取るべき行動 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 支払いが一時的に難しい | 自治体へ分割納付や納付猶予の相談 | 早めの相談が減免等の適用対象となる可能性あり |
| 督促状が届いた | 速やかに支払う、もしくは自治体へ事情説明 | 無視すると財産差押え等のリスクがある |
| 延滞金が発生した | 延滞金と併せて全額納付、もしくは相談 | 減免対象となるケースもあるため確認を |
特に、長期的な滞納は厳しいペナルティにつながります。やむを得ない事情がある場合は、必ず自治体に連絡を取り、分割納付や支払い猶予・減免制度の活用を検討しましょう。
また、税金の還付金や給与振込口座と保険料の口座が同じ銀行の場合は、差押えリスクも理解しておきましょう。
このように、国民健康保険料の支払いを無理なく管理するためには、自身の家計状況や納付スケジュールにあった最適な方法を見つけることが大切です。
トラブルが起こる前に、積極的に自治体窓口へ相談し情報収集を行うことが、安心して医療を受けるための大切なステップとなります。
よくある質問と誤解されやすいポイント

収入ゼロでも保険料は必要か
国民健康保険は、たとえその年度の収入がゼロや極端に少なくても、原則として最低限の均等割・平等割分の保険料がかかります。
ただし、市区町村の条例等で定められている所得が一定額以下の世帯や、生活保護受給中の場合などは減免や免除の対象となる場合があります。
年度ごとに世帯全体の所得状況を必ず申告し、必要に応じて減免申請を行うことで、負担を軽減できる可能性があります。
| ケース | 保険料の取扱い |
|---|---|
| 今年度の所得がゼロ | 原則保険料は必要。減免・免除申請を推奨 |
| 生活保護を受給 | 原則保険料なし(申請不要) |
| 無申告 | 未申告だと保険料が最高額に設定される場合あり |
子どもの保険証はどうなる
国民健康保険に加入している世帯では、生まれた子どもも出生届受理と同時に国民健康保険に自動的に加入し、保険証が発行されます。
ただし、出生届の際に国民健康保険資格取得届の手続きを行う必要があります。
また18歳未満の子どもでも、親が国民健康保険をやめた場合や世帯主変更などの際は、同様の手続きが必要です。
| 状況 | 手続き内容 |
|---|---|
| 出生 | 出生届+国民健康保険加入手続き |
| 引越し | 転入届+国民健康保険加入手続き |
| 世帯主が変更 | 世帯主変更届+必要に応じて保険証再発行 |
国民健康保険では、年齢や親の扶養に関わらず子どもごとに個別の保険証が発行されるため、紛失や有効期限切れに注意が必要です。
扶養に入れる方法はあるのか
国民健康保険に「扶養」という制度は存在しません。 会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ・組合健保等)と異なり、世帯での一括加入となり、家族全員が被保険者となります。
そのため、所得や年齢による「扶養控除」は税制上の適用は可能ですが、健康保険料の計算上での「扶養制度」はないため注意が必要です。
| 保険種類 | 扶養家族の取り扱い |
|---|---|
| 国民健康保険 | 扶養区分なし。家族全員が被保険者 |
| 協会けんぽ・組合健保 | 年間収入等の条件あり。「扶養家族」は保険料不要 |
60歳未満で無職の家族などについては、世帯分離などで保険料負担を調整できるケースもありますが、「扶養に入れる」健康保険とは仕組みが異なることに注意しましょう。
まとめ
国民健康保険は制度の仕組みや各種制度、高額療養費制度や減免措置、世帯分離などを上手に活用することで、大幅な負担軽減につながります。
正しい知識と各種手続きをしっかり行い、ご自身やご家族のライフステージに合わせて最適な節約方法を選択しましょう。